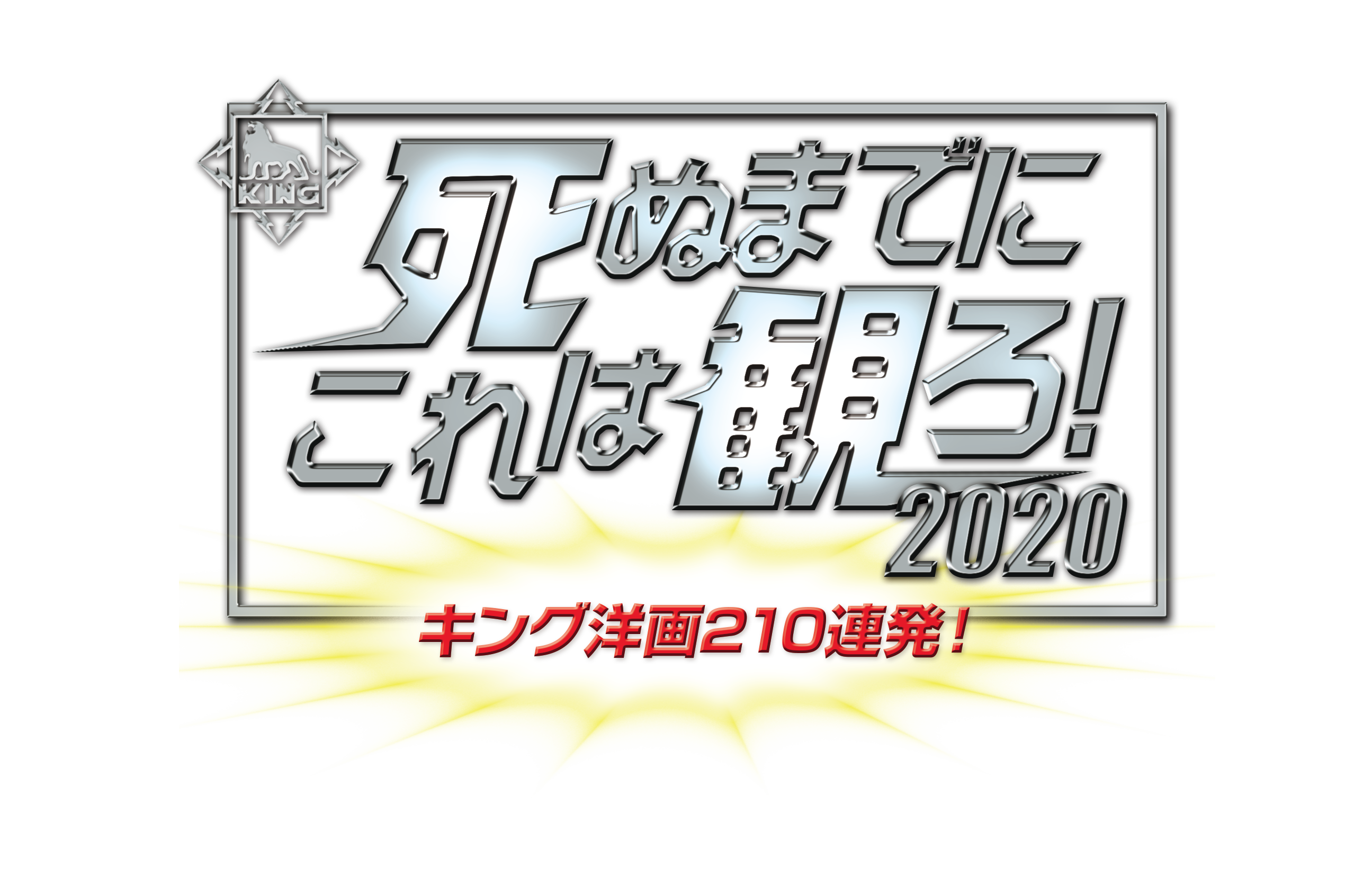「死ぬまでにこれは観ろ!2020」 松崎健夫(映画評論家)×三宅隆太(映画監督・スクリプトドクター)【後編】
- 死ぬまでにこれは観ろ , 松崎健夫 , キネマ旬報 , キングレコード , 三宅隆太 , ムービーウォッチメン , アフター6ジャンクション
- 2020年08月06日
「死ぬまでにこれは観ろ!2020」 松崎健夫(映画評論家)×三宅隆太(映画監督・スクリプトドクター)【後編】

前編に続き、キングレコードの「死ぬまでにこれは観ろ!2020」を、すでに多くを購入済みだけど廉価版にはやはり手が伸びてしまう痛し痒し嬉し恥ずかしの映画評論家・松崎健夫と、ラジオ番組『アフター6ジャンクション』でもおなじみ、映画監督・スクリプトドクターの三宅隆太のお二人に語っていただいた。
※「死ぬまでにこれは観ろ!」シリーズとは・・・アクションやドラマ、ホラーなど多彩なバリエーションに富み、名作・快/怪作・珍作までを揃えた知る人ぞ知る人気シリーズ。7年目を迎え、今年はブルーレイ112タイトル、DVD98タイトル、計210タイトルの洋画が揃う。3枚買うともれなく1枚もらえるというお得な特典もある。
今だからこそ観るべきもの

(前編の続きから)
三宅 「ヤングガン2」(90)も印象に残っていますね。西部劇って父親もしくはもう少し上の世代がドンピシャで、世代的にはちょっと気後れがあった。そういう〝ジャンルとしての敷居の高さ〟を僕らの世代のものにしようとアプローチしたのが「ヤングガン」(88)シリーズ。往時のファンからすると気になるところは多々あると思いますが、僕らはこれを観て西部劇はそんなに難しくないかもしれない、よし、じゃあ過去の作品も観てみよう! っていうふうに考えられるようになった。昔は今より映画を観るには不便でしたが、映画をたくさん観られる今の方が豊かじゃない気がする。だからこそ、こういったジャンルの話をきっかけに古い作品も観てほしい。「ザ・クレイジーズ」(73)なんて、もろじゃないですか。
松崎 今に置き換えて観られます。
三宅 「アウトブレイク」(95)の基になった映画、オープニングの画から怖い。
松崎 確か、お父さんは影だけで、ちゃんとは見せないんですよね。
三宅 今なら配慮してカットするような、〝悲劇的な親の喪失〟に子どもが恐怖を感じる場面ですね。「ミディアン」(90)にも似たようなシーンがある。親が殺されるのを2階で目撃した子どもに向かって、殺人鬼が階段を上ってくるシーンは怖かった。
松崎 デイヴィッド・クローネンバーグが殺人鬼役で出ているんですが、容赦ないんですよ。子どもにそれを見せていいかどうかと、今の時代、議論されますが……。
三宅 本来ホラーは教育的なジャンル。甘々なことだけ見せていたらかえって無責任なんじゃないかと、現役の作り手としては思いますけどね。実際、恐怖という感情を映画で疑似体験するのは、現実の生きる力を育む効果にもなるわけで。それで言うと、「SF核戦争後の未来・スレッズ」(84)は容赦ない。ほぼ同じ時期にアメリカでも『ザ・デイ・アフター』(83)があったけど全然違う。イギリスの「スレッズ」は核戦争後の随分先まで描く。それが怖くてトラウマに。子どもの頃、テレビで観て死ぬかと思いましたが、観ておいて本当に良かった。
松崎 この作品を観て核爆弾を持ちたいと思ったとしたら、頭がおかしいと思いますよね。
三宅 核戦争後の未来は何十年もあとの世界のはずなのに、あたかも今そこにある世界のようにドキュメンタリータッチで見せられるのは、すごく怖いし、我がこととして考えさせられる。廉価版になってまた多く人に観てもらえるのは本当にいいことだと思います。
松崎 そういう意味では、今観るべき映画は今回、結構ありますね。
三宅 偶然かもしれませんが、今回のラインアップは、特にそういう傾向が強いと思います。「マッドボンバー」(72)の孤独だってそう。でもどの映画も現実世界を生き抜くためのヒントや希望も描いている。それはおそらく、映画が愛されていた時代、映画が娯楽の王様だった時代には、作り手側が誇りを抱き、矜持を持って作ることができていたからだと思います。だからこそ辛い場面も忖度せずにあえて見せる。それは責任感の表れでもあったはず。
松崎 「ヤングガン」はそこまで評価されていないけど、サム・ペキンパーがやっていたスローモーション手法や、〝アメリカの夜〟といって、疑似夜景で撮っていた昔の西部劇にはできなかった、夜間撮影をバンバンやって、「第三の男」(49)でやった影の中から顔が浮かび上がる陰影の表現など、映画的な教養を投入しているんですね。それを、当時のスターを配してやってみせた。今観ると古いと思うかも知れないけど、この時だって西部劇は古いと言われていた時代だったことを再確認するための、線につながる点としては、すごくいい作品だと思います。
三宅 「〜2」も凄くいいです。今の話に乗っかると、それはアップデートしているということですよね。日本でも「るろうに剣心」(12)が殺陣アクションを今風にすることでチャンバラの魅力を伝えていったことに非常に近い。「ヤングガン」って実はリメイク、続篇ブームの先駆けじゃないかと思います。
吹き替え版の楽しみ方

松崎 また、このシリーズは吹き替え版が充実。テレビで映画を観てきた世代にとっては何種類か入っているのも嬉しいですね。僕は吹き替え版を観る時、日本語字幕を出して観るんです、翻訳との違いが分かって面白い! 例えば字幕では2個のところがセリフでは4個になっていたり。
三宅 凄い時はキャラが変わっていることもありますよね(笑)。でも、それらは単なる思いつきじゃなくて、当時の「茶の間」で、家族が揃って映画を観るという状況を鑑みたうえでの、実は相当にクリエイティブな〝超訳〟であることが多い。今回のラインアップにも、良質で考え抜かれた当時の吹き替え音声が収録された作品がたくさんある。作り手の矜持だけじゃなく、洋画をテレビ画面を通じて日本人に届けようとしていた吹き替え版制作者たちの矜持が垣間見えるのは貴重です。
松崎 そうだ! 一本凄くお薦めしたい作品がありました。「あの頃、君を追いかけた」(11)のギデンズ・コー監督の「怪怪怪怪物!」(17)。今年、ラインアップされた作品ですが、どろどろのホラーで驚きました。いじめの話ですが、映画館で観た時に笑っている人がいて、それが不快で。監督も笑っていたらダメじゃないかと思わせるところに意図があると仰っていましたが、最終的に笑っていた連中が青ざめるようなラスト。いじめ問題のリトマス試験紙になるような、まさに今の時代の映画です。
三宅 僕は「狼チャイルド」(17)ですね。物の怪の血を引いている子どもがどう生きていくのかという物語で、これも偏見と差別の話だけど、洗練された繊細な映画で、とても誠実です。フランス=ブラジルの合作というのも意外でした。「ヘル・レイザー」(87)「ベン」(72)「ウイラード」(71)など、昔の作品は、ジャンルの秩序や軌道をうまく使って、現実的な人間の苦しみや、そこからどう脱するべきかを描くものが多かった。今見ても発見は多いと思いますね。
松崎 話せばきりがないですが、「狼チャイルド」は廉価版が出るまで待てそうにないので、帰ったら即買います。
三宅 松崎さんとは初対面なのに、こんなに盛り上がる(笑)。「死ぬまでにこれを観ろ!」シリーズにはそういう力がありますね。あとづけの知識とか権威じゃなく、ワクワクしながら映画を観ていたころの恥ずかしい思い出も含め語りたくなるラインアップを、次世代にも是非お薦めしたいですね。
布教のために選ぶなら!? 渾身の3枚をセレクト
「死ぬまでにこれは観ろ!」シリーズの凄いところは、廉価の上に3枚買うともれなく1枚もらえるという画期的なシステム。お二人はこの特典を活かして、知人へのプレゼント(これを布教活動と呼んでいる?)にも利用しているとのこと。
そこでお二人から「これは観ろ!」という3枚をセレクトして頂いた。

松崎セレクト
「ストリート・オブ・ファイヤー」(84・米)
「まぼろしの市街戦」(67・仏)
「ランブルフィッシュ」(83・米)
三宅セレクト
「コンボイ」(78・米)
「追想」(75・仏)
「地球爆破作戦」(70・米)

㊧松崎健夫(まつざき・たけお)/1970年生まれ、兵庫県出身。東京藝術大学大学院映像研究科映画専攻修了。テレビ、映画の現場を経て、映画専門の執筆業に転向。数多くのテレビ、ラジオ、ネット配信の情報番組に出演。本誌ほか、映画の劇場用パンフレットなどに多数寄稿。キネマ旬報ベスト・テン選考委員、田辺・弁慶映画祭審査員、京都国際映画祭クリエイターズ・ファクトリー部門審査員などを務める。共著『現代映画用語事典』(キネマ旬報社刊)ほか。
㊨三宅隆太(みやけ・りゅうた)/1972年生まれ、東京都出身。若松プロダクションの助監督を経て、フリーの撮影・照明助手となり、その後脚本家・映画監督に。スクリプトドクターとして、国内外の映画企画に参加するほか、東京藝術大学大学院やシナリオ教室等で講師を務めている。著書に『スクリプトドクターの脚本教室』シリーズなどがある。映画「クロユリ団地」(13)「ホワイトリリー」(15)、21年公開予定のアニメ「神在月のこども」などで脚本を担当。
文=岡﨑優子/制作:キネマ旬報社(キネマ旬報8月下旬号より転載)