咽び唄の里 土呂久
むせびうたのさととろく- 上映日
- 1976年5月21日
- 製作国
- 日本
- 制作年
- 1976
- 上映時間
- 90分
- レーティング
- 一般映画
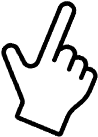 解説
解説
土呂久を中心とした休廃止鉱山による公害を告発する記録映画。映像集団エラン・ヴィタルの第一回作品。宮崎県西臼杵郡高千穂町大字岩戸、祖母山の麓にある土呂久集落。昭和46年11月13日に開かれた宮崎県教組の第21次教育研究集会で、高千穂町の岩戸小学校の斎藤正健教諭が、土呂久に存在する公害を告発した。江戸時代から金銀の採れる鉱山として有名であった土呂久では、大正7年から硫砒鉄鉱が採掘され、鉱石を焼いて毒ガスや殺虫剤の原料となる亜ヒ酸が製造されていた。昭和8年には中島鉱山株式会社が土呂久の鉱業権を取得、硫砒鉄鉱の乱掘を開始した。37年に休山(中島鉱山は42年に会社解散、現在の鉱業権は住友金属鉱山が所有)になってからは、住民たち(46年末現在、55世帯・二六九人が居住)は農業で生活していたが、彼らの肉体は(1)鉱山操業中に鉱石を焼いてでた有害な煙と、(2)放置されている鉱石および鉱滓、ズリによって汚毒された飲用水--のために蝕まれていた。鉱毒による被害が出だしたのは、亜ヒ酸の生産が始まった大正7年からで、53年にわたる操業期間中に多くの住民と鉱山の従業員が鉱毒のために死んでいったのである。斎藤教諭の告発がきっかけになって「土呂久鉱害被害者の会」と「土呂久・松尾等鉱害の被害者を守る会」が結成され、鉱害を放置した宮崎県当局を相手取って現在裁判闘争を行っている。なお、鉱害の出るおそれのある休廃止鉱山は、日本全国で約七千カ所もあるとのことである。映像集団エラン・ヴィタルのスタッフが土呂久でカメラを回しはじめたのは昭和47年夏からだが、途中で二年間ぐらい撮影を中断、本格的に撮りだしたのは50年6月からである。撮影終了は、51年3月。カメラマンの佐々木彦人が、土呂久に半年以上常住した。カメラは、アリフレックス。録音機は、ソニーのカセット・デンスケ。15時間分のフィルム(おもにコダックのプラスX)を使用。土呂久のほかに、やはり亜ヒ酸の鉱害の出ている休廃止鉱山である宮崎県の松尾と島根県の笹カ谷を撮っている。映像集団エラン・ヴィタルは、明治大学の映画史研究会のメンバーが昭和46年に創設した映画製作をめざすグループで、「土呂久」と同時にやはり記録映画である「塩」を製作したが、記録映画にこだわらずにこれから劇映画も製作していくつもりだとのことである。(16ミリ)
映画館で観る
配信で観る
Blu-ray&DVDで観る
TVで観る
ユーザーレビュー
「咽び唄の里 土呂久」のストーリー
※本作はドキュメンタリーのためストーリーはありません。
「咽び唄の里 土呂久」のスタッフ・キャスト
| スタッフ |
|---|
| キャスト | 役名 | |
|---|---|---|

「咽び唄の里 土呂久」のスペック
| 基本情報 | |
|---|---|
| 製作国 | 日本 |
| 製作年 | 1976 |
| 公開年月日 | 1976年5月21日 |
| 上映時間 | 90分 |
| 製作会社 | 映像集団エラン・ヴィタル |
| 配給 | その他 |
| レイティング | 一般映画 |
| アスペクト比 | スタンダード(1:1.37) |
| カラー/サイズ | モノクロ |
関連するキネマ旬報の記事
| 関連記事一覧 | |
|---|---|
| 1976年9月下旬号 | 日本映画紹介 咽び唄の里 土呂久 |

















