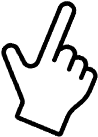 解説
解説
小泉八雲の“怪談”より和解(黒髪)、雪女、耳無抱一、茶碗の中の話、を「甘い汗」の水木洋子が脚色「切腹」の小林正樹が監督した文芸もの。撮影もコンビの宮島義男。第38回キネマ旬報ベスト・テン第2位、第18回カンヌ国際映画祭審査員特別賞受賞。1965年1月6日よりロードショー。1965年2月27日より全国公開。カンヌ出品版として161分の短縮版が存在する。
ユーザーレビュー
「怪談(1964)」のストーリー
〔黒髪〕昔京都で生活に苦しんでいた武士が、貧乏に疲れ、仕官の道を捨てきれずに、妻を捨てて、遠い任地へ向った。第二の妻は、家柄、財産に恵まれていたが、我侭で冷酷な女であった。男は今更のように別れた妻を慕い、愛情の価値を知った。ある晩秋の夜、荒溌するわが家に帰った男は、針仕事をする静かな妻の姿を見て、今迄の自分をわび、妻をいたわり、一夜を共にした。夜が白白と明け男が眼をさますと、傍に寝ていた妻は髪は乱れ、頬はくぼみ、無惨な形相の経かたびらに包まれた屍であった。 〔雪女〕武蔵国の若い樵夫巳之吉は、茂作老人と森へ薪をとりに入り、吹雪に出会って、山小屋に閉じこめられた。その夜、若者は、老人が雪女に白い息を吹きかけられて殺されたのを目撃したが、巳之吉は「誰にも今夜のことを話さないように。話したら必ず殺す」と言われ助けられた。三十近くなった巳之吉は、森の帰路出会った、美しい娘お雪を妻に迎え、子供も出来て、仕合せな日々を過していた。正月も真近にひかえたある夜、子供の晴着に針を運ぶお雪の顔をみて、山小屋の雪女を思い出した巳之吉は、妻に思わずその話しを聞かせた。お雪は「それは私です」と言うと、うらみを残して吹雪の中に消えていった。 〔耳無抱一の話〕西海の波に沈んだ平家一門の供養のために建てられた赤間ケ原に、抱一という琵琶の名人がいた。夜になると、寺を抜け出し、朝ぐったりして帰って来る抱一を、不審に思った同輩が、秘に後をつけると抱一は、平家一門の墓前で恍惚として平家物語を弾じていた。平家の怨霊にとりつかれた抱一は、高貴な人の邸で琵琶を弾じていると思っていたのだ。寺の住職は、抱一の生命を心配すると、抱一の身体中に経文を書き、怨霊が迎えに来ても声を出さないよう告げた。住職の留守に迎えに来た怨霊の武士は、返事がないまま、抱一の琵琶と耳を切って持ち帰った。住職が耳に経文を書くのを忘れたのだ。以後抱一は耳無抱一と呼ばれ、その名声は遠く聞こえた。 〔茶碗の中〕中川佐渡守の家臣関内は、年始廻りの途中茶店で、出された茶碗の中に、若い男の不気味な笑い顔を見た。それは、茶碗を何度とりかえても、同じように現われた。豪胆な関内は、一気に飲みほして帰ったものの、不思議に思った。佐渡守の邸に帰った関内を、見知らぬ若い侍が訪ねて来た。その顔は、茶碗の底の不気味な顔であった。問答の末、関内は男を斬ったが、男は音もなく消えた。帰宅した関内は、三人の侍の来訪を受けた。今日の若い侍の家臣と称する三人は、来月十六日に主君が今日の恨みを晴らしに来ると告げると、関内の刀をかわして、影のように消えた。
「怪談(1964)」のスタッフ・キャスト
| スタッフ |
|---|
| キャスト | 役名 | |
|---|---|---|

「怪談(1964)」のスペック
関連するキネマ旬報の記事
| 関連記事一覧 | |
|---|---|
| 1964年4月上旬春の特別号 |
「怪談」クランク5分前 特別グラフィック 「怪談」製作いよいよ本格化 「怪談」クランク5分前 「怪談」に賭けた2人の男 2大シナリオ特別一挙掲載 怪談 |
| 1964年11月上旬号 |
日本映画紹介 怪談 原作寸描 小泉八雲の「怪談」 |
| 1965年2月上旬決算特別号 |
旬報試写室 怪談 旬報試写室 怪談 |
| 1965年2月下旬号 | 日本映画批評 怪談 |
| 1965年3月下旬号 | 特集レポート 独立プロ 〈その現実と大企業との関係〉 「怪談」製作白書序説 |

















