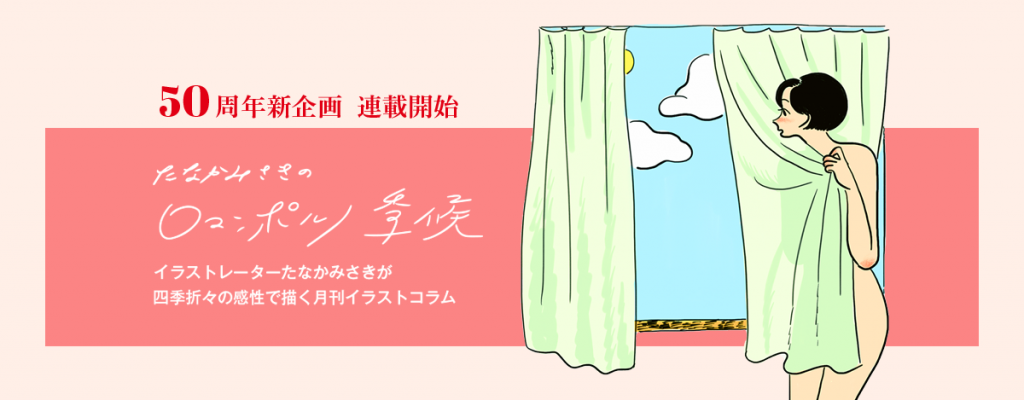【あの頃のロマンポルノ】プロフェッショナル 藤田敏八
- 日活ロマンポルノ50周年 , 藤田敏八
- 2021年12月17日
2021年に、日活ロマンポルノは生誕50年の節目の年をむかえました。それを記念して、「キネマ旬報」に過去掲載された記事の中から、ロマンポルノの魅力を様々な角度から掘り下げていく特別企画「あの頃のロマンポルノ」。キネマ旬報WEBとロマンポルノ公式サイトにて同時連載していきます。
今回は、「キネマ旬報」1975年9月上旬号より、寺脇研氏による「プロフェッショナル藤田敏八」の記事を転載いたします。
1919年に創刊され100年以上の歴史を持つ「キネマ旬報」の過去の記事を読める貴重なこの機会をお見逃しなく!
プロフェッショナル藤田敏八
『野良猫ロック ワイルドジャンボ』(70)、『八月の濡れた砂』(71)での、若者たちを溶かし込んでしまうような、激しい夏の光は印象的だ。日が眩む強烈な光の氾濫の中で、肢体が躍動する。
藤田敏八にとって、夏の思い出は、朝鮮で過ごした少年時代と重なる。半島の乾いた夏だ。父親が朝鮮鉄道の社員だったため、生地の平壌をふりだしに、各地を転々とした。日本人学校だけでなく、現地の子たちと共学の学校に通った土地もある。そこで、さまざまな形での差別を見、子供心にそれを理不尽に感じたという。だが、植民地生活の深刻な部分は、子供たちの耳目に入らないようになっていた。のびのびと、平和な少年時代。朝鮮の夏を、彼は今も懐かしむ。
朝鮮で迎えた13回目の夏、8月15日が来た。特別な感慨は覚えなかった。父は勤務の都合で北部におり、母と弟妹とともに、彼は釡山にいた。食べるため、貨車から大豆を盗んだりしたのを記憶している。自分が家族を守っていかねばならない、という気負いを感じていた。まだ中学2年生の少年には、重すぎる体験だったに違いない。
父親が戻らぬまま、一家は郷里の三重県四日市に引揚げた。地元の中学に編入する。引揚げ者としての疎外感を味わった。やがて抑留されていた父が帰国し、再び家族が揃う。高校は県立四日市高校。あまり本を読んだりしなかった。映画も見ていない。もっぱらスポーツに打込んだ。陸上競技部に属した。チーム競技でなく、個人の筋肉や瞬発力がそのままの形で発揮されるスポーツを選んでいるのが興味深い。その一方では、アルバイトで石鹸の行商などをしていた。
家庭は、ごく普通の小市民生活だった。父親は、まじめな人で、ことさら厳格というわけでもなかった。母親は、教師の経験もある人だったが、教育熱心で口うるさいなどということはなかった。それでも、周囲には、何となく息苦しい雰囲気があった。母方の叔父が県知事や国会議員をつとめる政治家であったりして、そうした権力への志向性が、まわりに色濃かったのだ。これに反撥していた。また、主体性がはっきりしない、三重県人のあいまいな県民性も厭だった。5年余り過ごした四日市の町を、彼は今でも好きになれないという。
“非行少年”ではなかった。闇市に出入りしたようなことはあったけれど、本格的な非行はしていない。“非行少年”というのが、今のように軽いイメージと違う。犯罪者同然に見られている時代だ。
家は、大学なぞ行かなくてもーーだったが、一浪の後、東大に入学し、上京する。将来については、別にどうとは考えていなかった。だから、駒場の教養学部では、バスケット部にはいったりして、普通に学生生活を始めた。学内の駒場寮にいたせいもあり、授業にも良く出席。
2年のとき、合演というサークルで演劇活動を始める。福田善之(劇作家)、渡辺文雄(俳優)などが一緒だった。芝居に、急速に惹かれだす。映画は念頭になく、演劇を志した。戦後の新しい新劇が生まれようとしていた頃だ。夢中になる。
本郷の文学部、仏文学科へ進む。当時は教養から学部へ移るとき試験があり、仏文は人気学科だったから難問だった。同級に石堂淑朗(作家)、井出孫六(作家)、種村季弘(詩人)、そして吉田喜重。ここでは、もう、ほとんど授業には出なかった。
で、その代わり、俳優座の養成所に通っていた。養成所5期生。ここでの同期は矢野宣、平幹二朗、亡くなった木村俊恵ら。かたわらでアナウンス学校にも通った。もし、そのまま俳優の道を歩いていたら、と想像してみるのは楽しい。俳優・藤田敏八。さぞ個性的な性格俳優になっていたろう。監督となっている現在でも、風貌を買われて、しばしば画面に登場するくらいだから。
後に『新宿アウトロー ぶっ飛ばせ』(70)で、成田三樹夫を初めて使ったとき、ボクは養成所で先輩だと言って驚かせたという話がある。

▲『八月はエロスの匂い』の撮影中の藤田敏八監督
まだ、新劇俳優で食っていくのが難しい世の中だった。役者では生活していけぬ、と思い、どこか就職しようと考えたが、行きたいところは、もう皆、試験が終わってしまっていた。残るは映画会社だけ、というので、日活と松竹に願書を出した。特に映画をやりたかったわけではない。成りゆきのようなものだった。ただ、映画は、養成所時代あたりから、熱心に見るようになっていた。日本映画では木下恵介のファンだった。『女の園』(54)などが印象に残っているという。
結局、知人のいた日活だけを受けた。映画全盛期にはいろうとする頃で、縁故者の推薦制にもかかわらず、800人近い受験者があり、その中から11人が採用された。試験官には中平康や鈴木清順がいた。創作試験のテーマは「窓」。窓のない、密室の物語を作った。合格。昭和30年。前年に製作を再開した新生・日活の3期組だ。他に遠藤三郎、千野皓司がいる。
多摩川撮影所に行くと、いきなり市川崑組『青春怪談』に放り込まれた。助監督の仕事がどんなものなのか、カチンコを鳴らすくらいしか知らなかった。五里霧中。すぐ次には西河克己組、滝沢英輔組--と、息つく間もなく5本、1年目につく。チーフ助監督だった舛田利雄や蔵原惟繕に鍛えられた。
助監督生活は辛く、特に映画をやりたくてはいったわけではないから、いつやめてしまおうか、と考えていた。そんなとき、ブニュエルの『忘れられた人々』を見る。刮目した。映画そのものを見直した。これほどまでみごとに自分のイメージを作り出せるのか、と。初めて、自分の映画を作りたい、という気持になった。
日活多摩川は、若々しい活気に満ちていた。次々と新しい才能が登場していった。助監督として、蔵原組を中心に、多くの作家についた。蔵原惟繕『愛の渇き』(67)の脚本が名高い。
そろそろーーと思っていた昭和42年、監督昇進の話が出た。番組に穴があき、吉永小百合ものの併映作が急遽必要になって、何かないか、ということになったのだ。前々から気になっていた、シナリオ誌所載のひとつの脚本を、企画として提出した。未知の間柄だったが、その作者は、松竹助監督の広瀬襄。そして、封切日に追われるあわただしい撮影。ーーこれが、『非行少年 陽の出の叫び』(67)だ。
評判になり、次に、浦山桐郎ら2監督と共同で『日本の若者たち』(68)というドキュメンタリーを撮る。だが、非公開となる※『にっぽん零年』として2002年に公開。しばらく沈黙が続くが、デビュー作の直後に次回作として準備していた企画が世に出ることになる。『非行少年 若者の砦』(70)。これが、いわゆる日活ニュー・アクションの先駆けとなった。
日活は傾き始め、ダイニチ映配が発足する中で、『野良猫ロック ワイルドジャンボ』(70)。ホリ・プロの歌謡映画を、もののみごとに自分の世界のものにして、若さを描きとった。『新宿アウトロー ぶっ飛ばせ』(71)『野良猫ロック 暴走集団'71』(71)『八月の濡れた砂』(71)ーと続く。
藤田敏八の映画作家としての声望が高まるのとうらはらに、日活は窮地に陥り、ポルノへ転進した。最初、ポルノは撮れない、と思ったという。性表現が100%可能でない限りは、真に性を描けないと考えたからだ。性表現には、0か100かしかないという姿勢だった。
けれど、日活ポルノが当局に摘発され、裁かれる事態が生じたとき、ポルノを作らねばならぬ、と決心した。大きな力で圧してくるものに対し、手むかわずにはいられなかった。『八月はエロスの匂い』(72)『エロスの誘惑』(72)『エロスは甘き香り』(73)。しかし、ポルノはやはり体質に合わず、これらの諸作も、性そのものを主題にすることはできなかった。
 ▲『八月はエロスの匂い』より
▲『八月はエロスの匂い』より
以後、東宝で『赤い鳥逃げた?』(73)『修羅雪姫』(73)『修羅雪姫 怨み恋歌』(74)。秋吉久美子三部作と言われる『赤ちょうちん』(74)『妹』(74)『バージンブルース』(74)。そして、加藤彰と合作の『炎の肖像』(74)。不評だった「修羅雪姫」シリーズの、錦絵風の明治から現代が浮かび上がってくる感じと、耽美的な画面が印象に残る。
前作から半年余、次回作の予定はないという。現在の日本映画の状況に、少なからず絶望しているという。撮らないことによる自己主張。だが、映画作家は作品でものを言わなければならない。三島由紀夫の「美しい星」など1ダース近くもあるという企画が、作品の形をとることを待ち望みたい。
ニュー・アクションの作品群で連帯の熱さを描いた70年。秋吉久美子を得て、人間の絆の脆さを持ち出すことで連帯に背を向けた74年。時代と自己、自己と時代のかかわりを見つめていこうとする藤田敏八監督、次はどのような状況を掴むのか。
75年、夏。その長身が、なぜか弱々しく見えてしまう。「『新幹線大爆破』のような秀れた映画がヒットしない現実を映画人は自身の痛みとして感じるべきだ」という言葉が忘れられない。
愛称‟パキさん” 。彼ほど同業者中にファンを持つ人も少なかろう。
自作以外の脚本は『愛の渇き』『戦争を知らない子供たち』(73・共作)など。テレビでの仕事はほとんどなく、「颱風とざくろ」「夕陽ヶ丘3号館」などを伺本か演出しているだけだ。
文・寺脇研
「キネマ旬報」1975年9月上旬号より転載
藤田敏八 / ふじた としや
昭和7年1月16日朝鮮平壌生まれ。弟、妹が1人ずつ。終戦で引揚げ、三重県四日市市で中学、高校時代を過ごす。県立四口市高校から26年東大文学都へ。30年日活に入社。助監督として多くの監督につくが,蔵原惟繕、滝沢英輔などに影響を受ける。
「日活ロマンポルノ50周年×キネマ旬報創刊100周年」コラボレーション企画、過去の「キネマ旬報」記事からよりすぐりの記事を掲載している特別連載【あの頃のロマンポルノ】の全記事はこちらから

日活ロマンポルノ50周年企画「みうらじゅんのグレイト余生映画ショー in 日活ロマンポルノ」の全記事はこちらからご覧いただけます。

日活ロマンポルノ50周年新企画 イラストレーターたなかみさきが、四季折々の感性で描く月刊イラストコラム「ロマンポルノ季候」