ビルマの竪琴(1985)
びるまのたてごと The Burmese Harp
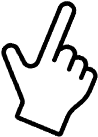 解説
解説
日本兵の霊を慰めるため、僧侶となってひとりビルマの地に残る兵士の姿を描く。竹山道雄の同名小説の29年ぶりの再映画化。脚本、和田夏十、監督、市川崑は前作と同じコンビ。撮影は「あゝ野麦峠・新緑篇」の小林節雄がそれぞれ担当。
ユーザーレビュー
「ビルマの竪琴(1985)」のストーリー
一九四五年夏、ビルマ戦線の日本軍はタイ国へと苦難の撤退を続けていた。そんな逃避行の最中、手製の堅琴に合わせて「埴生の宿」を合唱する一部隊がいた。井上小隊長が兵士の心をいやすため、歌を教えこんだのである。堅琴で判奏するのは水島上等兵であった。小隊は国境近くまで来たところで終戦を知り、武器を棄てて投降した。彼らは南のムドンに護送されることになったが、水島だけは附近の三角山で、抵抗を続ける日本軍に降伏を勧めるため隊を離れて行った。小隊はムドンで労務作業に服していたが、ある時、青いオウムを肩に乗せた水島そっくりの僧とすれ違った。彼らは僧を呼び止めたが、僧は一言も返さず歩み去って行った。三角山の戦いの後ムドンへ向かった水島は、道々、無数の日本兵の死体と出会い、愕然としたのである。そして自分だけが帰国することに心を痛め、日本兵の霊を慰めるために僧となってこの地に止まろうと決意し、白骨を葬って巡礼の旅を続けていたのだ。物売りの話から、井上はおおよその事情を推察した。彼はもう一羽のオウムを譲りうけ、「オーイ、ミズシマ、イッショニ、ニッポンニカエロウ」と日本語を覚えこませる。数日後、小隊が森の中で合唱をしていると、大仏の臥像の胎内にいた水島がそれを聞きつけ、思わず夢中で堅琴を弾き始めた。兵士たちは大仏の鉄扉を開けよとするが、水島はそれを拒んでしまう。その夜、三日後に帰国することが決まり、一同は水島も引き連れようと毎日合唱した。井上は日本語を覚えこませたオウムを水島に渡してくれるよう、物売りの老婆に頼んだ。出発の前日、水島がとうとう皆の前に姿をあらわした。収容所の柵越しに、兵士たちは合唱し、一緒に帰ろうと呼びかけるが、水島は黙ってうなだれ、「仰げば尊し」を弾奏した。そして、森の中へ去って行く。翌日、帰国の途につく井上のもとへ、オウムが届いた。オウムは「アア、ヤッパリ、ジブンハ、カエルワケニハ、イカナイ」と叫ぶのだった。
「ビルマの竪琴(1985)」のスタッフ・キャスト
| スタッフ |
|---|
| キャスト | 役名 | |
|---|---|---|

「ビルマの竪琴(1985)」のスペック
関連するキネマ旬報の記事
| 関連記事一覧 | |
|---|---|
| 1985年6月下旬号 |
グラビア ビルマの竪琴 特集 ビルマの竪琴 市川崑監督作品 対談 市川崑×荻昌弘 特集 ビルマの竪琴 市川崑監督作品 撮影ルポ 特集 ビルマの竪琴 市川崑監督作品 作品評 特集 ビルマの竪琴 市川崑監督作品 脚本 |
| 1985年8月下旬号 |
グラビア ストップ・メーキング・センス 特集 ストップ・メイキング・センス ジョナサン・デミィ監督作品 作品&監督研究 日本映画批評 ビルマの竪琴 |
| 1985年9月上旬号 |
日本映画批評 ムッちゃんの詩 グラビア 台風クラブ 特集 台風クラブ 相米慎二監督作品 監督インタビュー 特集 台風クラブ 相米慎二監督作品 スタッフインタビュー 特集 台風クラブ 相米慎二監督作品 作品評 外国映画紹介 ヴィデオドローム 日本映画紹介 ビルマの竪琴 |

















