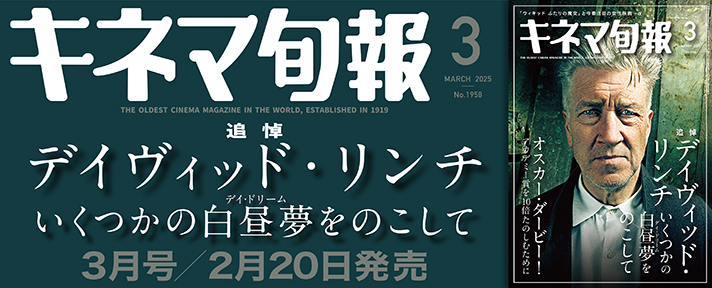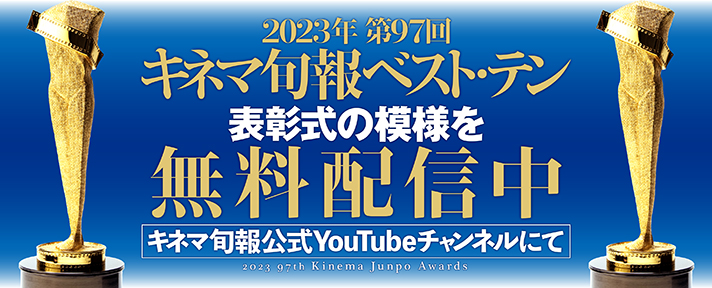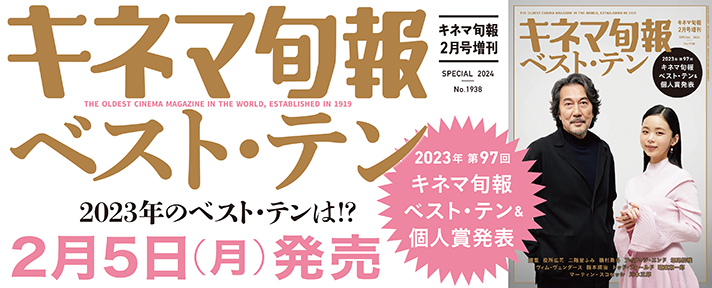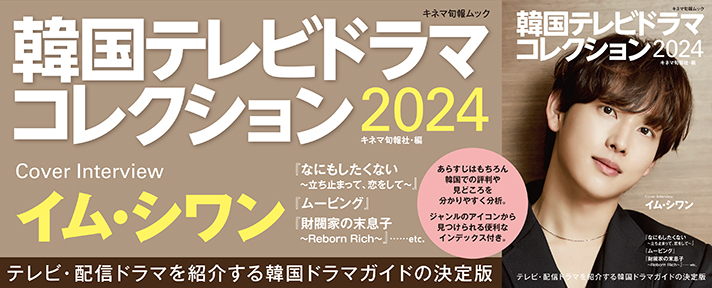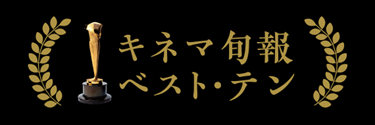映画専門家レビュー一覧
-
ペナルティループ
-
映画評論家
吉田広明
何度も死(私)刑を繰り返すVRという発想、主人公と犯人が意に反して仲良くなる展開は興味深いが、ただし犯人の動機、贖罪や死刑制度といった問題には踏み込まず、それはそれで選択、映画に「問題」など必要ないのかもしれない。ただ結局何も変わらなかったかのように見える結末はどうか。主人公に内的変化はあったはずで、それを体感するには彼と犯人の時間が、それだけで映画的時間でありうるほど充実すべきで(犯人の絵がそこで生きるのでは)、それ次第で結末も変わってきたはず。
-
-
コール・ジェーン 女性たちの秘密の電話
-
文筆業
奈々村久生
60年代アメリカを舞台とした物語だが、ノスタルジーとは無縁な16mm映像の等身大レトロルックは、時代劇とは思えない手触りで当時の復刻版かと錯覚してしまうほど。E・バンクスの馴染み方も素晴らしい。特に堕胎に臨む女性の心理、施術室の様子、手順の過程までつぶさに追った描写は秀逸で、数々の映画で感動的にフィーチャーされてきた出産シーンと同じように、今後も描かれていくべきだ。終盤の展開はやや飛躍して見えるが、荒唐無稽な寓話より圧倒的にエッセンシャルな一本。
-
アダルトビデオ監督
二村ヒトシ
彼女はホテルの宴会場で華やかな、つまらないパーティに出ていた。ホテルのすぐ外では反ヴェトナム戦争のデモ。他人の痛みは自分の痛みではない。だが、そう感じてしまった人間を運命は逃さない。堕胎しないと生きていくことができなくなって初めて、この社会の宗教と道徳は堕胎を許さないことを知る。そうなって初めて出会える人がいる。立場が異なる者たちが同じ立場で戦うとき友情が湧く。お元気そうなシガニー・ウィーバーを見て、僕は「嬉しい、また会えた」という気もちになりました。
-
映画評論家
真魚八重子
1960年代、中絶が違法だった時代のアメリカで、一般の女性たちが自分の身体の権利のために、中絶手術を行う極秘の活動を繰り広げる。主演のエリザベス・バンクスは「コカイン・ベア」の監督もすれば、中流家庭の専業主婦の役もこなす、信頼のできるクリエーターだ。この団体の中心人物がシガニー・ウィーバーなのも、圧倒的な頼り甲斐しかない。良い話過ぎるきらいはあるが、この時代に戻るかもしれない切羽詰まった現状では、初歩的な問題をわかりやすく振り返る映画も必要だろう。
-
-
流転の地球 太陽系脱出計画
-
文筆業
奈々村久生
『三体』の劉慈欣による短篇小説を映画化したシリーズ2作目だが、前作ともども原作の面影はほぼ見当たらず。序盤の怒濤のアクション描写とコメディ色が謎すぎる。SFでありながら作劇、メッセージ、映像的にも目新しさはない。それどころか地球の未来を担う各国首脳陣や意思決定のポジションには男性の姿ばかりが集結するという前時代ぶり。全体主義的な自己犠牲の精神性を讃えるような文脈にも危険を感じる。ただし、アンディ・ラウの芝居と彼のパートには一見の価値が残っている。
-
アダルトビデオ監督
二村ヒトシ
地球自体にエンジンつけて太陽系を脱出する計画の訓練生が恋愛しながら軌道エレベータで宇宙に向かってたら、人類全員が意識をコンピュータに移植して電脳空間で精神体になって生きのびるべきだという思想のテロ集団に襲撃され、スター・ウォーズ的ドッグファイトとCG多用の格闘。すでにお腹は一杯だし、そこからさらに2時間半延々と続くSFギミックと泣かせ演出の連発、そのすべてに既視感。原作は未読ですけど短篇で傑作だというから、きっとギュッと圧縮された〈詩〉になってるのだろう。
-
映画評論家
真魚八重子
原作は未読。またシリーズものと思わず1作目も未見。そのためか本作は3時間の大作であるにもかかわらず、突然始まった早回しのダイジェストを観ているようで、恥ずかしながらほとんど意味がわからなかった。全世界で協力して「妖星ゴラス」をするのだろうか。途中でアンディ・ラウが出てきてようやくホッとした。彼と幼い娘のやりとりは悲痛で狂気に浮かされたようなエモーションがあり、ようやく映画らしい瞬間を観た気がした。星はわたしが怠惰な状態で観たのを差っ引いてください。
-
-
映画おしりたんてい さらば愛しき相棒(おしり)よ
-
ライター、編集
岡本敦史
あられもないビジュアルで子どもに大人気のキャラクターだが、見た目ほど品のないギャグは少ないので親御さんは安心して家族で観に行ってほしい。むしろ節操のなさでは「劇場版 SPY×FAMILY CODE:White」のほうが遙かに上だった。密偵アクション風のストーリーはたわいもないものだが、終幕には大画面にふさわしく特大の一発を浴びせてくれる。りんたろう監督版「メトロポリス」の超巨大ビルと「スチームボーイ」のエフェクト作画が合体したようなクライマックスは一見の価値あり。
-
映画評論家
北川れい子
子どもたちに人気というこのアニメを観たのは今回が初めてだが、かなり感心した。人間や動物たちが混在するキャラクターは確かに児童向きだが、どうしてどうして大人でも楽しめる。まぁ当然だろう。テレビアニメと違って児童が劇場版を観に行く場合、大人同伴も少なくない。とあればキャラはともかく雑なドラマは許されない。そもそも“さらば愛しき相棒よ”というサブタイトルからして大人向き。お尻顔の探偵が、隠し球というか、黄色の切り札!を乱発しない節度にも感心する。
-
映画評論家
吉田伊知郎
1歳の息子とTV版を見ているため、本欄で担当するアニメとしては珍しく(失礼!)予備知識があった本作。もっとも昔の相棒との馴れ初めが発端になるため一見さんでも問題なし。中心となる元相棒との再会と、贋作絵画すり替え事件の?末も目新しさはないが飽きさせない。陰のあるキンモク先生を奥行きのある声の演技で聴かせた津田健次郎に引けを取らなかったのが、元相棒スイセン役の仲里依紗。声優としての出演作は少ないものの、その声を高く買う者としては今回の役は絶品。
-
-
戦雲 いくさふむ
-
文筆家
和泉萌香
棄民亡国、の四文字がぴったりな国だ。三上監督もおっしゃる通り、喜怒哀楽の真ん中の二文字、怒と哀ばかりが胸を占める。「こうやって、私たちを疲れさせようとしている」……。住民の方々の反対、抵抗運動のあと、淡々と画面に現れる数年後の数字。繰り返される叫びの圧殺。だが、よく簡単に「絶望」と言ってしまう私は自分を恥じた。映画に登場する方々の声、皆の祈りが、この2時間が過ぎたあとも、さらにつらなり、さらに大きな祈りにするために、広く上映されることを切望する。
-
フランス文学者
谷昌親
沖縄の厳しい状況は、それなりに理解しているつもりでいたが、「戦雲」を観ると愕然としてしまう。南西諸島に次々と自衛隊の基地が作られ、ミサイル配備が着々と進んでいるのだ。沖縄の植民地化にほかならず、同時に、日本そのものがいつのまにか臨戦態勢に置かれている……。三上智恵監督の執念を感じさせる取材の結晶だが、基地問題ばかりでなく、与那国島でのカジキ漁など、南西諸島に住む人びとの日々を描くことで、このドキュメンタリー映画に作品としての厚みももたらしている。
-
映画評論家
吉田広明
台湾有事を口実に着々と軍事基地化されていく沖縄、南西諸島の現状報告。既成事実で住民を疲弊させる自衛隊=政府、住民投票さえなかったことにして追従する地方議会。実際の有事に備え隊員用シェルターは用意するが、住民避難は保証しない。この島々の住民を守れない/守る気がないとは、つまり日本国民を守れない/守る気はないということだろう。「もしトラ」になれば米は棄日、梯子を外されて矢面に立たされた日本国の棄民は現実化する。思想なき国防が招く末路を考えさせる一作。
-
-
青春ジャック 止められるか、俺たちを2
-
ライター、編集
岡本敦史
前作とは比べものにならないくらい面白かった。そりゃあ井上監督自身の青春時代を描いてもいるのだから、記憶も鮮明で生き生きとしているし、実在の人物描写にも遠慮がない。何より半分コメディであるところが楽しく、それぞれに苦い現実と格闘する人々の悲哀を引き立たせてもいる。若松孝二監督の「微妙な時期」を伝えるドラマも興味深く、シネマスコーレ誕生記としても貴重。井浦新扮する若松監督はもはや寅さんのようで、いくらでもシリーズ化可能だ。次はぜひ90年代篇を!
-
映画評論家
北川れい子
正直に言えば、ここで描かれているあれこれの実話は、わざわざ映画にするまでもない極私的な回想録である。いったい誰が監督/脚本・井上淳一の若き日の葛藤を知りたい? 誰が名古屋のミニシアター支配人の人生を覗いてみたい? そして人騒がせな仕掛人、若松孝二監督のこととか。いくら80年代という時代がポイントだとはいえ、しょせん“映画”という井の中に足を掬われた蛙たちが飛んだり跳ねたりしているに過ぎない。と思いつつ、この作品の一途さに嫉妬を感じ、どうしたアタシ。
-
映画評論家
吉田伊知郎
若松孝二が映画館を作り、支配人と共闘するシネマスコーレ・パラダイスが観たいのであって井上淳一の自伝が観たいわけではない。終盤も蛇足でしかない。井上監督も承知だろう。だが、それでも自らを劇中に投入することでしか映画にならないと見極めたことが出色の青春映画を生んだ。若き日の自身を醒めた目で描く筆致は若松や映画との距離を描く際にも発揮される。小さな映画だが、シネマスコーレを活用し、井浦&東出、杉田&芋生が大きな存在感を見せることで豊かな広がりを見せる。
-
-
変な家
-
ライター、編集
岡本敦史
部屋の間取りという無機質な平面図から立ち上がる、不可解な禍々しさを描いた前半は本気で怖い。森田芳光作品みたいな佐藤二朗のエキセントリックな芝居もすこぶる楽しい。ただ、幽霊は出さないというシバリのせいか(それはそれで心意気や良し)、後半はデタラメな因習ホラーになり、悪ふざけに走るのが残念。ご都合主義的な「展開のための展開」が重なりすぎると、遊びに付き合う意欲もなくす。根岸季衣の大暴走もちともったいなく、もう少し丁寧に作ってもバチは当たらないと思った。
-
映画評論家
北川れい子
YouTubeで話題になった動画の映画化だそうで、試写時に渡された作品資料の中に、その動画のQRコードがあり、つい観てしまった。シンプルなだけに動画の方が想像力を掻き立てその間取りまで点検したり。が映画版はクセのある人物たちや、不可解なエピソードを盛り込み過ぎて何が何やら、途中で飽きてくる。“この家は殺人のための殺人代行の家だ”なんて台詞があるが、政治やスパイ絡みのミステリじゃあるまいし。監督は『世にも奇妙な物語』の演出家、本作もその路線に近い。
-
映画評論家
吉田伊知郎
YouTube特有の面白さが映画にできるかと訝しみながら観ると、見事に怪奇伝記ミステリへと拡張されている。間取りを自在に作り出す映画ならではの美術セットが駆使されるだけに、実は映画との相性が良かったことに気づく。石坂浩二も登場する後半はまさかの横溝正史的世界へ突入。謎解き役・佐藤二朗の四角い顔が渥美清に似ていることもあり、いっそう松竹版「八つ墓村」へ接近していく予想外の展開を愉しむ。登場と同時に川栄であることを忘却させる薄幸のヒロインも印象的。
-
-
デューン 砂の惑星PART2
-
翻訳者、映画批評
篠儀直子
第1部は作品世界の説明だけで終わった感があるが、話もスペクタクルもほんとうに面白くなるのはここから。巨大砂虫と対決する重要シーンに興奮。熱愛する「ボーダーライン」のときは気づかなかったけれど、その後持ち上がった「もしやヴィルヌーヴはアクションが撮れないのでは」という不安が、今回少しだけ払拭されたかも。もちろんプロダクションデザインは今回も必見。「予言」に翻弄され、苦悩する主人公をティモシー・シャラメが熱演するほか、これでもかという豪華キャストにもびっくり。
-