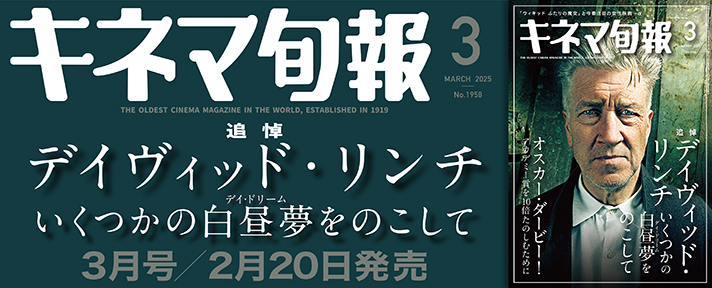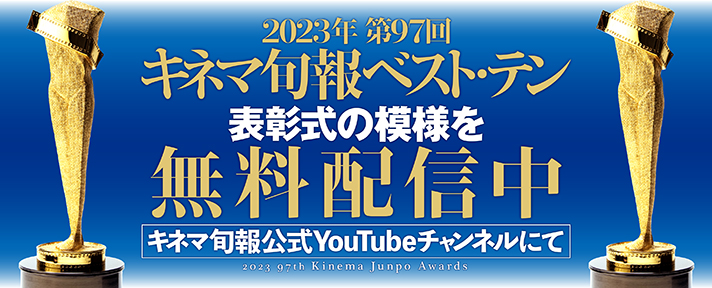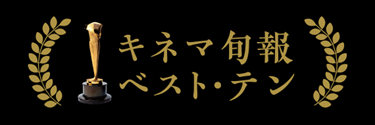映画専門家レビュー一覧
-
コヴェナント 約束の救出
-
編集者、映画批評家
高崎俊夫
「捜索者」を嚆矢とする数多の〈seek & sight〉のドラマにはどれも抗しがたい神話的な魅力がある。アフガニスタンを舞台にタリバンの武器倉庫を破壊する特命を帯びた米軍兵士とアフガン人通訳の抜き差しならぬ友情と自己犠牲の美徳を謳いあげた本作もその系譜にある。荒唐無稽スレスレの大胆で巧みに構築された手に汗握る奪還劇はカタルシスを与えるに十分だが、ラスト、米軍の撤退後、タリバンが実権を握ったアフガニスタンで起こった光景に思いを馳せると暗澹とならざる得ない。
-
映画批評・編集
渡部幻
ガイ・リッチーが新境地の開拓に挑んだ佳作。“Guy Ritchie's The Covenant”の原題からその意気込みは伝わる。2018年のアフガニスタン。米国への移住ビザを約束された地元通訳と、彼に命を救われた米軍曹長。国家と政治を排除しきれない題材ではあるが、リッチーが語りたいのは立場を越えて個になる男同士の恩義の物語。もっとも、リッチーには新機軸でも、観客にもそうとは限らないが……。ジェイク・ギレンホールはやはり上手だが、寡黙な通訳のダール・サリムも印象に残る。
-
-
落下の解剖学
-
映画監督
清原惟
人間同士の関係性はとても複雑だということに、真正面から向き合った作品。裁判ものなので、最終的な勝ち負けは存在している。だけれども、人生において何が正しく間違っているかということは、本当の意味では判断できないということを思う。主人公である小説家の女性も、目の不自由なその息子も、弁護士も、みな忘れがたい顔をしている。素晴らしい演技を刻みつけられる場面があった。2時間半という時間が短く感じるほど、彼女たちの過ごしてきた人生の時間を想像させられる。
-
編集者、映画批評家
高崎俊夫
かつてのシャーロット・ランプリングを思わせるザンドラ・ヒュラーの沈着な、しかし微妙に千変万化する表情に魅せられる。傲慢さ、悲嘆、諦念、幻滅、その内面で生起している感情を容易には看取させない貌と身振りを見つめているだけで飽くことがない。現場に唯一、居合わせた視覚障がいの息子の怯えと繊細さを際立たせる音響設計、緩慢に〈夫婦の崩壊〉の内実を浮かび上がらせる作劇も見事だ。ショパンのプレリュードがこれほど哀切かつメランコリックに響く映画も稀有ではないだろうか。
-
映画批評・編集
渡部幻
フランスで夫殺害の罪に問われたドイツ人の妻を巡る法廷劇。フラッシュバックではなく、言葉で語られる事件の“解剖”に重点が置かれる。しかも舞台劇的ではなく映画的なのだ。夫妻はドイツ人とフランス人で、共通言語は英語。言語の目隠しが感情の目隠しとなって、関係の力学に軋みが生じる。夫婦喧嘩の感情的な暴発は「イン・ザ・ベッドルーム」「マリッジ・ストーリー」以来のリアリティ。ドイツ女優ザンドラ・ヒュラーが圧巻で、スワン・アルローら男優陣も卓越している。隅々まで緩みない映画表現。
-
-
ボーはおそれている
-
文筆業
奈々村久生
「ヘレディタリー/継承」から連綿と受け継がれる母性神話と生殖への徹底した懐疑。それこそがアリ・アスターの哲学であり、本作はその結実の一つを提示する。主人公ボーが直面するカオスは、映像から得られる情報以外には一切の説明を欠いており、これがドッキリだとすれば観る者はネタバラシをされないまま不安と焦燥を延々抱え続けることになる。だが理性を凌駕する圧倒的なイメージの力によって、家族というものの本質に逆説からたどり着いた結末が悲劇であるとは思わない。
-
アダルトビデオ監督
二村ヒトシ
星10個。いまどき、こんな精神分析的な喜劇映画を作っていいのか。いいのです。母を愛しすぎてたり、親からひどい目にあって今でも親を憎んでいたり、親のせいで人を愛することも適切な距離をとることもできなくなって人生が滞ってる、すべての人のための映画だから。「へレディタリー/継承」の答え合わせでもあり、「へレディタリー」より怖い。往年の筒井康隆ファンも必見。ラース・フォン・トリアーのファンも必見。日本のSNS上の冗談概念〈全裸中年男性〉をホアキンが演じてるのにも感動。
-
映画評論家
真魚八重子
非常に難物だが、基本の型は「ヘレディタリー/継承」と同じで、家族が下の代に災難をもたらす物語である。アスターは本作をブラックジョークと言い、確かにそうではあるものの、母親が息子を心身ともに破壊する話を笑うのは難しい。世界は暴力に溢れ荒涼としており、劇団の映画内演劇にしか落ち着ける場所はない。確かに我々も内心、この世界を生きづらいと思っていても、アスターの家族観の極端さは死に至るので、さすがに戸惑いを覚える。ただ家族が災厄というのは、恐ろしいが真実ではある。
-
-
身代わり忠臣蔵
-
ライター、編集
岡本敦史
ムロツヨシの芝居を楽しみたい人には満足度の高い内容だろう。最大の見どころは柄本明との共演シーン。かつて劇団東京乾電池の研究生時代に柄本の厳しい指導を受けたというムロが、今度は主演俳優として対峙する場面には愉しい緊張と興奮が走る。映画自体は「忠臣蔵」の大胆な脚色に見えて、武士道は特に否定しない保守系コメディ。仇討後の赤穂浪士たちの末路も含めて本来ひどい話だと思うので、もっと主人公の生臭坊主の視点から「美談」を派手にひっくり返してほしかった。
-
映画評論家
北川れい子
忠臣蔵も世につれ、作者につれ。今回は敵役・吉良上野介の実弟である生臭坊主が、金に釣られて床に伏した吉良の影武者になってのドタバタ忠臣蔵で、影武者役のムロツヨシも、大石内蔵助の永山瑛太も、重厚、風格とは一切無縁のカジュアル演技。二人が以前、出会っているというのが、いざ討ち入りのネックに。とはいえ幕府の非情さや家臣の動きなどは最低限描いていて、忠臣蔵に馴染みのない若い世代の入門書にもなるかも。四十七士の数もしっかり抜かりなく、オチも悪くない。
-
映画評論家
吉田伊知郎
近年に限らず、90年代に市川崑と深作欣二が競作した頃から忠臣蔵映画は外伝傾向が強くなっていったが、本作は最も跳ねた内容かつ、笑える。忠臣蔵に「影武者」を混在させるアイデアが良く、偽物の吉良が大石と討ち入りを共謀したりするが、史実との駆け引きもうまい。ムロツヨシが往年の日本の喜劇人的存在感を増し、出てくるだけで面白くなる。終盤は北野武の「首」を観た後では物足りなくなり、吉良と大石の衆道まで描けたのではないかと思えてくる。東映京都の美術が際立つ。
-
-
風よ あらしよ 劇場版
-
文筆家
和泉萌香
男女格差、セックス、愛、家庭、自由恋愛の果て、論じ描いた社会生活の姿、そして国家の犬に殺されるまで、伊藤野枝の短くもすさまじい人生はテーマひとつ、ある期間ひとつを切り取り描いてもむせ返りそうな濃密な映画になると思うが、「風よ、あらしよ」の言葉には追いつかない、単調な人物紹介ドラマの枠にとどまってしまっている。神近市子の刺傷事件も、ホラーめいた演出なのが残念だ。だが、彼女の叫びと言葉に一片でも触れる機会、多くの人に見てもらいたいと思う。
-
フランス文学者
谷昌親
伊藤野枝の人生がいかに苛烈なものであったかは伝わってくるし、胸を打たれもする。それは、物語が持つ力の証でもあるだろう。しかし、映画として見た場合、俳優たちの熱演にもかかわらず、どうしてもダイジェスト版のように感じられてしまう。テレビで3回にわたって放映したドラマの劇場版になるわけだが、劇場用に再編集するのであれば、もっと思い切った編集の仕方もあったのではないか。そうすれば、この作品に欠けている、映画そのもののダイナミズムが出てきたかもしれない。
-
映画評論家
吉田広明
大杉栄は十代の頃に著作も読み、その思想は現在においても自分の根底を支えているが、伊藤野枝は吉田喜重の映画を通じてその重要性は知りながら親しい存在とは言えず、ゆえに彼女がその無垢、純真なセンチメンタリズムによって却って大杉のうちに潜む無意識な男性性を撃ち、彼を鼓舞したその重要性は不覚にしてほぼ初めて知った。とは言えそれ以上の映画的感興があったかと言えば疑問で、元がNHKのドラマだと言われればなるほどそうだなと言うしかなかったことは確かだ。
-
-
夜明けのすべて
-
文筆家
和泉萌香
PMSの言葉を知ってどこかほっとした人、薬で改善した人もいれば一向に良くならない人もいて。それでも向き合っていかなければならないと思い悩む女性はたくさんいるし、私もそのひとり。自分の症状により現職を辞めざるを得なかったある2人が勤めることになった同じ職場。彼らが紡ぎ出すシンプルで小さな答えは、これから最も尊ぶべきことの一つだろう。その答えの実践者である、脇を固める人々の温かさもわざとらしさがなく、都会の灯りと手作りの星空に重なる。
-
フランス文学者
谷昌親
PMS(月経症候群)に苦しむ女とパニック障害を抱えるようになった男の物語、などと書くと、障害者への偏見をなくすように促す作品だとか、社会のなかに居場所のない男女の恋愛模様を想像してしまうかもしれない。しかし、2人は職場の同僚にすぎず、むしろ違う方向を見ている。それでも互いの障害を理解し、助け合うようになる過程が、淡々と静かに描かれる映画なのである。原作はあるが、映画で付け加えられた要素によって、「夜」がより印象的なものになっている点も魅力的だ。
-
映画評論家
吉田広明
弱者同士の連帯という主題の作品が多くなってきているのは、それだけ社会が疲弊しているということなのか、我々の視点が細密化して、これまで見ようとされなかった差異が可視化されてきたということなのか、ともあれ本作もその流れの中にあって、しかしこの種の主題にありがちな殊更な劇化の道を取ることなく、静かに日常を生き延びてゆく同志たちの姿をほのかなユーモアを交えながら淡々と捉えており、映画の姿が上品である。過去から届く光と声が現在を息づかせる辺りにも感動する。
-
-
瞳をとじて(2023)
-
映画監督
清原惟
31年ぶりのビクトル・エリセの新作は、映画をとりまく状況の変化と、映画というメディアについて描く映画だった。はじめは、どこに向かっていくのか全くわからない、長い旅に出ているような感覚だったのが、最後で急に腑に落ち、深く感動した。「ミツバチのささやき」の小さなアナ・トレントが、大人の女性になっている。それでも、すぐに彼女だとわかった。人物たちの顔がすべてを物語っている。この映画をフィルムではなくデジタルで撮影したことに、監督がもつ未来への希望を感じた。
-
編集者、映画批評家
高崎俊夫
かつてビクトル・エリセは「ミツバチのささやき」のドキュメントの中で6歳のアナ・トレントが怪奇映画を見ながら思わず声を上げたときの表情、まなざしをとらえ「私が映画を発見した最高の瞬間だった」と語った。「瞳をとじて」に半世紀ぶりにアナに出演を乞うたのは、エリセがそんな奇蹟にも似たエピファニーの瞬間を再び見出したかったからにほかなるまい。50代後半のアナは目尻の小皺さえ美しい。父と再会した際「ソイ・アナ(私はアナよ)」と呟くアナ・トレントを観ていて私は崩壊した。
-
映画批評・編集
渡部幻
エリセの老境を偲ばせる私的な瞑想。映画表現は常に時間と場所に帰属するが、今ここにある我々の現在もまた個々の記憶=過去の集合体にほかならないからこそ、人はスクリーンの幻に現実の似姿を見出すことができるのだろう。その意味でこの映画が比喩するのは人生の旅、それも終点にほど近い者が見た夢としての映画であり、一種ミステリ的な興味とともに上映時間は過ぎていく。その様は美しく悲しい。しかし“My Rifle, My Pony and Me”の歌詞がこんなに沁みるとは思わなかった。
-