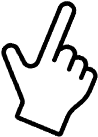 解説
解説
明治末期の大阪の寄席で活躍した桂馬喬を主人公に、上方芸人の芸に対する執念と壮絶な生涯を描く。原作は藤本義一の同名小説。脚本は藤本義一と杉浦久、監督は脚本も執筆している「富士山頂(1970)」の村野鐵太郎、撮影は「夜にほほよせ」の吉岡康弘がそれぞれ担当。
ユーザーレビュー
「鬼の詩」のストーリー
ほんの一刻、明治の末に、大阪の寄席で桂馬喬は居並ぶ大家の落語より人気を集めた。桂馬喬は桂馬狂ではないかといわれた。まさにその芸は狂であった。しかし、もともと狂っていたわけではない。孤児の馬喬は養父の遺志を継いで芸人となった。最初の彼は古典一途の生真面目な落語を披露していたが、お茶子の露との結婚を境に、積極的な性格に変った。それまでの馬喬は手踊りと芝居咄しを得意とする人気落語家・桂露久の芸を邪道として軽蔑していたのだが、今の彼は、露久の芸を盗み、己れの芸にすべく、一挙一動を真似るのだった。そんなある日、突然、露が流産で死んだ。その日から馬喬の姿が消え、一カ月後、まるで幽鬼のような姿で現われた。以後、馬喬は、幽鬼のような姿で、盲目の乞食巫女を演じ、客席は涌いた。しかし不幸なことに馬喬は天然痘にかかってしまった。病は癒えたが、その顔は無残なあばた顔に変形した。だが、馬喬の芸への執念は、自らの顔を利用した鬼の咄しを考え出して、高座に復帰した。客は馬喬を鬼に見たてて、自分たちが高座の鬼をいじめている錯覚におちいるのだった。他の誰もが真似できない芸を馬喬は己れのものとした。客の馬喬に対する加虐趣味はエスカレートし、ついに馬喬は自分の歪み窪んだあばた顔に煙管を吊した。今日は一本、明日は二本と、客は何本の煙管を吊るすかという期待で集って来た。煙管の林の中に鬼の泣き笑いの顔があった。一本でも多く吊るそうと、馬喬は顔の窪みを深くするために、食を絶った。馬喬が自らの顔に十数本の煙管を吊して、露の位牌の前で死んでいたのは、それから間もなくの事だった。享年、35歳でだった。
「鬼の詩」のスタッフ・キャスト
| スタッフ |
|---|
| キャスト | 役名 | |
|---|---|---|

「鬼の詩」のスペック
| 基本情報 | |
|---|---|
| ジャンル | ドラマ |
| 製作国 | 日本 |
| 製作年 | 1975 |
| 公開年月日 | 1975年8月16日 |
| 上映時間 | 93分 |
| 製作会社 | 鐵プロダクション=ATG |
| 配給 | ATG |
| レイティング | 一般映画 |
| アスペクト比 | アメリカンビスタ(1:1.85) |
| カラー/サイズ | カラー/ビスタ |
関連するキネマ旬報の記事
| 関連記事一覧 | |
|---|---|
| 1975年5月上旬号 | グラビア 「鬼の詩」 |
| 1975年8月上旬号 |
グラビア 村野鐡太郎監督 「鬼の詩」 特集 「鬼の詩」 1 「鬼の詩」に見る芸道もの映画の上昇志向 特集 「鬼の詩」 2 村野監督の顔と手が全ショットに見える 特集 「鬼の詩」 シナリオ |
| 1975年8月下旬号 | キネ旬試写室 鬼の詩 |
| 1975年9月下旬号 | 日本映画紹介 鬼の詩 |

















