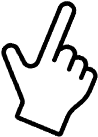 解説
解説
連合艦隊旗艦「三笠」の乗員であった海軍軍楽隊の若者たちの激しく燃えあがる愛と生と死を描く。脚本は「大日本帝国」の笠原和夫、監督も同作の舛田利雄、撮影も同作の飯村雅彦がそれぞれ担当。
映画館で観る
配信で観る
TVで観る
ユーザーレビュー
「日本海大海戦 海ゆかば」のストーリー
明治三十八年。日露戦争は勃発以来二年目を迎え、大国ロシアと近代国家を目指す日本との大海戦が、いまその火蓋を切ろうとしていた。この決戦を迎えるに当って、東郷平八郎はじめ司令部が頭を悩ましたのはウラジオストックに入港するバルチック艦隊が、どの航路をとるかであった。一つに対馬水道を通って日本海を最短で入港するコース、いま一つは大平洋側を通って津軽海峡または宗谷海峡を横断するコースである。連合艦隊を三分したのでは勝ち目はなく、今、決断が迫られていた。その頃、連合艦隊旗艦三笠の軍楽隊に、神田源太郎が配属されてきた。軍楽隊は軍艦の入出港、閲兵式等に演奏を主にする楽隊であり、直接戦闘員でないことから軍隊での立場は低いものである。その源太郎のもとに恋人せつが面会にやって来た。せつは娼婦であった。しかし、天皇陛下の赤子として死を覚悟した源太郎は、せつを無情に突き放すと、急いで隊に戻ってしまった。三笠は呉を出て途中佐世保港に立ち寄り、最後の陸地補給を急いだ。そこに再びせつが現われ、手の中に古物のトランペットを握っているのを見て、源太郎は強い衝動を感じ「きっと帰ってくる」と約束するのだった。洋上に出てからの訓練は、一層の激しさを増し、軍楽隊員は楽器を仕舞い、一水兵として訓練に汗を流す。三笠の連合艦隊司令部では、東郷長官、秋山真之中佐等が、いまだにバルチック艦隊の進路を決めかねていた。激しい訓練の中で、疲労が深まるにつれて源太郎の内奥に秘めた音楽への情熱が燃えたぎり、東郷長官の甲板巡視の際、長官への演奏許可の直訴を行った。その場は立ち去った東郷長官は、やがて演奏の許可を与える。軍楽隊員は目を輝かせ、ドヴォルザークの「新世界」を演奏した。乗組員それぞれの胸に去来するものは、故郷の山河であり、国に残した妻や子の面影であった。東郷はこの海戦が、世界に勝利を喧伝し、外交戦をも有利に進める重要な戦いであると認識していた。将は将を知る。東郷はバルチック艦隊も正面攻撃でくると確信した。東郷は決断し、激戦の末日本軍は勝利をおさめた。
「日本海大海戦 海ゆかば」のスタッフ・キャスト
| スタッフ |
|---|
| キャスト | 役名 | |
|---|---|---|

「日本海大海戦 海ゆかば」のスペック
関連するキネマ旬報の記事
| 関連記事一覧 | |
|---|---|
| 1983年5月下旬号 | グラビア 日本海大海戦・海ゆかば |
| 1983年6月上旬号 | 特集 日本海大海戦・海ゆかば 舛田利雄監督作品 舛田利雄監督 インタビュー |
| 1983年6月下旬号 | 日本映画批評 日本海大海戦・海ゆかば |
| 1983年7月上旬号 | 日本映画紹介 日本海大海戦・海ゆかば |

















