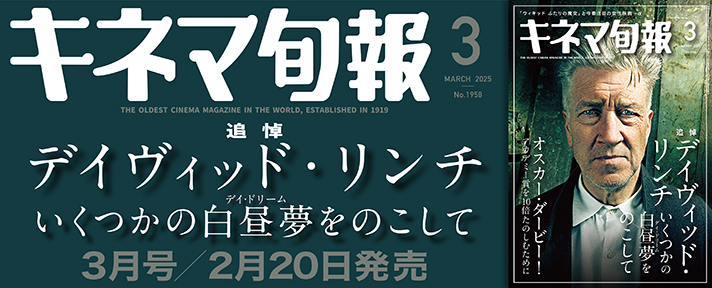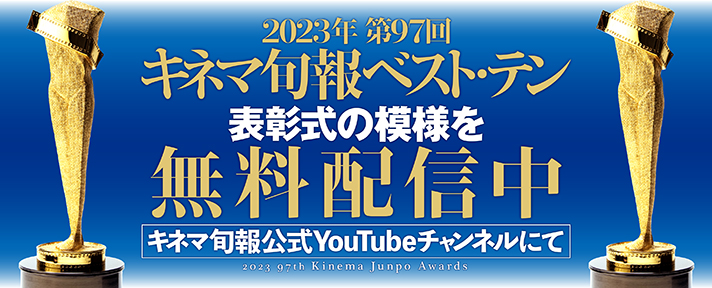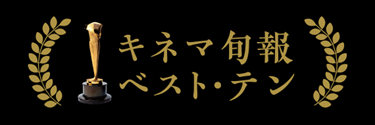ヴォイス・オブ・ラブの映画専門家レビュー一覧
ヴォイス・オブ・ラブ
世界の歌姫セリーヌ・ディオンの半生をモデルにした音楽映画。1960年代カナダ。ケベック州の田舎で、音楽一家に生まれたアリーヌは、幼い頃から歌の才能を発揮。12歳で音楽プロデューサー、ギィ=クロードと出会い、レコードデビューを果たすが……。監督・主演を務めたのは、「プチ・ニコラ 最強の夏休み」のヴァレリー・ルメルシェ。
-
映画評論家
上島春彦
伝記映画だがキャラクターの名前は一部変更されている。「リスペクト」にも歌われたスタンダード〈ネイチャー・ボーイ〉が、こちらでも前半のテーマ曲っぽくたっぷりフィーチャー。どうやらネイチャーという観念は良くも悪くも現在の世界を象徴する鍵語なのだろう。不思議なことにオスカー・セレモニーにおける歌唱場面はあるのに、映画「タイタニック」という言葉も文字も一切出てこない。ヴィクトリア・シオのヴォーカルとヴァレリー・ルメルシエのパフォーマンスが圧巻だ。
-
映画執筆家
児玉美月
誰もが知っている「タイタニック」の主題歌〈マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン〉のメロディが流れるや、セリーヌ・ディオンをモデルにした主人公が観客の高揚を遮断するかのように「好きじゃない」と紙に殴り書きするあたりのユーモアとチャーミングさが、コメディアンであるヴァレリー・ルメルシエの作家性を垣間見せる。そんな同楽曲をふんだんに使うなど、扇情的なドラマに仕立て上げる選択もあったはずだが、終奏に響くフレーズ「ただの普通の女」からあくまで外れない。
-
映画監督
宮崎大祐
老人の顔をした小学生の怪奇寸劇からまったくついていけず、芸能人のモノマネ大会を無言で家族と見ているときのような、今死んだら本当に後悔するだろうなという沈鬱な時間だけがつづき、終わった。あとから聞いた話では、なんと還暦近い年齢の監督が全世代のセリーヌ・ディオン役をこなしていて、幼少期もCGを用い演じていたという。対象への愛情や少しでも面白い映画を作ろうという意思ではなく、少しでも目立ちたいという下卑た自意識だけが走る映画が面白いわけなかろう。
1 -
3件表示/全3件