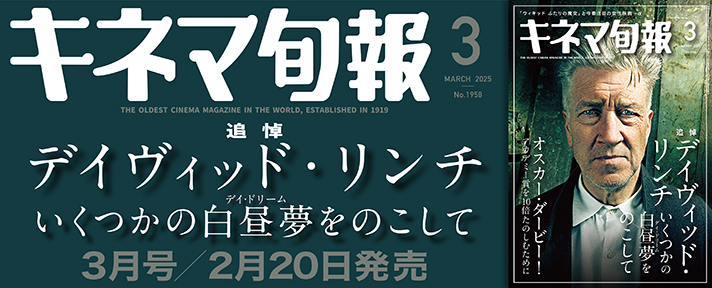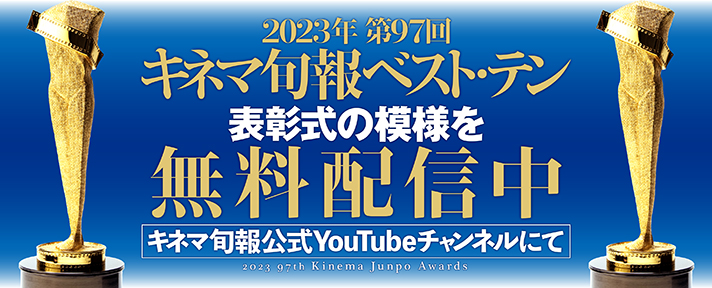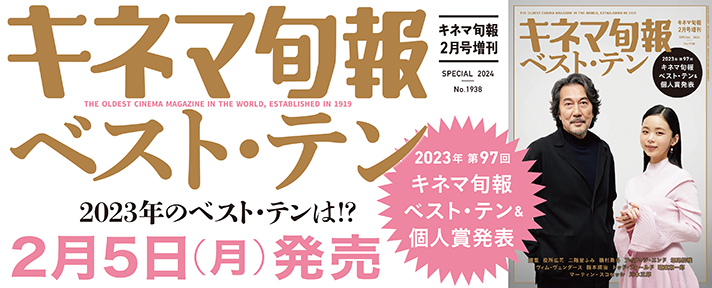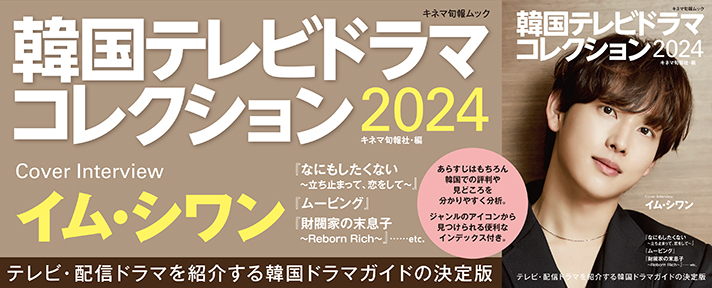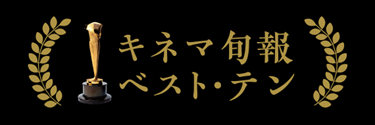映画専門家レビュー一覧
-
THE MOON
-
翻訳者、映画批評
篠儀直子
映画内の人々が国の威信をかけて技術力の高さを証明しようとするのと同様、この作品自体もまた、韓国映画の技術力がいよいよ世界トップレベルにあることを証明する。複数の先行米国映画の影が序盤こそちらちらするが、手に汗握る展開を観るうち気にならなくなるはず。一方、もはやこれまでという局面を打開するのが、過去の因縁とディープな情念というのは韓国映画らしいところ。いつものように愛すべき小物感を爆発させるチョ・ハンチョルからいつも素晴らしいソル・ギョングまで、キャストも充実。
-
編集者/東北芸術工科大学教授
菅付雅信
韓国初の月面有人探査というミッションを担い3人の宇宙飛行士が月へ旅立つが、太陽風の影響で2名の命が失われる。果たして残された1名は月面探査を行い、地球に帰還できるのか。韓国映画として最大級の超大作SFだが、構成は「ゼロ・グラビティ」×「オデッセイ」のまんま。そこに過剰なまでの愛国主義的な情感を盛り込み、かなりウエットな仕上がり。この制作費と技術力には素直に負けを認めるが、いかなる国の愛国主義映画も好まない私としては残念なプロパガンダ映画に思える。
-
-
フェラーリ
-
文筆業
奈々村久生
P・クルスの妻が息子の死という夫婦最大の試練から目をそらせないのに対して、愛人との二重生活に苦悩の証しを求めるエンツォは、A・ドライヴァーがまとう煮え切らない空気と相まって絶妙に愛され難い人物像となっている。特筆すべきは終盤の事故シーン。スピード、カット割り、犠牲者をとらえる描写の切れ味は戦争映画の爆撃シーンにも匹敵し、皮肉なことに、カーレースの熱狂とスリルと迫力を最も実感したのはここだった。その容赦ない凄惨ぶりにマイケル・マンの本気を見た気がする。
-
アダルトビデオ監督
二村ヒトシ
アダムくん老け役でも顔つきも物腰もやっぱり変でいい。家父長制を煮詰めたような哀れな成功者。速度が経済になり、競うことに愛や死を賭けるなんて地獄だよ。自動車の映画だと思って観に来た人が期待するのだろう男のロマンという糞みたいなものがほぼ描かれない(クライマックスで少し描かれたと思ったら、すぐ最悪の悲劇が起きる)のがいい。ペネロペさんのサレ妻もいい。お金持ちの妻や愛人やってる女性、それと「がんばれ。命がけでやれ」と人に指図するのが仕事の人はみんな観てね。
-
映画評論家
真魚八重子
アダム・ドライヴァーは魅力的な俳優だし、役に入ると雰囲気も変わる傑出した存在だけれども、「ハウス・オブ・グッチ」から「フェラーリ」と、名門の実在の人物を立て続けに演じるのはどうなのか。他の才能ある俳優たちの、世に出る機会を奪っているのではないか? 車へのフェティシズムよりビジネスを優先しており、世知辛い話題が続くのも面白いとは言いづらい。事故のシーンは丁寧で非常にリアリティを持っていたが、基本的には車のフェラーリではなく会社としてのフェラーリの話だ。
-
-
Shirley シャーリイ
-
映画監督
清原惟
凡庸の中に閉じ込められている若い女性と、天才的小説家の年上の女性が惹かれ合う物語。惹かれ合う二人の関係性もキャラクターも独特で、ステレオタイプではない。現代よりも女は男に支配されており自由ではなかったという視点も、単なる主張に留まらず、とても巧妙に物語に組み込まれていた。それでいうと夫が結局暗躍者で、創作さえうまく行けばいいとも捉えられるラストは少し腑に落ちないかもしれない。不穏なときに軽快な音楽が鳴る演出も、事態の混乱を表しているようで冴えていた。
-
編集者、映画批評家
高崎俊夫
〈イヤミス〉のベストテン上位に必ず選ばれる傑作短篇『くじ』の作家シャーリイ・ジャクスンの知られざる私生活に迫った異色作。最大の理解者たる大学教授の夫との捻れた共依存関係、そこに教職に就こうと目論む若い野心家夫婦が絡む。かくして肥大したエゴとモラルを欠落させた4人の間でアブノーマルな心理劇が展開される。シャーリイは多重人格がテーマの『鳥の巣』という傑作ミステリも書いているが、エリザベス・モスは深い狂気の淵にたたずむヒロインを絶妙に演じている。
-
映画批評・編集
渡部幻
伝説の小説家シャーリイ・ジャクスン夫妻と架空の若い夫妻をめぐる結婚と創作の物語。通常の伝記映画とは異なる。事情と空想を溶かした映像美が蠱惑的で、指先で触れれば絵の具が付きそうだ。劇中のシャーリイは、代表作『くじ』の後で、実際の少女失踪事件に刺激された『絞首人』を執筆しようとしている。それらは実在の小説だが、ジョセフィン・デッカー監督は、かつてワイズが映画化した「たたり」同様、女性心理に力点を置き、仮にシャーリイ(エリザベス・モスはそっくり)に詳しくなくとも引き込む力があると思う。
-
-
言えない秘密(2024)
-
文筆家
和泉萌香
映画は時を超えるボーイ・ミーツ・ガール。「歩く二宮金次郎像」をはじめ昔から学校には不思議話が多々あるが、この現代にあって学校はそんな不思議や秘密ごとを忍ばすことができる最後の砦であり、ただ恋の舞台となりえる最後の場所のようにも思えてくる。彼らの<旅>が直線の時間軸からきっちりと足を踏み外しはしないのと、涙、涙のクライマックスは残念だが、ラストカットはロマンティックで、潔い。ピアノの猛練習を重ねたという主演の京本と古川もきらめくように魅力満点だ。
-
フランス文学者
谷昌親
ファンタジー色の強い台湾の恋愛映画のリメイクだが、いくらファンタジーと言っても、この物語の設定を受け入れさせるにはそれ相応の表現力が必要なはずで、たしかに、謎の少女が初めて画面に登場する際に鏡に映った身体の一部のイメージを示すなど、それなりの工夫は見られるものの、作品全体としては残念ながら説得力を持つまでに至っていない。劇中で重要な役割を演じるピアノ曲も、映画音楽風のものでなく、オリジナル版のようなクラシカルな曲のほうがよかったのではないか。
-
映画評論家
吉田広明
ピアノが嫌いになっていた音大生が、妖精的な存在により音楽への愛を取り戻す。定型的な物語であるが、定型は内容の理解が早い利点もある一方、個々の作品を呑み込んでしまう怖いものでもある。個性は伝統のもとに発揮され、伝統は個性によって賦活する。何も新しい作品が新奇でなければならないこともないが、定型への意識(それが批評意識であり、個性)は必要に違いない。それが無ければ単なる「使用価値」(この場合「泣ける」等)しか残らないが、そんなものは早晩摩耗するだろう。
-
-
WALK UP
-
俳優
小川あん
今までありそうでなかった、ワンシチュエーション縦4層構成。娘を含めた女性4人に対してのそれぞれの時間軸を経て、主人公の男性を多方面から覗き見る。会話劇として肝心なはずの会話は、中身があるようでないよう。傍観するしかない観客は、どこに当の本人の姿があるのか見失う。そうしてるうちに、ひとり煙草を吸うビョンスの無の時間で幕は降りる。結果、悩める男を悲哀の者にしてしまうのだ。こういったある意味の悪事を見事なセンスでホン・サンス先生はこっそりカバーする。
-
翻訳者、映画批評
篠儀直子
作中に出てくる台詞を聞いて、なるほどホン・サンスの映画は酒を飲みながらだらだら観るのにちょうどいいのだ(そして酔いが回ってわからなくなったらその地点からまた繰り返し観ればいいのだ)と膝を打ち、今回は変なズームとかないんだな、ある意味正攻法の撮り方だなと思っていたら、最後の最後にこんな仕掛けがあるのだから油断がならない。原題は「塔」という意味だが、階を上がるたび変わるビョンスの姿は、まさに「どれもビョンス」なのだろう。クォン・ヘヒョが美声の持ち主だと今回気づく。
-
編集者/東北芸術工科大学教授
菅付雅信
韓国のインディー映画作家を代表するホン・サンス監督の最新作は、まるで彼のアバターのような映画監督が主人公となり4階建てアパートメントを舞台に、各章ごとに一階ずつ上の階に上がっていく4章構成の繊細なコメディ。悩み多き中年映画監督だが女にはモテるところはウディ・アレン的。モノクロの画像が美しく、ウィットに富んだ会話が楽しく、時間経過が曖昧なままエピソードがつながり、最後が円環構造になる構成の斬新さに感服。「映画作家」への批評的視点も持った、見事な映画作家映画。
-
-
スリープ
-
文筆業
奈々村久生
睡眠中の夫の奇行が心身機能の異変か超常現象かの境を行き交うストーリーテリング。「ローズマリーの赤ちゃん」(68)に連なる系譜で、本作の核心は、最も身近で信頼すべき相手を信じられなくなる恐怖だ。愛する人が得体の知れない存在になっていく。その葛藤と戦う妻をチョン・ユミが好演。夫役のイ・ソンギュンも昨年韓国での公開時に観たときはまだ存命だった。惜しむらくは映像が暗いこと。光量を落とせば暗さが写るわけではなく、闇は光との対比であり、影の濃さで体感したかった。
-
アダルトビデオ監督
二村ヒトシ
不眠で生活に支障をきたしたり悪夢に殺人鬼が現れるのではなく、よく寝てるのに動きだして昼間はしない異常行動をしちゃう。夢遊病者は内面の無意識で抑圧(幸せな夫婦が抑圧が強いのは現実によくある)から解放されてるのか、外部の超自然の悪意に呪われているのか、ホラー映画の文脈では峻別困難だという脱構築ホラー。章立てで視点が変わるのは「来る」と同じだが、あそこまで無惨ではない。睡眠中に自分で顔を掻きむしるのが事件の発端で、アトピー持ちの僕としては複雑な気持ちに。
-
映画評論家
真魚八重子
イ・ソンギュンは韓国の俳優の中でも三本指に入るほど好きだったので、亡くなった今その姿を観るのは悲しい。映画の構成は章立ての通り、妻の出産を境に狂気に憑かれているのが夫から妻に移行して見える。無防備な赤ん坊を前にして、母性が女性の正気を奪うのは正しいかもしれない。後半のチョン・ユミの演技は恐ろしく、何をしでかすかわからない演出と芝居は秀でている。ラストは芝居なのか、本当に霊が抜けたのか、観客に判断を委ねるタイプで、珍しく面白い宙吊り感があった。
-
-
ふたごのユーとミー 忘れられない夏
-
映画監督
清原惟
まず、ひとりの俳優によって双子の少女が演じられていることにとても驚いた。そしてそのことに常に意識を奪われながら見てしまったようにも感じる。双子の恋とお互いへの想いの間での葛藤を描く物語なのだが、全体的にかなりクリーンな映像で、少年少女も絵空事のように美しいので、あまり内容に親身になれない感じがあった。それでも、同じ俳優が双子を演じていても、映画が進むうちに全く別の人に見えてくるのは、演技というものの不思議さに改めて思いめぐらせるきっかけになった。
-
編集者、映画批評家
高崎俊夫
双子というテーマは「らせん階段」から「シャイニング」まで恐怖映画と相性が良いが、思春期の恋愛ものはどうか。近年、タイ映画は前衛的なアートフィルムから時代の先端を行くエンタテインメントまで懐の深さを垣間見せているが、監督が一卵性双生児姉妹である本作のような等身大の視点を感じさせる作品に出会うと妙にホッとする。親密なスロームービーの趣向とは裏腹に貧困で離散を強いられる過酷な家族の肖像は苦い現実のリアルさを突きつける。
-
映画批評・編集
渡部幻
田舎で夏休みを過ごした女の子2人と男の子1人の恋模様。飽き飽きの設定だが、少し変わっているのは舞台が1999年のタイで、主人公が双子の少女の点。長篇デビューとなる監督も双子の女性であり、新人女優が一人二役で双子を演じている。何をするにもシェアしてきた双子も中学生となり、ある出来事をきっかけに心優しい少年をシェアすることになってしまう。恋は大人への一歩で、やがてはそれぞれの恋をして、人生を歩まねばならない。わざとらしいほど天真爛漫として純情な3人のセンチメンタルな成長物語。
-