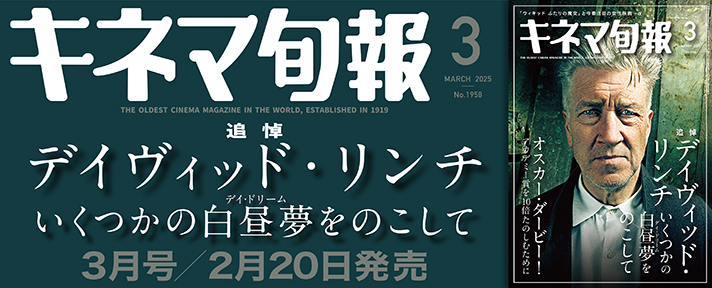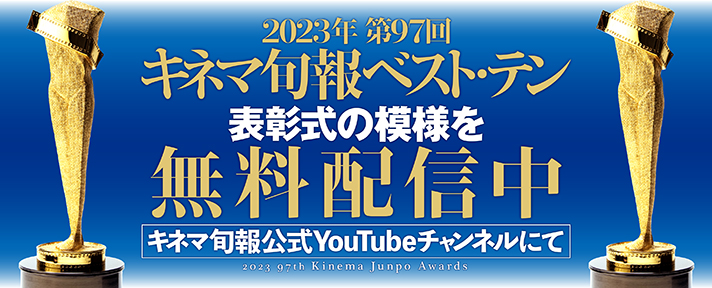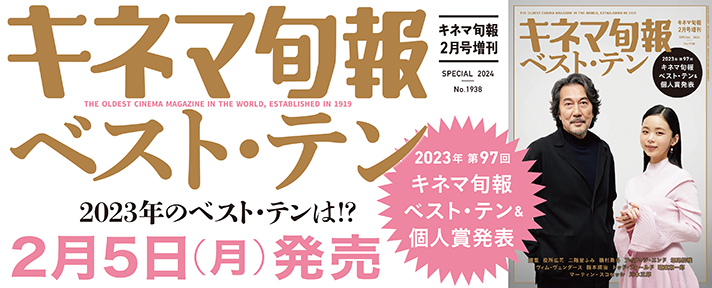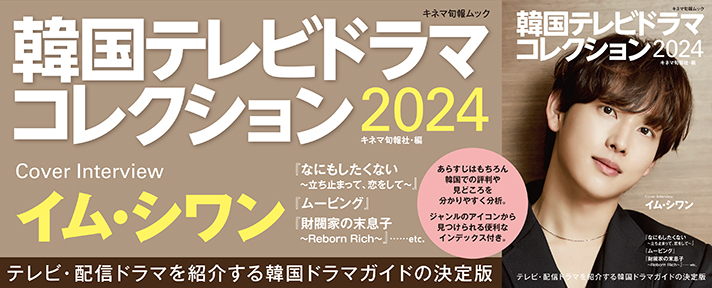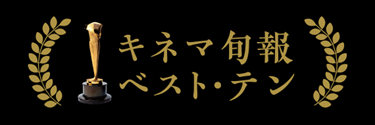記事
「ほから始まるもの」の検索結果
(50件)
記事
「ほから始まるもの」の検索結果
(50件)
-
1985年以来、34年間パレスチナ・イスラエルに通って取材し、ガザ地区、ヨルダン川西岸、東エルサレムなどパレスチナ人地区とイスラエルについて多くのドキュメンタリー映像や著作を発表してきた映像ジャーナリストの土井敏邦監督が、キャリアの集大成として製作したドキュメンタリー映画「愛国の告白—沈黙を破るPart2—」が、11月19日(土)より新宿K’s cinemaほかで全国順次公開。ビジュアルと著名人コメントが到着した。 さまざまな映画賞を受賞して話題を呼んだ「沈黙を破る」から13年。この間、イスラエルでは右傾化が加速し、パレスチナ人自治区にユダヤ人入植地が増殖。ガザ地区ではイスラエル軍の激しい武力攻撃が繰り返されてきた。 “占領軍”の兵士となったイスラエルの若者は、パレスチナ人に対して絶大な権力を行使する中、道徳心や倫理観を麻痺させ、それがやがてイスラエル社会のモラルも崩壊させるという危機感を抱くようになる。そんな元兵士たちの一部が“占領軍”を告発するNGO「Breaking the Silence(沈黙を破る)」を立ち上げた。前作では彼らの姿と証言、そして占領地の凄まじい実態を描いた。 個人と社会の倫理のために占領を告発し続ける彼らの活動は、イスラエル社会でさらに重要な存在意義と役割を持つようになったが、一方で政府や右派勢力からの攻撃も急激に強まっていく。それでも彼らは屈せずに活動を続ける。「自国の加害」と真摯に向き合う元兵士たちの生き方は、私たち日本人にも大きな問いかけをしている。 コメントは以下。 ほんとに観るのがつらい映画だ。 しかし、今だからこそ観なければならないドキュメンタリーだ。 土井敏邦さんの作品を見ていつも思うのは「正義とはなんなのか?」という根源的なことだ。そしてこの映画の凄いところは、イスラエル軍の兵士たちをも「単なる加害者」ではないと伝えている所である。彼らが人間として苦悩し、自分に問いかける感情がはっきりとこちらに伝わってくる。 ──渡辺えり(女優・劇作家) これはパレスチナに対するイスラエルの軍事占領、支配、暴力の物語であるばかりか、ロシア軍に侵攻されているウクライナの物語でもあり、さらにプーチンのロシアにおいて、反戦・非戦の声をあげている人々をめぐる物語でもあり、世界の各地で起こっている国家の暴力による領土獲得という普遍的な問題についての物語であるということだ。さらにここが最も重要な点なのだが、私たち日本で起きている過去の歴史の抹消、修正、改ざんの物語でもあるということだ。 ──金平茂紀(ジャーナリスト) 入植者に蝕まれているパレスチナ人の土地を案内する彼らには、内にこもった攻撃性も、欺瞞を隠す気取りも、現状を容認して体制に適応する卑屈さもない。加害者の側に、これほど理知的な青年たちの運動が生まれたのである。政治状況のために、イスラエル国内で観ることが難しいこの映画を、私たちは観ることができる。この映画との出会いを大切にしたい。 ──野田正彰(精神科医・ノンフィクション作家) 政治や政府と対抗することは「沈黙を破る」グループが求めたものではい。健全な社会を求めるグループの活動が、増え続ける入植地建設、繰り返されるガザ攻撃での無差別空爆など、国際法に反する自国の“加害”を目の当たりにして、グループは政治や政府と対抗して、パレスチナとの関係を模索しなければならなくなった。「愛国の告白」が描く“(前作「沈黙を破る」から)13年後”の現実は、イスラエル政府自身が国と国民の安全と平和を脅かしているという現在のイスラエルの状況を反映している。 ──川上泰徳(中東ジャーナリスト) 「愛国の告白—沈黙を破るPart2—」 監督/撮影/編集/製作:土井敏邦 編集協力:尾尻弘一、渡辺真帆、小林桐美 整音:藤口諒太 デザイン:野田雅也 配給:きろくびと 2022年/日本/170分(第一部100分・第二部70分) ©DOI Toshikuni http://doi-toshikuni.net/j/aikoku
-
自分たちは何者でどこに向かえば良いのか、人生の豊かさとは何かを求めるジョージ・ハリスンの発案で、ザ・ビートルズの4人は超越瞑想運動の創始者マハリシ・マヘーシュ・ヨーギーと出会い、ガンジス川を臨む丘の上のアシュラム(僧院)に招待される──。最高傑作『ホワイト・アルバム』を生んだ1968年のインド滞在期のザ・ビートルズを、当地で偶然の出会いから8日間を共にしたポール・サルツマン監督が捉えたドキュメンタリー「ミーティング・ザ・ビートルズ・イン・インド」が、9月23日(金・祝)よりヒューマントラストシネマ渋谷、池袋シネマ・ロサ、アップリンク吉祥寺、新宿バルト9ほかで全国順次公開。ジョン・レノンにフォーカスした写真ならびに湯川れい子、鈴木慶一、安田顕、GLIM SPANKY、ハリー杉山、立川直樹ら著名人のコメントが到着した。 到着した写真は、当時ピントを合わせるのが難しかった手動カメラで監督がジョンを撮影したもの。アップの表情、マーティンD-28ギターを弾く姿、ポールらとの和やかなセッションを捉えている。 「愛とは時には酷なものだね。だが、いいかい、愛がすばらしいのは、必ず次のチャンスがあるところさ」。この言葉はジョンが失恋で傷心したサルツマン青年にかけた言葉だという。何も知らなかった監督だが、当時すでにジョンはヨーコと出会っており、1969年3月20日に結婚している。 著名人コメントは以下(敬称略・順不同)。 インド、瞑想、ビートルズ。 数々の貴重な証言と、ジョン・レノンの『天国は心の中に』という言葉。 幸運は人それぞれでも、幸福は自分の心の内と向き合えば見つけられるものなのですね。 ビートルズが心の中にいるとき、僕は幸せです。 ──安田顕(俳優) ビートルズと一緒にインドのアシュラムを体験できる、実にマジカルでミステリアスな旅! ──湯川れい子(音楽評論・作詞) 自己啓発のためにインドを訪れたカナダの青年が瞑想に興味を持ち、 マハリシのアシュラムでビートルズと居合わせたのは偶然だったのか、宿命だったのか、 彼が何の下心もなく撮った多くの親密な写真を含むこの淡々としたドキュメンタリーを見るとそんなことを考えてしまいます。 ──ピーター・バラカン(ブロードキャスター) イギリス人の息子として、僕はビートルズの全てを知ってると思ってた。 この作品の蓋を開けてみたら、僕は何も知らなかった。 彼らの本当の素顔、思想、生き様、哲学が今明らかになる。 ──ハリー杉山(タレント) 頭の中の「インドでのビートルズ」が初めてカラーで動き出したような感じ。それが嬉しい。 ビートルズの大ファンならば、彼らが1968年前半に滞在したリシケシュでのマハリシとの日々にある程度思いを馳せると思う。 でも昔から語られている事は大体同じだし、僕たちはアシュラムの中までは入れず、門まで来ては 中の出来事を想像して帰る、の繰り返しだったように思う。今までは! さぁ、このお話の主人公、ポール・サルツマンと共に 1968年のビートルズとガールフレンド達のいるリシケシュへタイムスリップしよう! なんなら瞑想にも興味を持って帰ってきて頂ければ、人生さらに楽しくなるはずです。 ──和田唱(TRICERATOPS) 僕らが知りたかったのはビートルズの過ごしたインド・リシケシュの「空気感」だった。 『ホワイト・アルバム』の楽曲の生まれたその場所、会話、雰囲気。 それが見事に再現されている。60年代の素晴らしい時代感と共に。 ──サエキけんぞう(作詞家、アーティスト) ビートルズの音楽で人生が変わった人間は星の数ほどいるが、サルツマン監督はその中で最もラッキーな一人。 眩しすぎるほどの創作現場を目にして、自身のThe Inner Lightと出会えたのだから。 ──サラーム海上(DJ/中東料理研究家) ここ数年、本当に数多くのドキュメンタリーが公開されているが、この映画の出来の良さ、魅力は別格。 人間関係が綾を成して続く時空を超えた旅の表現方法は映画ならではのものだ。 ──立川直樹(プロデューサー/ディレクター) インドでの4人の“素顔”が、興味深いエピソードとともに明かされる数々の場面を、ただ眺めているだけでも楽しい。 マーク・ルイソンの“現地調査”もたまりません。 これを観て、「来年リシケシュに行こう!」と決めました。 ──藤本国彦(ビートルズ研究家/字幕監修) 全てが奇跡的で、愛に溢れた記録。 インドでビートルズ達と共に過ごしたサルツマン監督から語られる4人の姿はとても自然で、その体験は優しさに包まれていた。ビートルズとラーガ、神秘的で魅力的!私も旅に出たくなる。 ──松尾レミ(GLIM SPANKY/ミュージシャン) 若くしてお金も名声も手に入れた彼らが、新たな刺激を求めたインド滞在の姿をリアルに垣間見ることが出来ました。 もし自分がその場に居合わせたらどんな風に感じるだろう、と想像してとてもワクワクしました! ──亀本寛貴(GLIM SPANKY/ミュージシャン) 音楽の世界において、神格化されている THE BEATLESの4人が、ごく普通の青年達と感じるほど、 彼らの素顔に触れることが出来る本当に貴重なドキュメンタリー! ──ROY(THE BAWDIES) サルツマン氏がインドでTHE BEATLESと出会った 奇跡の8日間で納めた素晴らしい写真の数々と、 THE BEATLESと共に過ごした出来事を、この映画で振り返ってから改めて聴く『ホワイト・アルバム』は、 驚くほどまるで違うアルバムのように聴こえてくる。 全てのTHE BEATLESファンに是非観てもらいたいドキュメンタリーです。 ──TAXMAN(THE BAWDIES) インド滞在中に作曲された名曲たちが生まれるキッカケになった重要な時間を観る事ができる。 また4人の新たな一面が観れました。 ──MARCY(THE BAWDIES) 僕は、母親に初めて聴かせてもらったTHE BEATLESが『ホワイト・アルバム』だった。 その中でも、子どもだった僕は「The Continuing Story of Bungalow Bill」が大好きだった。もちろん今でも。 なぜかは分からないけど、もちろん、キャッチーだった、からかなあ。 この映画を観て、またこの曲を聴き直した。 少し違って聴こえた気がしたけど、やっぱり好きな「The Continuing Story of Bungalow Bill」だった。 THE BEATLESの音楽への、自分自身に対しての問い方が、子どものように、嘘がなく、素直で。 それが子どもの僕に響いたのかなあ、と思った。 ──JIM(THE BAWDIES) 4人がリシケシュで感じた“内なる平和”は、 創作の源が“喜び”であることの再確認だった。 ──はっとり(マカロニえんぴつvo.gt) あの名曲達が、インドで生み落とされるその瞬間。 そして、彼らがお金や名声よりも超越した、本当の幸せを手に入れようとする瞬間の話。 色褪せない興奮と共に語り継いでもらえたような尊い時間でした。 ──藤原さくら(シンガーソングライター) ビートルズ史のミッシングリンクを明らかにする 重要資料であるだけでなく、岐路に立たされた一人の若者に起きた奇跡を振り返る私小説でもある。 まるで1968年、目の前でジョンとポールが曲を作っている現場に立ち会うような体験。 ──オカモトコウキ(OKAMOTO’S/ミュージシャン) ある意味ピュアな青春映画のような趣もあってすがすがしい気持ちになった。 ──伊藤銀次(ミュージシャン) この映画の控えめなドラマティックさは、ドキュメンタリーの醍醐味を ヴォリュームつまみ11で感じつつ耳栓してるような静寂の炸裂を感じる。 モキュメンタリーでは決してないし、フェアリーテールのような事実だ。 見どころはなんとなんとたくさんある。まずはリンゴ、ジョン、ポールの3人のカラー写真のリンゴの足元にあるアタッシュケース、ナグラ(テープレコーダー)ではなさそうだ。缶詰が入ってるのだろうか。そして動くマーク・ルイソン、いったいアシュラムで何曲作曲したかで2つの説を語り合う。本物のバンガロウ・ビルの登場。デヴィッド・リンチがザ・ビートルズについてわずかに語る。当時の動く映像は多くはないが、写真と今しか撮れない映像によってサルツマン監督の実体験を追体験することができるわけだ。 ご本人も再訪するんだから、追々体験かな。 超越的瞑想(当時の言い方)は個を見つめ直す習慣を生んだ。ザ・ビートルズ(主にジョンとポール)はまるで10代で出会った頃のように曲を作っていくのだが、実は大きく違っていた。 成功前と成功後では。これから何をやろうかと、今まで何をやってきたんだろうということなんだろう。 結果生まれた通称「ホワイト・アルバム」は大量の曲と個人主義のビニール円盤×2と なった。でも、この映画の中ではリシケシュ(地図を見るとすぐ中国の国境で、2022年の今は複雑な地政を感じてしまう)で作られた曲はそんなに多くはないと語られる。 うーむ、しかしすべて名曲、ギター奏法、ドキュメンタリーのような歌詞、異邦人性と多様性を内包した名作だと思う。 ここに滞在した意味は大いにあった。いつもザ・ビートルズは体験したことをすぐに作品化していったのだけど。 おまけです。我々、次はどういった録音方法をとろうか。そりゃ「ホワイト・アルバム」的に作ってみようって一体何十回言ったことよ。 鈴木慶一(moonriders) © B6B-II FILMS INC. 2020. All rights reserved 配給:ミモザフィルムズ ▶︎ インド滞在期のビートルズを捉えた「ミーティング・ザ・ビートルズ・イン・インド」
-
〈現代アートハウス入門 ドキュメンタリーの誘惑〉開催。18名の映画作家の推薦作は?
2022年9月16日ミニシアターの呼称で親しまれてきた〈アートハウス〉に新たな観客を呼び込むため、コロナ禍真っ只中の2021年1月に始まった〈現代アートハウス入門〉。その第3弾企画となる巡回上映〈現代アートハウス入門 ドキュメンタリーの誘惑〉が、10月22日(土)よりユーロスペースほかで順次開催される。併せて気鋭の映画作家18名に向けて行われたアンケートの回答が公開された。 近年、日本のアートハウスのプログラムにおいて大きな比重を占めるようになった“ドキュメンタリーと呼ばれる方法で作られた映画”にフォーカスする本企画。18名の映画作家に向けて、 Q1 若く新しい観客に映画の魅力を伝えるために5本の“ドキュメンタリー映画”を観せるとしたら、どんな作品をセレクトしますか? Q2 その理由を800文字から1,200文字程度でお書きください。 というアンケートを投げかけ、挙げられたタイトル群より7作を上映する。ラインナップは9月下旬頃に決定・発表される予定。 Q1に対する各者の回答は以下の通り(※五十音順、敬称略)。ネオクラシックと言いうる傑作からモキュメンタリーまで、多様な方法と視点の作品が出揃った。なお、Q2への回答は現代アートハウス入門の公式サイトで掲載される。 入江悠(映画監督) ・フープ・ドリームス(監督:スティーヴ・ジェームズ|1994年) ・映画は戦場だ 深作欣二in『バトル・ロワイアル』(演出・構成:浦谷年良|2001年) ・東京裁判(監督:小林正樹|1983年) ・ゆきゆきて、神軍(監督:原一男|1987年) ・コレクティブ 国家の嘘(監督:アレクサンダー・ナナウ|2019年) 小川紗良(俳優・映画作家) ・隣る人(監督:刀川和也|2011年) ・沈没家族 劇場版(監督:加納土|2018年) ・さとにきたらええやん(監督:重江良樹|2015年) ・人生フルーツ(監督:伏原健之|2016年) ・ゆきゆきて、神軍(監督:原一男|1987年) 小田香(映画作家) ・マルメロの陽光(監督:ビクトル・エリセ|1992年) ・あの家は黒い(監督:フォルーグ・ファッロフザード|1962年 ) ・Palms(Ladoni)(監督:Artur Aristakisyan|1994年) ・おてんとうさまがほしい(撮影・照明:渡辺生、構成・編集:佐藤真|1994年) ・忘れられた皇軍(監督:大島渚|1963年) 草野なつか(映画作家) ・1000年刻みの日時計 牧野村物語(監督:小川紳介|1986年) ・SELF AND OTHERS(監督:佐藤真|2000年) ・ヴァルパライソにて…(監督:ヨリス・イヴェンス|1963年) ・ミュールハイム(ルール)(監督:ぺーター・ネストラー|1964年) ・書かれた顔(監督:ダニエル・シュミット|1995年) 小森はるか(映像作家) ・阿賀に生きる(監督:佐藤真|1992年) ・草とり草紙(監督:福田克彦|1985年) ・そっちやない、こっちや コミュニティ・ケアへの道(監督:柳澤壽男|1982年) ・ルイジアナ物語(監督:ロバート・フラハティ|1948年) ・アマチュア(監督:クシシュトフ・キェシロフスキ|1979年) 島田隆一(映画監督) ・ぼくの好きな先生(監督:ニコラ・フィリベール|2002年) ・宝島(監督:ギョーム・ブラック|2018年) ・トランスニストラ(監督:アンナ・イボーン|2019年) ・トトとふたりの姉(監督:アレクサンダー・ナナウ|2014年) ・ダゲール街の人々(監督:アニエス・ヴァルダ|1975年) 白石晃士(映画監督) ・光と闇の伝説 コリン・マッケンジー(監督:ピーター・ジャクソン、コスタ・ボーテス|1995年) ・スパイナル・タップ(監督:ロブ・ライナー|1984年) ・ノロイ(監督:白石晃士|2005年) ・オカルト(監督:白石晃士|2008年) ・ハート・オブ・ダークネス コッポラの黙示録(監督:ファックス・バー、ジョージ・ヒッケンルーパー、エレノア・コッポラ|1991年) 瀬田なつき(映画監督) ・三姉妹~雲南の子(監督:ワン・ビン|2012年) ・音のない世界で(監督:ニコラ・フィリベール|1992年) ・100人の子供たちが列車を待っている(監督:イグナシオ・アグエロ|1988年) ・少年裁判所(監督:フレデリック・ワイズマン|1973年) ・教室の子供たち 学習指導への道(監督:羽仁進|1954年) 想田和弘(映画作家) ・Forever(監督:エディ・ホニグマン|2006年) ・In Comparison(監督:ハルーン・ファロッキ|2009年) ・My Name Is Salt(監督:ファリーダ・パチャ|2013年) ・Los Reyes(監督:Bettina Perut & Ivan Osnovikoff|2018年) ・Ostrov – Lost Island(監督:Svetlana Rodina & Laurent Stoop|2021年) 富田克也(映画監督) ・旅するパオジャンフー(監督:柳町光男|1995年) or ゴッド・スピード・ユー! BLACK EMPEROR(監督:柳町光男|1976年) ・山谷 やられたらやりかえせ(監督:佐藤満男、山岡強一|1985年) ・1000年刻みの日時計 牧野村物語(監督:小川紳介|1986年) or どっこい!人間節 寿・自由労働者の街(構成:小川紳介|1975年) ・忘れられた皇軍(監督:大島渚|1963年) ・からゆきさん(監督:今村昌平|1973年) 広瀬奈々子(映画監督) ・マルメロの陽光(監督:ビクトル・エリセ|1992年) ・圧殺の森 高崎経済大学闘争の記録(監督:小川紳介|1967年) ・FAKE(監督:森達也|2016年) ・物語る私たち(監督:サラ・ポーリー|2012年) ・人間ピラミッド(監督:ジャン・ルーシュ|1961年) 深田晃司(映画監督) ・メキシコ万歳(監督:セルゲイ・エイゼイシュテイン、グリゴリー・アレクサンドロフ|1932、1979年) ・動物園(監督:フレデリック・ワイズマン|1993年) ・セザンヌ(監督:ストローブ=ユイレ|1989年) ・花子(監督:佐藤真|2001年) ・快適な生活(監督:ニック・パーク|1989年) 藤元明緒(映画監督) ・ヴァンダの部屋(監督:ペドロ・コスタ|2000年) ・マルメロの陽光(監督:ビクトル・エリセ|1992年) ・ドキュメンタリー映画100万回生きたねこ(監督:小谷忠典|2012年) ・三姉妹~雲南の子(監督:ワン・ビン|2012年) ・ミッドナイト・トラベラー(監督:ハッサン・ファジリ|2019年) 甫木元空(映画監督) ・路地へ 中上健次の残したフィルム(監督:青山真治|2000年) ・ヴァンダの部屋(監督:ペドロ・コスタ|2000年) ・SELF AND OTHERS(監督:佐藤真|2000年) ・書かれた顔(監督:ダニエル・シュミット|1995年) ・ワン・プラス・ワン(監督:ジャン=リュック・ゴダール|1968年) 松林要樹(映画監督) ・My Name Is Salt(監督:ファリーダ・パチャ|2013年) ・Vivan las Antipodas(監督:ヴィクトル・コサコフスキー|2011年) ・コヤニスカッティ/平衡を失った世界(監督:ゴッドフリー・レッジョ|1982年) ・これがロシヤだ/カメラを持った男(監督:ジガ・ヴェルトフ|1929年) ・アンダルシアの犬(監督:ルイス・ブニュエル、サルバドール・ダリ|1928年) 三宅唱(映画監督) ・アウトレイジ 最終章(監督:北野武|2017年) ・百年恋歌(監督:侯孝賢|2005年) ・6才のボクが、大人になるまで。(監督:リチャード・リンクレイター|2014年) ・ハドソン川の奇跡(監督:クリント・イーストウッド|2016年) ・エリ・エリ・レマ・サバクタニ(監督:青山真治|2005年) 山中瑶子(映画監督) ・マルメロの陽光(監督:ビクトル・エリセ|1992年) ・アヒルの子(監督:小野さやか|2005年) ・東京干潟(監督:村上浩康|2019年) ・グレイ・ガーデンズ(監督:アルバート・メイズルス、デヴィッド・メイズルス、エレン・ホド、マフィー・メイヤー|1975年) ・セルロイド・クローゼット(監督:ロブ・エプスタイン、ジェフリー・フリードマン|1995年) 横浜聡子(映画監督) ・イヨマンテ 熊おくり(監督:姫田忠義|1977年) ・教室の子供たち 学習指導への道(監督:羽仁進|1954年) ・絵を描く子どもたち 児童画を理解するために(監督:羽仁進|1956年) ・モアナ 南海の歓喜(監督:ロバート・フラハティ|1926、1980、2014年) ・ダゲール街の人々(監督:アニエス・ヴァルダ|1975年) ・グレイ・ガーデンズ(監督:アルバート・メイズルス、デヴィッド・メイズルス、エレン・ホド、マフィー・メイヤー|1975年) 〈現代アートハウス入門 ドキュメンタリーの誘惑〉 企画・運営:東風 企画協力:ユーロスペース 技術協力・予告篇制作:restafilms WEB制作:坂元純(月光堂) デザイン:loneliness books 文化庁「ARTS for the future! 2」補助対象事業 ©2022AHG https://arthouse-guide.jp/ -
ベネディクト・カンバーバッチが伝説のネコ画家に。「ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ」
2022年9月16日19世紀末から20世紀にかけてイギリスで大人気を博した “ネコ画家” ルイス・ウェインの人生を、ベネディクト・カンバーバッチ主演で描いた「ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ」が、12月1日(木)よりTOHOシネマズ シャンテほかで全国公開。場面写真が到着した。 当時はネズミ退治役として軽んじられるか不吉な存在として恐れられていたネコの魅力を“発見”し、夏目漱石にインスピレーションを与え、SFの巨匠H・G・ウェルズに「ルイス・ウェインは独自の猫を発明した」と称賛されたイラストレーターのルイス・ウェイン。その人生には、深い愛で彼を生涯守り続けた妻エミリーと、親友にして人生の師であるネコのピーターとの物語があった──。 ベネディクト・カンバーバッチが不器用でピュアでお茶目な天才ルイスに扮し、「ファースト・マン」『ザ・クラウン』のクレア・フォイがエミリー役で共演。ネコのピーターを、年齢に応じて3匹のネコが演じ分けている。 さらに「バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)」のアンドレア・ライズボロー、「裏切りのサーカス」のトビー・ジョーンズ、「わたしは、ダニエル・ブレイク」のヘイリー・スクワイアーズが脇を固め、「ジョジョ・ラビット」のタイカ・ワイティティ監督とミュージシャンのニック・ケイヴも意外な役柄で登場。そして「女王陛下のお気に入り」のオスカー女優オリヴィア・コールマンがナレーションを担当する。 監督は、俳優としても活躍する日系イギリス人のウィル・シャープ。エレガントな衣装を手掛けたのは、「ある公爵夫人の生涯」でオスカーを獲得したマイケル・オコナー。 たとえ命が尽きても、愛は残された者と共に生き続けると信じさせてくれる、優しくも温かな物語に期待したい。 Story イギリスの上流階級に生まれたルイス・ウェインは、父亡き後に一家を支えるため、ロンドンニュース紙でイラストレーターとして活躍する。やがて、妹の家庭教師エミリーと恋に落ちたルイスは、身分違いだと大反対する周囲の声を押し切って結婚するが、まもなくエミリーは末期ガンを宣告される。庭に迷い込んだ子猫をピーターと名づけ、その姿をエミリーのために描き始めるルイス。深い絆で結ばれた“3人”は、残された日々を慈しむように大切に過ごしていくが、ついにエミリーがこの世を去る日が訪れる。ルイスはピーターを心の友とし、ネコの絵を猛然と描き続けて大成功を手にする。そして、「どんなに悲しくても描き続けて」というエミリーの言葉の本当の意味を知る──。 「ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ」 出演:ベネディクト・カンバーバッチ、クレア・フォイ、アンドレア・ライズボロー、トビー・ジョーンズ、オリヴィア・コールマン(ナレーション) 監督・脚本:ウィル・シャープ 原案・脚本:サイモン・スティーブンソン 2021年/イギリス/英語/111分/カラー/スタンダード/5.1ch/G/原題:The Electrical Life of Louis Wain/字幕翻訳:岩辺いずみ 提供:木下グループ 配給:キノフィルムズ ©2021 STUDIOCANAL SAS - CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION 公式Twitter:@louis_wain_film 公式HP:louis-wain.jp -
直木賞作家・島本理生が顔にアザのある女性を主人公に綴った恋愛小説を、監督・安川有果 × 脚本・城定秀夫で、松井玲奈と中島歩の共演により映画化した「よだかの片想い」が、9月16日(金)より新宿武蔵野館ほかで全国公開。俳優の倍賞千恵子、映画監督の奥田裕介、映画評論家の森直人、太田母斑の主人公を描く漫画『青に、ふれる。』の作者・鈴木望ら著名人のコメント、ならびにmajoccoと秋鹿えいとのイラストが到着した。 [caption id="attachment_15975" align="alignnone" width="660"] ▲majoccoイラスト[/caption] [caption id="attachment_15976" align="alignnone" width="660"] ▲秋鹿えいとイラスト[/caption] 理系大学生の前田アイコ(松井玲奈)は、顔の左側のアザを幼い頃にからかわれた辛い経験から、恋や遊びに消極的だった。だが取材を受けた「顔にアザや怪我を負った人」のルポルタージュ本が話題となり、状況は一変。本の映画化の話が進み、友人の編集者・まりえの紹介で、監督の飛坂逢太(中島歩)と出会う。そして、初めは映画化を断っていたが、話すうちに彼の人柄に惹かれていく。飛坂への片想いを自覚し、不器用に距離を縮めていくアイコ。しかし、飛坂の元恋人の存在、さらに飛坂は映画のために自分に近づいたという疑心暗鬼が、彼女の恋と人生を大きく変えていく……。 各者コメントは以下(※50音順・敬称略)。 青柳美帆子(ライター) 島本理生の生み出した、恋でぼろぼろに傷つき、恋で自分を知る女の子。むずかしい恋だとわかっていても、飛び込まずにはいられない。松井玲奈が浮かび上がらせたアイコの輪郭を、安川有果は光の中に映していく。 秋鹿えいと(漫画家) イラスト寄稿 池田園子(株式会社プレスラボ代表取締役) 踏み出すのが怖い、という感情を持つのは自然なこと。でも、一歩進んでみれば違う世界が見えてくる。アイコがときに涙を流しながらも、しなやかな強さを宿して踊る様は、観る者の背中を優しく押してくれる。 奥田裕介(映画監督) 「女性監督ならではの視点」なんて野暮な言葉だ。安川有果という監督が捉える感情には、心の芯を震わす力があり、繊細さに寄り添う姿勢はいつしか攻撃的な気味悪さに変わっている。登場人物たちが「二本の足で立つ」その瞬間が描かれている。それがどうにもこうにも美しかった。カッコよかった。絶対に映画館で観届けて欲しい。 太田尚樹(LGBTエンタメサイト「やる気あり美」編集長) 光を教えてくれるのが闇であるように、マイノリティという経験は「ない方がよかったが、あってよかった」と私にいつも思わせる。きっと、アイコの闇は消えない。だがそれは、アイコのそばに光がこれからありつづけることを意味している。ラストシーンのかがやきは、彼女の美しさそのものだった。 苅部太郎(写真家) 人間の目は全ての光を見ることができない。紫外線や赤外線などをのぞく、ごく限られた可視域の世 界の中でさえ、どれほど自分は「見えているのか」。そのことに気づかせてくれる、鏡のような物語。 神崎メリ(恋愛コラムニスト) ざらざらのカカトを軽石で擦って磨き上げるように、切ない恋は少女をオトナへと磨き上げてくれる…。 「おクズ様は女の人生の軽石ですなぁ」と心を前向きにしてくれるステキな映画でした。 神原由佳(アルビノ当事者) きれいな俳優が「顔にアザのある女性」を演じる事に期待と不安がありました。主人公アイコは恋に臆病で、だけど好きという気持ちにまっすぐな強い女性です。私も、一方的な視線を向けられるのではなく、真剣に誰かと向き合う恋がしたいと思いました。 北村紗衣(研究者) 赤の他人のインスピレーションの源になるというのはわくわくするような体験でもあり、とてもつらい体験でもあります。この映画は、そうした経験を芸術作品のモデルになる人の視点から繊細なタッチで描いています 児玉美月(映画執筆家) この映画は「ありのままの自分を愛そう」と声高に謳わない。こんなに傷つけられてしまう恋愛ばかりのこの世界で、否応なくルッキズムに縛られてしまうこの世界で、「ありのままの自分」が脆弱な存在になりえるこの世界で、そんなメッセージはときに、欺瞞の響きを伴いさえするだろう。安川有果はひとりの女性の〈片想い〉に、多くの〈想い〉を込めた。ひとつのドラマを跳び越えて、そこには映画作家として、映画が内包してきてしまった非対称性や暴力への自覚的な意思表明も含まれている。シスターフッドを伴奏にして見えない羽根を揺らす女性たちの舞いが途切れるその瞬間まで、眩く切実な〈想い〉のすべてを決して取り零してはいけない。 下村健一(ジャーナリスト) 好奇の目より、それを叱る言葉の方が痛いとか。「びわ湖」が刺さる とか。当事者の多様なリアルが細やかに織り込まれ、観る者の傍らに“気づき”をそっと置いていってくれる。決して押し付けることなく。 鈴木望(『青に、ふれる。』漫画家) 誰かと深く関わりたいと思った時、より深く見つめるのは自分の内面なのだ…と、どんどん表情が変わっていくアイコと一緒に、感情のジェットコースターに乗っている気分でした。 観終わった後は温かな気持ち。 素敵な気持ちでした。 沢山の方に届いてほしい作品です。 外川浩子(NPO法人マイフェイス・マイスタイル代表) 「“見た目”と正直に向きあえば、人生の次の扉が開かれる。」 アイコを通して、誰もがそう実感できる映画です。 西森路代(ライター) かすか不安や、かすかな疑い、その積み重ねによって得られる、ともすれば切り落とされてしまいそうな細やかな感情のひとつひとつが伝わってくる。そんな映画でした。 倍賞千恵子(俳優) じんわりとしみ込んできて心の中にソット足音を残されたような気がしました。世の中には白黒をつける事が出来ない事がある中彼女が生きている様がよかった。そして周りで生きている俳優さん達の無理のない居方心地がよかった。安川さん鎌倉の上映会で会えて良かったね。映画を愛してくれてありがとう。 はらだ有彩(文筆家) 「マイノリティ性」を通して当事者が世界を見ることと、世界がマイノリティ性を通して当事者を見ること。カタルシスに他者が踏み入るときの足跡、その足跡の粗さ、それでもあなたが居心地のいい場所を選ぼうと思えるなら。 真魚八重子(映画評論家) 控えめに生きてきた瓜実顔の女は、曖昧な恋愛に揺らぎ、愛するゆえの孤独を感じる。それは自然な感情だ。凛として乱れる前にみずからをとどめる強さ。ラストの夕陽を指した彼女の姿は、美しくて走馬燈に現れそうだ。 majocco(イラストレーター) *イラスト寄稿 「でも、美人でしょう」 「でも、頭がいいのでしょう」 「でも、お金があるのでしょう」 「でも、家族に恵まれているのでしょう」 「でも、あなたは主人公になるのでしょう」 「でも、顔にアザがあるでしょう」 「でも」の全部を無視できればいいのに。 アイコの心、選んで産み出した光のことだけ大好きになりたい。それは誰にもできない。 選べなかった全てと、選んできた全てには関係があるから。 「でも」「だから」みたいな、 すべてをひっくるめて人を大好きになったり、 大嫌いになったりすることしかできないなと感じる映画でした。 水野敬也(作家/「顔ニモマケズ」著者) 開始13分で主人公のアイコ(松井玲奈)と一緒に号泣し、そのあとも数えきれないくらい泣かされたけれど、ただの感動作ではなくすべての個人を悩みから解放する作品で、とか色々言ってきたけれど、めっちゃ好き。めちゃくちゃ好きな映画でした。 森直人(映画評論家) 増村保造からセリーヌ・シアマの遙か先まで走っていく怒涛の100分。クラシックな恋愛映画の濃密さに、ルッキズム、当事者と演技、表現の加害性など、あらゆる現代の問題提起がぶち込まれて、全く新しい映画に変容する。これが僕の今年のベストワンです。 ロックバンド「騒音寺」Vocal Nabe 数年前、当事者の方々の交流会で演奏し、短いながら皆と話をしてみると、皆が「想像以上に」明るい事に驚いた。差別区別のない私だと思っていたのだが「想像以上に」という感覚を私は恥じた。これこそ見た目を差別してきた感覚だったからだ。映画を見たあとあの頃の私の恥ずかしさが思い起こされた。誰も当事者本人にはなれないが、この映画を機に少しずつあなたの「見る目」が変わればいい。以前の私のように。人は仕事もするし恋もする。あなたも当事者も同じ社会に立っている。とても美しい映画をありがとう! ©島本理生/集英社 ©2021映画「よだかの片想い」製作委員会 配給:ラビットハウス ▶︎ 松井玲奈がアザのあるヒロイン。島本理生原作「よだかの片想い」の本予告&ビジュアル到着