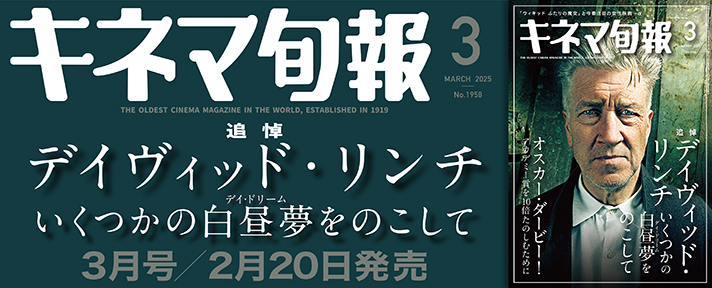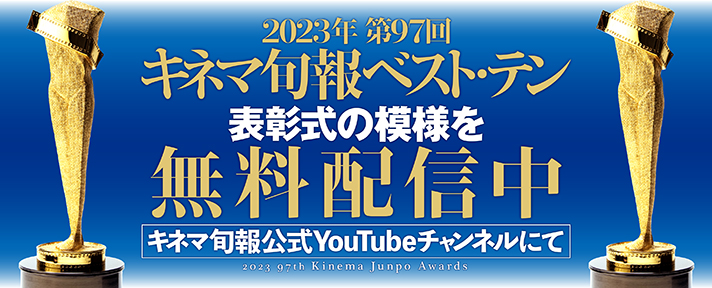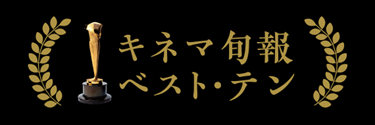親愛なる同志たちへの映画専門家レビュー一覧
親愛なる同志たちへ
1962年にソ連南部の地方都市ノボチェルカッスクで実際に起こった市民の虐殺事件。それはソ連崩壊の1992年まで30年間、国家によって隠蔽された。労働者のデモ弾圧に発したこの衝撃的事件の真相を、シングルマザーで共産党員でもある主人公の愛娘捜索を軸に描いた歴史大作。監督は「暴走機関車」(85)、「映写技師は見ていた」(91)や、タルコフスキー作品の共同脚本などで知られる、現在84歳となるロシアの巨匠アンドレイ・コンチャロフスキー。全編をモノクロかつ1.33:1のアスペクト比で撮影することで、当時のソ連社会の冷徹な空気を描出した。監督の妻でもあるユリア・ヴィソツカヤが主人公のリューダを演じた。スターリンを敬愛し、ソ連の繁栄を信じて疑わなかったリューダは、非武装の市民が次々に殺害される現場を目の当たりにして、自らのアイデンティティーを打ち砕かれていく。さらに事件を主導したKGBのメンバーの男ヴィクトルも、リューダの娘の捜索に協力するなかで、事件の隠蔽を図る国家の非情な実態を目撃する。国家に忠誠を誓った二人にとって、“祖国”とは果たして何だったのか……。
-
映画監督/脚本家
いまおかしんじ
可愛げのない主人公の女の人が、だんだん可愛く見えてくる。バタバタ部屋を行き来する。乱暴にドアを閉める。娘を探して半狂乱になって歩き回る。泣き喚く。理想と現実がこれほどまでに離れてしまうと人はどうなるのか? 彼女は転がっている死体を平然と眺める。彼女の感情を抑えた表情と動きに持って行かれた。かっこいい。そして哀しい。権力を持った人たちがどれほどアホなのか。ロシアの監督が、こんなにもロシアがひどかったというのを冷静に描いていることに驚く。
-
文筆家/女優
唾蓮みどり
祖国と何か。そんなものは幻想であると言い切ってしまえば簡単だ。理想と現実の板挟みになるのは常に労働者であり、労働者たちは生活を守るために闘わねばならない。家族とは何か。そんなものは所詮、他人同士が集まった最小限の共同体だと言ってしまうのも簡単だ。冷たくて暗い川の水面に、季節外れの花びらが舞い降りてきたような、そんな瞬間を垣間見た。緊張感が走るなかに思いがけない温かみがある。この映画で流れた血は果たして何色だったか。モノクロに思いを馳せる。
-
映画批評家、東京都立大助教
須藤健太郎
リューダは矛盾を一身に体現する存在だ。公と私、忠誠と裏切り、過去と現在、敵と味方、彼女の中ではあらゆる対立が同居している。人混みがあっても並ぶことなく、誰もが逃げ出す場所へと逆流して赴く。冒頭、彼女の姿が鏡を通して反転された形でしか映されないのは示唆的だった。ノヴォチェルカッスクの虐殺はソ連という国家が孕んだ矛盾そのものだったのかもしれない。労働者国家に生じた労働者の反乱であり、国家は市民を虐殺しておきながら、痕跡を消してなかったことにした。
1 -
3件表示/全3件