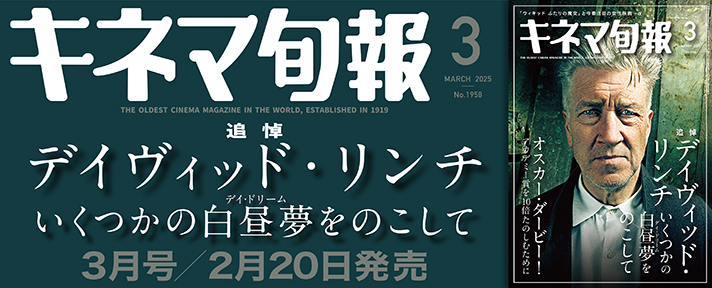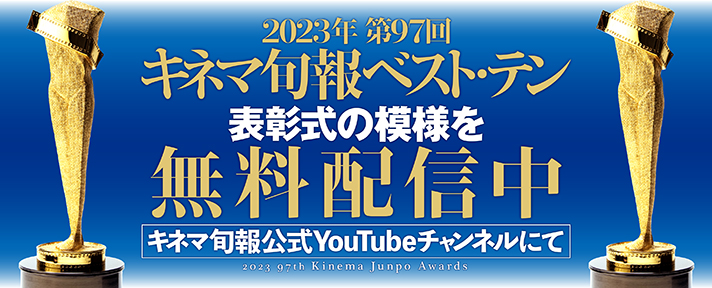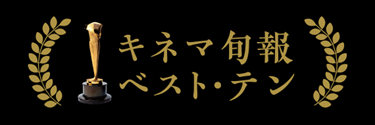美と殺戮のすべての映画専門家レビュー一覧
-
文筆業
奈々村久生
アウトサイダーカルチャーのシーンと製薬会社の過失を記録した志の高さは認めるが、映像によって語る行為において、自分が映画という表現に求めるものとは異なると言わざるを得ない。メインの被写体であるナン・ゴールディンの写真がスライドショー形式で上映されるのを彷彿とさせるような画づくりは、テーマありきで構成され、ビジュアルや言葉はそれを裏づける資料として機能する。ゴールディンの実像もその筋書き以上には見えてこない。題材と手法が必ずしも比例しないのは悩ましい。
-
アダルトビデオ監督
二村ヒトシ
世界から痛めつけられている。生きているだけで痛い。〈普通〉じゃない私だけの痛み。痛みがあるから芸術を創作し、痛みがあるから恋愛する。鑑賞者の痛みを刺激して感動される。痛い恋愛してるから殴られて眼底骨折する。痛いから戦える。痛いから何らかの依存症になる。痛みなんかないほうがいい。痛みを消してくれる危険な薬物を大量生産して人を殺して儲ける〈普通〉の人非人。ナンは言う。「売春していたことは初めて話した。売春は恥ずかしい仕事ではない。けれど、楽な仕事でもない」
-
映画評論家
真魚八重子
ナン・ゴールディンが仲間と、サックラー家が販売製造し中毒者を多く出している「オピオイド系鎮痛剤」に反対運動をしている。映画はナンの過去を振り返り、むしろ80年代にはLGBTQの人々が集まる店で働き、ドラッグサブカルチャーの写真を撮っていたことを語る。被写体の多くをエイズで失ってしまったことも。自己判断で麻薬をやることと、医師の処方箋によってオピオイドの中毒になるのはあまりに違う。それは謎の病気だったエイズが自己判断の死でなかったことと一緒なのだ。
1 -
3件表示/全3件