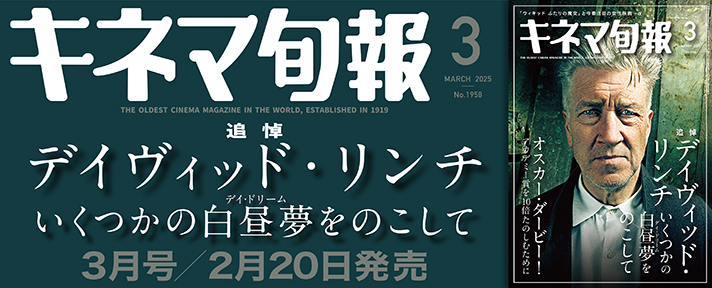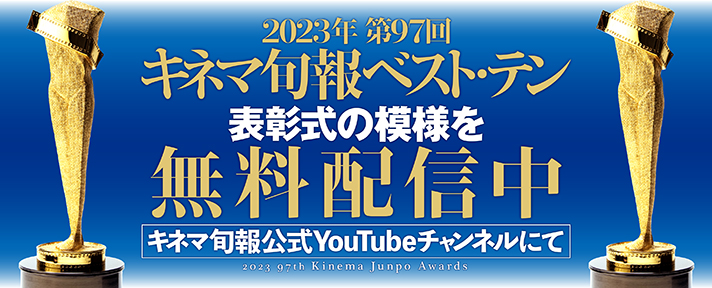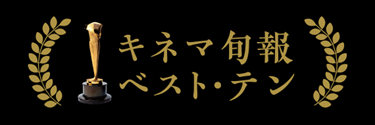キュリー夫人 天才科学者の愛と情熱の映画専門家レビュー一覧
キュリー夫人 天才科学者の愛と情熱
人類史上初めてノーベル賞を2度受賞した天才科学者キュリー夫人の激動の半生を、実話をもとに描いたヒューマンドラマ。放射線元素を発見し、1903年にノーベル物理学賞、1911年に同科学賞を受賞した輝かしい業績、愛する夫との出会いと別れ、女性や移民であるため差別を受けたことなど、知られざる人生の“光と影”に焦点を当てる。キュリー夫人を「ゴーン・ガール」のロザムンド・パイク、夫ピエールを「マレフィセント」シリーズのサム・ライリー、監督を「ペルセポリス」のマルジャン・サトラピが務めた。
-
映画評論家
上島春彦
もちろん偉大な女性科学者の伝記映画だが、原題を読めば分かるように放射能科学のその後、半世紀の推移も見据えた作りになっている。広島での原爆使用から戦後の核実験(高性能爆弾開発)、さらに旧ソ連体制下の原発事故まで。そこでは医療への活用という肯定的な側面も紹介されてはいるのだが、彼女が生きている時から人体への放射能の甚大な影響はとっくに知られていたというのが怖い。やっぱり知っててもやるのが科学者だ。愛人との生々しいスキャンダル事件も見どころたっぷり。
-
映画執筆家
児玉美月
この伝記映画は男性中心的な科学界において功績を残した「キュリー夫人」ことマリの偉大さを過度に称えるのでもなく、女性差別を殊更に糾弾するのでもなく、彼女の人生そのものをありのまま映し出したいようである。だからこそラストにまで位置付けられている夫ピエールとのロマンティックな関係の濃密さは、いかに性差別による不当な処遇と彼への深い愛情の中で生きたかというマリのジレンマを裏付ける為に必然性があるともいえるが、この時代にそれが合致しているかは疑問が残る。
-
映画監督
宮崎大祐
キュリー夫人というとそのキャッチーな名称と裏腹に、小学校の教室にある自伝本コーナーでも最後まで取り残されることが多い、なんとも地味な偉人だという印象がある。そんな印象を払拭するなにかを提供しようとキュリー夫人演ずるロザムンド・パイクは熱演をつづけるが、作者の政治思想を披瀝するためにとってつけたような説教くさいドラマと記号的に挿入される放射能がらみの歴史的事象がわれわれの意識を「核で敵国を脅しあう」進歩のない現実へと引き戻す。
1 -
3件表示/全3件