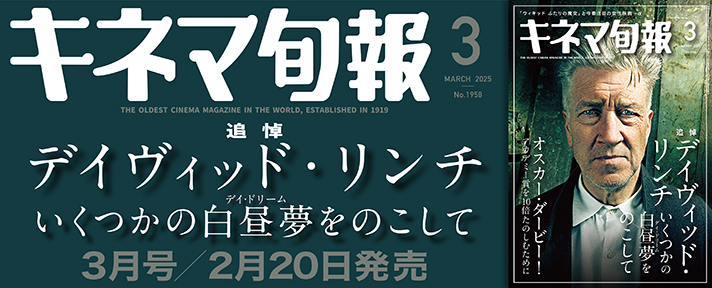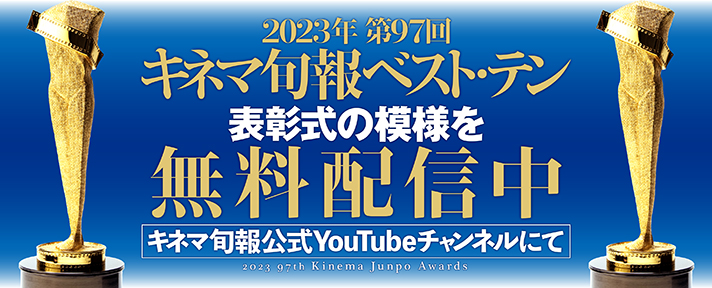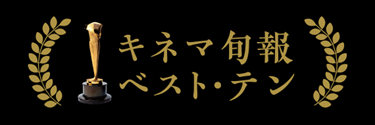苦い涙の映画専門家レビュー一覧
-
米文学・文化研究
冨塚亮平
当該作のリメイクというよりは、ファスビンダーのキャリア全体を踏まえつつ性別や職業をオゾンの当事者性に引きつけた改作といった趣。鏡を活用して画面が演劇的になることを防ぎつつ、本家の閉塞感よりもむしろ開放感を感じさせる撮影や、他作品への捻りの効いたオマージュなど、随所に批評性が感じられるのは確か。ただその反面、俳優陣を含めてファスビンダー映画への敬意が強すぎたのか、原作同様の感情のもつれをどう表現するかまで含め、全てが知的な操作に過ぎないようにも。
-
日本未公開映画上映・配給団体Gucchi's Free School主宰
降矢聡
見るからに上手くいきそうにない有名な映画監督と若い俳優のカップルが、誰もが予想するような破綻の迎え方をする。映画監督も俳優も圧倒的にどうしようもない感じが、まさに映画業界の権威が著しく低下している現在にぴったり。人間的に「クズ」だが、常人にはないこの愚かさこそ、偉大な監督や俳優の素質なのだ、などという転倒した肯定ももちろんなく、ひたすら唾棄すべき人物として描かれているところは極めて現代的かもしれない。文字通り唾を吐かれるシーンは失笑を誘う。
-
文筆業
八幡橙
目に、耳に、毒々しくも鮮やかで美しく、時に滑稽にして物悲しい、これはもうオゾンにしか描けない、オゾンだけの「苦い涙」だ。ファスビンダー版との比較や旧作の講釈を脇に置いても、若き美青年に翻弄される巨漢の映画監督の揺れ動く心、表情、身のこなし、どこか「ベニスに死す」にも通じる芸術的破滅の道行きはそれ自体が単純に面白く、大いに心そそられる。人間とは、かくも愚かなり。それでも愛さずにおれないピーターを全身で魅せたドゥニ・メノーシェ、快なる哉。
1 -
3件表示/全3件