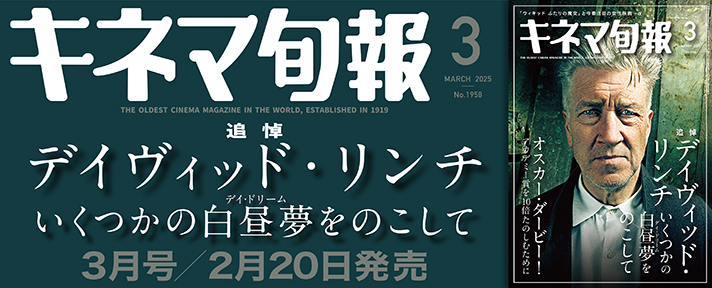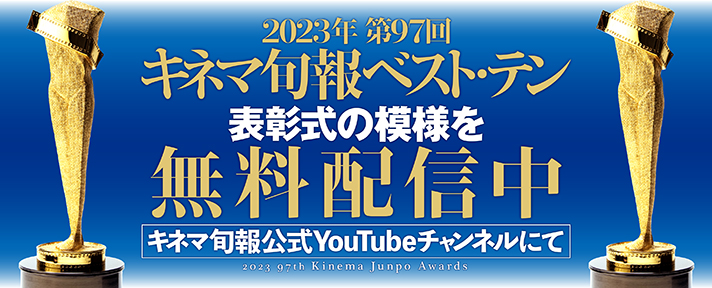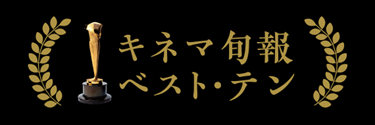映画専門家レビュー一覧
-
わたしの物語
-
文筆業
奈々村久生
差別や偏見が生まれる一因として「見慣れていない」ことは強く作用する。監督かつ被写体であるエラの下半身が短い容姿は多くの人にとって「きわめて稀」だと思われるが、約1時間半の上映中にエラの姿に触れ続けるだけでも認識は劇的に変わる。要は「慣れる」。四肢延長と再建手術の権威である医師との対面はハイライトで、誰かを否定したとて自分を肯定できるわけではない複雑さをエラの表情が物語る。エラの夫の視点がないことは、彼女たちの関係にとって障がいが絶対的ではない証だろうか。
-
アダルトビデオ監督
二村ヒトシ
エラ監督は美人だ(とジャッジしてるんだからこの短評はルッキズムという差別である)が映画ではそこは言及されない。若い美女でありつつ障がい者でもあることはそれはそれで大変だろう。ところでメガネをかけなければ外出できない我々は障がい者だが、メガネやコンタクトという補助具が普及しまくったから生きることができてる。治療したほうが幸せだという医療モデルと、矯正するのではなく当人の自己受容の尊厳を大切にするべきとの考えの、人生を賭けた対立が凄い。いい映画でした。
-
映画評論家
真魚八重子
生まれつき、両足に障がいがあるエラ・グレンディニング監督。特徴的な障がいの中でも、片足だけの症状が多く、両足という例は他に会ったことがないという。障がいが世界でも自分だけというのはなんと不安なことか。その合間に映るエラの私生活は、恋人と生活をエンジョイする積極性が印象深い。手術による治療も進んでいるが、幼児期から何度も手術をし、部分的な切断なども余儀なくされる。自身で判断がつかぬ年齢からの治療や、健常者と同じが良いことなのかを問いかける映画だ。
-
-
アンゼルム “傷ついた世界”の芸術家
-
映画監督
清原惟
アンゼルム・キーファーの作品を紹介するためにヴェンダースがとった手法は、言葉を削ぎ落として、高精細で抽象的なイメージを使うということ。少年時代のシーンなどはノスタルジーを感じてしまわなくもないが、同世代の作家として世界観に共鳴して撮っているのも窺える。制作風景の場面では、80歳近い作家自身が熱々の液体を絵にぶちまけていてスリリングで良かった。ヨーロッパの負の歴史に向き合う作家が、現代社会とどのように向き合っているのか、もっと知りたい気持ちが芽生えた。
-
編集者、映画批評家
高崎俊夫
ヴェンダースは敗戦の前後に生まれ、同時代としての戦後を生きたアンゼルム・キーファーの膨大な作品を俯瞰する際、注釈としてハイデガーとパウル・ツェランを引用する。ナチズムの〈凡庸な悪〉を告発したハンナ・アーレントの愛人・師でありナチスに加担した大哲学者と虐殺から生き残ったユダヤ詩人の対比が印象に残る。とりわけツェランの肉声による詩の朗読が延々と流れる件が忘れがたい。ホロコーストの呪縛を抱えた母国へのアンビヴァレントな想念が本作の純粋心棒といえよう。
-
映画批評・編集
渡部幻
ドイツの芸術家アンゼルム・キーファーのドキュメンタリー。冒頭にドレスの彫刻群が現れる。頭がなく、代わりに本や石が乗せられ、ガラスの破片が刺さったものもある。女性の声——「私たちは名もなく忘れられし者。でも私たちは忘れない」——空間を時間が浮遊している。ドイツ降伏の1945年に生まれたアンゼルムは、自国の過去と対峙し、その忘却に抗う壮大な絵画と彫刻を連作。同年生まれのヴェンダースは「ベルリン」を撮った。3Dを2Dで観た。が、それでもここには紛れもない“映画の感動”があった。
-
-
ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ
-
映画監督
清原惟
人間は自分以外の誰かのために自分の人生をつかうことができる。そのことを信じさせてくれる素晴らしい作品だった。初めは気軽な学園コメディだと思い観ていたが、少年が一人取り残されるあたりから、クリスマスの神聖な空気も相まって映画全体が神秘的な空気で包まれた。出てくる人たちは、別にみんな善人というわけでもない。それでも、たとえ人生の中の一瞬の出来事であっても、人間と人間の儚く強い結びつきが存在できたことに心震える。クリスマス映画の定番になってほしい!
-
編集者、映画批評家
高崎俊夫
1970年という映画の時代背景はアメリカン・ニューシネマの全盛期にあたるが、既成のヒットポップスを一見、無造作に垂れ流すような手法はまるで「卒業」のようである(映画館でD・ホフマンの「小さな巨人」を見るシーンあり)。無論下敷きになっているのはハル・アシュビーの「さらば冬のかもめ」だろう。互いに反撥しあう師弟関係が繊細な感情教育によって変容を遂げてゆく。こんな深い味わいをもったロードムービーは本当に久しぶりだ。ポール・ジアマッティの新たな代表作である。
-
映画批評・編集
渡部幻
アレクサンダー・ペインは今もロードムービー作家であり続けていて、世がどうであろうとも人間主義を手放さない。名優ポール・ジアマッティも同様だ。例えば同じペインとの「サイドウェイ」、あるいはクローネンバーグの「コズモポリス」終盤で映画全体をさらったあの人間臭さ。1970年のクリスマスが舞台の教師と生徒の物語。冬の映画であり、70年代のハル・アシュビー好きは気に入るのではないか。我が道をゆくアメリカ監督による小さな宝石。ぼくならオスカーはジアマッティに投票しただろう。
-
-
ディア・ファミリー
-
ライター、編集
岡本敦史
「実話ベースのお涙頂戴もの」というイメージで甘く見てはいけない良作。日本人好みの『下町ロケット』的な熱血技術開発秘話と、常に哀歓を湛えた家族の年代記が並行して描かれる物語は、現実の悲劇に対して不謹慎な物言いだが、秀逸な構造である。それに対してオーソドックスに徹する演出の賢明さも好ましい。ただ、IABPバルーンカテーテルという名称を劇中であれだけ連呼するなら、もっと専門的ディテールを見せてもよかった。観客の知識欲も満たすことが作品の厚みになるのだから。
-
映画評論家
北川れい子
かつてのNHKの看板ドキュメンタリー『プロジェクトX 挑戦者たち』が、『新プロジェクトX〜』としてこの4月から復活したが、本作はさしずめ“プロジェクトX“の個人版。町工場の経営者が、心臓に疾患のある娘のために、自ら時間と資金を注ぎこんで医療器具の開発に挑み、やがて多くの命を救う器具を完成するまで。むろんその過程で大学の研究者や専門家なども関わり、具体的な器具がいくつも作られる。主人公の飽くなき探究心と家族愛には頭が下がるが、大泉洋の見え見えの熱演が煩くも。ごめん。
-
映画評論家
吉田伊知郎
冒頭でカテーテル開発をめぐる映画であることが明かされるので、人工心臓の開発に四苦八苦する前半に、いつカテーテル開発に切り替わるのかとやきもき。しかし、大泉の軽やかさが猪突猛進型のキャラを暑苦しくさせない。川栄、福本ら姉妹の関係性もさり気なく描かれ、押しつけがましい感動映画にならないよう慎重に計算されている。菅野美穂の吐息芝居が妙に引っかかった点を除けば流石は月川翔。70年代から現代へと時代性を程よく表出させた見せ方も大味にならず好感。
-
-
オールド・フォックス 11 歳の選択
-
俳優
小川あん
数多くの傑作が生まれている台湾。独特の風習と生活が撮影に大きな影響をもたらすはずが……本作にはその魅力が感じられない。生と死、男と女、経済格差などの要素を扱っているが、表面から掘り下げられていない。その上、俳優の芝居もポーズになってしまっていて伝わらない。長い時間をかけてゆっくりと抉っていく人間の性を見たかった。少年の将来像がチープな演出になっていたのもがっかり。チェン・クンホウ「少年」を想う。侯孝賢は脚本に言及しなかったのかしら?
-
翻訳者、映画批評
篠儀直子
ファーストショットのあまりの見事さにいきなり度肝を抜かれ、美しい画面のテキパキした連鎖にドキドキし、帰宅したリウ・グァンティンがサックスで〈恋に落ちた時〉をしっとりと演奏しはじめるに至ってはもう身もだえしそうにたまらない。この導入部分で興奮しすぎたせいか、いまいち加速していかないかのように感じてしまったけれど、その後も充実した画面が頻出、ノスタルジックなスコアも素晴らしい。ある種のふてぶてしさをたたえた子役俳優の演技を含め、全方面において立派な仕事の映画。
-
編集者/東北芸術工科大学教授
菅付雅信
バブル期の台北の少年の成長を描くドラマ。レストランで働きながらお金を貯めて理髪店を開こうとする父を尊敬する純朴な少年が、バブル崩壊の中で「腹黒いキツネ(オールド・フォックス)」と呼ばれる地主のタフな人生哲学に惹かれていく。清貧潔白な父を支えるか、強烈な拝金主義に身を委ねるか。少年の成長譚として普遍のテーマを台湾ならではのウォームな質感で包み、丁寧なリアリズムで描く。共感する物語だが映像的面白みに欠けるのが惜しい。
-
-
HOW TO BLOW UP
-
文筆業
奈々村久生
過激な環境テロで加害企業に一矢を報いようとする者たち。緊迫感を煽るように延々と流れ続ける音楽がかえって集中力を疲弊させる。メンバーの動機は全員の個人的な怒りや悲しみに基づき、社会活動と言うには甘く、組織的な犯行としての周到さにも欠け、未熟な寄せ集め集団の幼稚な犯罪劇になっているのが悲哀を誘う。犯人が何らかの被害者である場合、首謀者が英雄になってしまうと本質がロマンチシズムにすり替わってしまうため、リーダーのドヤ顔が散らつくラストは極めて後味がよくない。
-
アダルトビデオ監督
二村ヒトシ
スーパー戦隊み、と言って不謹慎なら「七人の侍」みがあった。脚本に凝りすぎずバババッと書いちゃって撮った感じも、低予算だから撮りかたをいろいろ工夫してるのも、終わりかたも、めちゃめちゃ良い。こんな話をこんな面白い映画にされては国家権力や大企業は困っちゃうねえ。こっちとしてはアジア人を一人入れといてくれると(金持ち坊ちゃんを中国か韓国か台湾か日本からの留学生にするとか?)さらにもっと楽しめたかもと思ったけど、そこまでやらんでもいいか。とにかく面白かった!
-
映画評論家
真魚八重子
破片のような個々の人々が、ある時点で集合し力が結実して何かが起こる。それがテロリズムであることが、この計画に携わる者たちと、石油会社による環境汚染の関係性で明らかになっていく。計画はスマートで、若者たちは危険だが練りに練った計画が展開する。不毛に終わらず、過激すぎない目的を掲げた正義感に基づくテロリズム。こういったテロを描いた映画が少ないと気づかされ、個々の若者たちの役割分担が鮮やかな脚本に唸る。率先した自己犠牲など身を切る思いに揺さぶられた。
-
-
蛇の道(2024)
-
映画監督
清原惟
1998年の原作映画は男性同士の二人組だったが、今回は男と女に設定が変わっていたのが、印象を大きく変えていた。前作を観たのがかなり前なのでぼんやりとした記憶だが、残酷でありながらもその過剰さに少し笑いを覚えた気がする。しかし、今作は笑いが微塵もないシリアスな映画になっていた。人を拷問するシーンがフィクションに見えず、世界で今も起きている現実として見えてしまう自分の受け取り方の変化かもしれないが……。柴咲コウの本心が分からない魅惑的な声に惹きこまれた。
-
編集者、映画批評家
高崎俊夫
「勝手にしやがれ」シリーズを連打していた頃に見た「蛇の道」はその酷たらしいまでの暗さに驚いたが、いっぽうで、スラップスティックすれすれのガンアクションには黒沢清の真骨頂が窺えた。リメイク版もパリの市街を柴咲コウが律儀に自転車で移動する場面や廃屋のような寂れた工場での拷問シーンまでもが前作同様の低予算感覚に貫かれ妙に感心してしまった。ただし住宅街を車で周回するだけで〈不気味なもの〉を醸成させた不可知論的な恐怖をめぐっては前作に軍配が上がるのではないか。
-