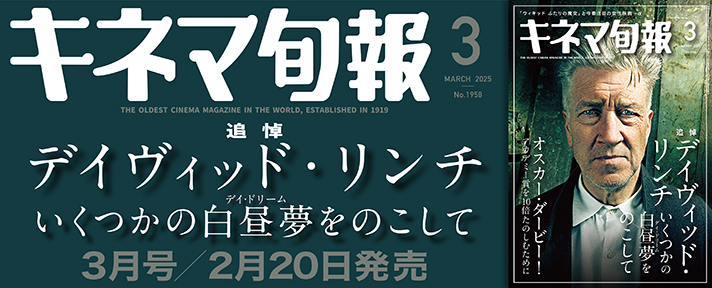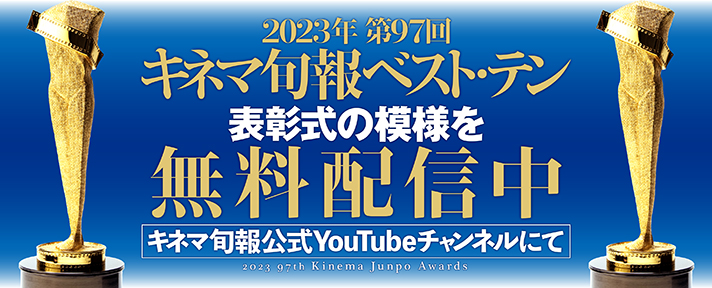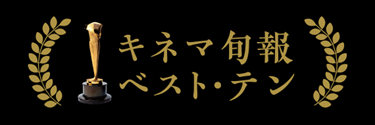ニュースNEWS
特集・評論ARTICLE
新作情報NEW RELEASE INFORMATION
週末映画ランキングMOVIE RANKING
名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)
公開: 2024年4月12日 公開 7週目猿の惑星 キングダム
公開: 2024年5月10日 公開 3週目劇場版ブルーロック EPISODE 凪
公開: 2024年4月19日 公開 6週目ゴジラ×コング 新たなる帝国
公開: 2024年4月26日 公開 5週目鬼平犯科帳 血闘
公開: 2024年5月10日 公開 3週目劇場用再編集版 ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP
公開: 2024年5月10日 公開 3週目青春18×2 君へと続く道
公開: 2024年5月3日 公開 4週目変な家
公開: 2024年3月15日 公開 11週目劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦
公開: 2024年2月16日 公開 15週目トラペジウム
公開: 2024年5月10日 公開 3週目専門家レビューREVIEW
美しき仕事
公開: 2024年5月31日-
俳優 小川あん
見る人を選ぶ。クレール・ドゥニかドニ・ラヴァンのファンか、もしくはフランス映画史を愛する人など。そうでなければ、まずこの大胆さと繊細さを楽しむことができないと思う。軍隊を中心に置く作品を「集団映画」と勝手に呼んでいるが、(例えば「フルメタル・ジャケット」とか) 総体的な意味での整列から個の乱れを描く。本作は肉体的な反応に目が向けられ、理解よりも先に生々しい感覚を獲得できる。あらすじから決して想像できないように魅せ、一筋縄ではいかないのがクレール・ドゥニ。
-
翻訳者、映画批評 篠儀直子
いまごろわたしごときが褒めてもかえって作品に失礼なんじゃないかと思えて申し訳ないのだけれど、やっぱり褒めないわけにはいかない。故郷を離れた男たちの特殊な場に監督が向ける視線や、嫉妬の研究といった面も重要だが、それ以上に、一つひとつのショットの美しさと生々しさ、およびそのつながりが生み出す生々しさ、画面から独立して機能するナレーションなど、すべてが思考と感覚を触発する。あと、すでにネットミームになってるらしいけどやっぱりドニ・ラヴァンの突然のダンスは必見。
-
編集者/東北芸術工科大学教授 菅付雅信
仏クレール・ドゥニ監督の未公開作で、アフリカのジブチにおける外人部隊の訓練の日々を描く。主人公の指揮官をカラックス作品で知られるドニ・ラヴァンが演じ、新入りの兵士との複雑な愛憎が物語の軸になる。アフリカ、外人部隊、ラヴァンといい材料が揃っているのだが、映画は極めて単調に展開する。ラヴァンならではのシーンが随所にあるが、エンディングを含めて彼の役者力に頼りすぎで脚本の詰めが甘い。退屈なポエムのような脚本を作家主義と見なすフランス作家主義映画病の典型。
告白 コンフェッション
公開: 2024年5月31日-
文筆家 和泉萌香
後味が最悪な(素晴らしい)原作でのキャラクターは日本人男性二人だったが、今回最初に「告白」をするのは韓国人男性に。あのオチがあるにしても、人外生物のような執拗なアクションに「シャイニング」的シーンなどなど、漫画ならば良いが実写だとキツいし、バタバタ動き回るせいで、せっかくの山小屋=密室という舞台も生かされていない。生田斗真とヤン・イクチュンならば、がなったり(「うるせえよ」と本人に言わせてしまっているし!)しなくとも凄みたっぷりだったはず!
-
フランス文学者 谷昌親
中盤からはホラーの色合いが強くなるが、サスペンスやミステリーの要素も盛り込んであり、山小屋の空間の使い方にも工夫が見てとれ、映画的な感興をそそる仕掛けは充分にある。ただ、おそらく密室劇にすることにこだわったからだろうが、既視感のある状況設定と人間関係があまりにも寸劇的に描かれる結果になってしまった。雪山での登山、山小屋で過ごす夜の時間の経過、そうしたなかで徐々に変化する人間関係、それらが描かれていれば、作品としての味わいが増したかもしれない。
-
映画評論家 吉田広明
山小屋での密室劇、二人しか登場人物がいないのでこれだけの上映時間になったのではあろうが、しかし掘り下げはすべきだったのでは。取り分け奈緒の人物像は通り一遍のものでしかなく、決定的な難である。この造形の浅さが、どんでん返しによる事件の真相開示を白々しいものにしている。人物造形の難は二人の一方を韓国人にした点にも現れており、韓国人だから日本人に対しコンプレックスを持っているという設定には不快なものを感じるし、そもそも現在もはや成立しないだろう。
バティモン5 望まれざる者
公開: 2024年5月24日-
文筆業 奈々村久生
移民が暮らす集合住宅の一室で人が亡くなり、大勢の手に担がれた棺が、狭い通路や階段に阻まれながら外に運び出される。その過程でこの居住区の状況や問題が一目瞭然になるだけでなく、ここに生きる人々の息づかいまで顕にしてしまう描写が素晴らしい。声をあげて行動する住人たちの力を体感させる音の使い方も効いている。これが日本だったら成り立たない絵面だと思いつつ、彼らの闘いが成功しているとも言えず、武力の応酬では誰も救われないという現実の再生産に虚しさを突きつけられる。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
同月公開の「ミセス・クルナスvsジョージ・W・ブッシュ」と同じく、人種や経済格差の前でまったく公平ではない「民主」政治や無関心な世間から、排除され、軽くあつかわれて侮辱される人々がテーマだが、こちらはそれを極めてシリアスに描く。生活に余裕のある側の(とは本当は限らないのだが)まじめな人が、自分はより良い人間であろうとして結果的に弱い人たちを傷つけるどころか、生活まで奪うことになる現実。これは資本主義が、というか人類が背負ったバグなのだろうか。
-
映画評論家 真魚八重子
団地の取り壊しの場面から始まるのは象徴的だ。そして新市長が移民や貧困層の切り捨てに急進的な姿勢を見せるのが、日本と似ている。ラジ・リは前作の「レ・ミゼラブル」ではほぼ男だけの世界を描いたが、団地に暮らすのは老若問わず女性もいる。しかし女性のアビーが指導者になるのは難しい。貧困地区が犯罪多発地域と重なる傾向があり、団地の温存もひとつの生き延びる術にすぎない。問題の解決は複数の人間で対処しなければ難しいのに、女性のアビーは一人で立ち上がるしかない。
おいしい給食 Road to イカメシ
公開: 2024年5月24日-
ライター、編集 岡本敦史
市原隼人扮する教師の「お前は最後まで手を抜かなかった」というセリフに、あんたに言いたいよ、と思った瞬間、落涙。『孤独のグルメ』の松重豊とは異なる独自の食事芝居を編み出したのは偉業である。血管の切れそうな熱演は頭の回転の速さ、身体能力の高さにも裏打ちされ、見応えがすごい。そして当たり役を得るとはすなわち全スタッフの職人技を味方につけることだとも痛感。80年代という時代設定はややあざといが、きちんと現代的テーマも盛り込み、娯楽作の在り方として優秀である。
-
映画評論家 北川れい子
そういえば昨今の急激な物価高で、給食会社の休業や給食費の値上がりがニュースになっているが、北海道の中学校が舞台の本作の時代は、バブルが崩壊するちょっと前。格別豪華な給食が出てくるわけではないが、給食を生き甲斐にしている主人公の教師が、暴走的妄想を発揮しながら食べはじめるとどれも美味しそうで、演じる市原隼人、給食のためなら見栄も外聞もなし。人は美味しく食べることを発明した唯一の生きものだ、という台詞もなるほどね。気楽に楽しめる消化のいい娯楽作。
-
映画評論家 吉田伊知郎
恥ずかしながらTVシリーズも劇場版も未見につき、未知との遭遇だったが、市原隼人のアクションに瞠目する。1コマたりともノーマルな人間の動きを見せることを拒絶し、人力VFXともいうべき体技と表情を全篇にわたってやってのける。生徒を威圧しまくる直情的な教師像も時代設定を踏まえれば違和感はない。給食が町長選に利用される話だが、大谷グローブを私物化する非常識な市長もいる現代からすれば、本作で給食に介入する町長は、程よくスパイシーな味付けとして作用する。
帰ってきた あぶない刑事
公開: 2024年5月24日-
ライター、編集 岡本敦史
自分たちが老いぼれたとはまるで思っていない主役コンビの活躍を描くというコンセプト自体は圧倒的に正しい。舘ひろしと柴田恭兵の(言い方はヘンだが)鋼鉄のように軽い芝居も、もはや至芸。問題は周囲のリアクションをどう描くかで、その相対化の欠如は今の娯楽映画とは思えない。旧キャスト陣が振り撒く不自然さを周囲の若手がほとんど指摘しない状態は、政界の忖度を見るかのようで不気味だ。とはいえ若々しさと分かりやすいオマージュで、前作の枯れた味わいとは一線を画した。
-
映画評論家 北川れい子
スタートから約40年。近年このシリーズになると館ひろしも柴田恭平もどこかタガが緩むのか、もうほとんど趣味と遊びで演じているようなノリ。シリーズ初期から二人を見ているこちらも、そんな彼らにいつしか寛大になり、ふざけ合いと、そこだけ真面目(!)なアクションが楽しめれば、わざとらしい設定やムリムリのエピソードも、勝手にどうぞのノリ。若い観客層をまったく意識しない二人の言動も、逆に潔いとも言えなくもないし。ただ演出のキレがいまいちで、途中で何度かイライラ。
-
映画評論家 吉田伊知郎
黒澤満も仙元誠三もいなくなったが、スタッフの世代交代を成功させた理想的一篇。かぶき者タカ&ユージの華麗なる老いが、BL寄りの初老ブロマンスを成立させる。銃を持てない枷を、どう潜り抜けてあぶデカになり得るかを硬軟織り交ぜた趣向で成立させたのも良い。過去のフィルムを自在に挿入してシームレスに繋げた芸当は「男はつらいよ お帰り 寅さん」と双璧。早乙女太一以外の若手は総じて影が薄いが、探偵バディものへのリブートは予想以上にうまくいっており、毎年観たくなる。
PS1 黄金の河
公開: 2024年5月17日-
映画監督 清原惟
私の知るこの世とは違う論理で動いているような映画。あまりインド映画を観たことがなく、参照もないなかで個人的な視点でしかなく申し訳ないけれど、私が映画に対して苦手だなと思うところが集合していた。アクションは肝心な部分がカット割りで処理されていておもちゃみたいな感じだし、音楽が終始鳴り続けているせいで全体として単調さが否めない。ギャグなのか真剣なのかもわからない。時代背景的に仕方ないのかもしれないけれど、女性がもの扱いされている感じもしんどさがある。
-
編集者、映画批評家 高崎俊夫
延々と読み終えることのない大河小説を一気読みさせられているような奇妙に倒錯した感覚にとらわれる。一瞬たりとも退屈させてはならぬという至上命題を遵守する語り口にあっけにとられ、ようやく3時間弱で前篇が終了。改めて作り手たちの膨大なるエネルギーに呆然となる。ふと1940年代に栄華をきわめたアレクサンダー・コルダが量産したエキゾチシズム溢れる華麗な歴史絵巻の伝統は、今や歌&ダンス&肉弾戦を繰り広げるボリウッドの大作群にしっかりと転生したのだなと実感する。
-
映画批評・編集 渡部幻
原作小説は70年間にもわたる国民的ベストセラーなのだという。タミル語による冒険映画で、ベテラン監督の職人芸で3時間近くは瞬く間に過ぎていく。歌と踊りは勿論、インディ・ジョーンズ的なアクションには、どこまでも陽気なヒーローと、非現実めいた美女が登場。運命の恋あり、友情もあるが、王位継承をめぐる各人の思惑が入り乱れる歴史の物語は複雑。しかし小説が全5巻2200ページに及ぶと知れば、映画の地面に足を着けた監督の腕を感じさせる。実は第一部で、続篇に続くとは知らずに見ていた。
ありふれた教室
公開: 2024年5月17日-
文筆業 奈々村久生
真実は我々が思うより強くない。何らかの情報をめぐって特定の人物や対象がダメージを受ける可能性のある場合、その話が本当かどうかよりも、疑惑が立ち上がった時点で負けなのだ。それは新撰組でも不穏分子の排除に用いられた手法だったし、SNSのゴシップやフェイクニュースでも同じことが言える。そして学校という社会の縮小版においても。日に日に緊張感を増す空気を作り上げた子供たちとの連携と、このゲームに勝者がいるとしたら誰なのかを問うラストカットに目を奪われる。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
ヨーロッパでも学校教員のなり手がいない問題は深刻なのかしら。どこの国でもそうなのだとしたら、それはなぜなのか。同月公開の「胸騒ぎ」では他人は何を考えているかわからずホラーなのかどうかしばらく判断に迷わされたが、こちらは「これはホラー映画ではない、というそのことが恐ろしい」じつに社会的な映画だった。観客にも主人公にも、他の登場人物が何を考えているのか、わかりすぎてしまうのが恐ろしい。結末もホラーの終わりかたではなかった。希望はほんのちょっとだけあった。
-
映画評論家 真魚八重子
流行の厭な映画の一種だ。教室や職員室で起こる盗難騒ぎ。犯人は職員の可能性も高く、主人公の女性教師カーラはPCの録画モードで犯人の腕だけを捉える。映画は意図的に建設的な方向に議論を進めない。同僚はカーラの行動に対し、他人を疑う行為が不快だと言う。特定の誰かを疑わずに犯人を捜す方法を提案するのではなく、だが問題を放置する気でないのなら、どうしても付随してくることだ。生徒たちも流され、視野狭窄的に人権問題を訴える。ラストの玉座のような演出も意図が不明。
碁盤斬り
公開: 2024年5月17日-
文筆家 和泉萌香
確かな四季のうつろいを感じさせるライティングに夜の雨の描写に音楽、もちろん、終盤に向けて(前号でのインタビューの言葉を借りるならば)「汚く」なっていく草なぎ剛はじめ役者陣の演技の、スタイリッシュに映画を支える見事なアンサンブル。終始健気な娘に用意される最終的な場所といい、やや美しくまとまりすぎているような印象の中、クライマックスのアクションシーンからの血飛沫は鮮烈。<正しいこと>の曖昧さに揺れる主人公同様、悪役の複雑な表情ももう少し見たかった。
-
フランス文学者 谷昌親
落語『柳田格之進』を基にして、格之進が浪々の身となった背景に武士同士の確執を盛り込み、時代劇らしい展開をうまく作り出している。全体に、初の時代劇に挑んだ白石和彌監督の意気込みが伝わってくるのだが、ダッチアングルや移動撮影を多用せず、もう少し腰を据えて取り組んでもよかったのではないか。さらに、草なぎ剛が演じる格之進は、囲碁の打ち方にもその実直な人柄をにじませてみごとであるものの、実直さゆえの悲劇を感じさせる人物造形にまで至っていないのがやや残念だ。
-
映画評論家 吉田広明
古典落語の題目だけあって、話は磨き込まれて堅牢、美術もしっかりした作りで、場面が変わるごとに感心させられる。俳優たちも素晴らしい。ただ、例えば居酒屋の場面で、会話している主人公たちからカメラが後退し、手前の卓の二人を舐めながら回り込んで再び主人公たちに回帰する意味のない長回し、清原が吉原の大門をくぐる場面での妙な画面効果など、小細工が目について五月蠅い。主人公をストイックに作り過ぎていささか堅苦しく、人間としての幅、魅力が感じられないのも難。
湖の女たち
公開: 2024年5月17日-
文筆家 和泉萌香
同時期に鑑賞した他作品にもあったが、他人を好きになることを半ば「決める」、周囲は理解し難い二人だけの倒錯的な関係に身を投じてみるのは現代において一番──本作の台詞を借りるなら頭がおかしい、おかしくなれる、ような──体験であるかもしれないし結構なこと。施設での殺人事件と関係者の愛欲関係という場所から出発し、戦時中の日本軍の残虐さにも話は触れるも深まりはなく、バランスを崩したまま、突如発せられる「世界は美しいか否か」の問いにはひたすら違和感があった。
-
フランス文学者 谷昌親
介護療養施設での殺人と強引な捜査があり、男女のインモラルな関係があり、それらが最終的には戦時中の731部隊にまでつながっていくという、深さと広がりのある物語が、ぎくしゃくしながらもなんとか映画に仕立てられている。逆に言うと、ぎくしゃくしているからこそ成り立つ作品なのかもしれない。集落のなかをめぐる水路を生活用水として使い、介護の合間に琵琶湖の夜明けを眺め、その琵琶湖に最後は身を投じるヒロインの佳代が、なんとも不可思議な潤いを画面にもたらしている。
-
映画評論家 吉田広明
731から相模原を経て、名を記すも筆の穢れ杉田某に至る、生産性なき者死すべし論の系譜と、これも731につながる薬害捜査を権力で握りつぶされて精神が歪んだ刑事の部下へのパワハラ、その部下の事件関係者への性強要という権力の負の連鎖。この二つの系譜の接合がいささか強引な印象はあるが、作り手の怒りはひしひしと伝わる。ただ、弱者への卑劣な性強要にしか見えない福士と松本の関係を、生産性から外れるオルタナな愛の形を提示しているとするのはかなり強弁な気がする。
ボブ・マーリー:ONE LOVE
公開: 2024年5月17日-
俳優 小川あん
レゲエとソウルが体に染みている私にとって最高の映画。偉大なミュージシャンの魂を描くときに必要とされるのは、その生き様を限られた時間のなかでどう映すか。本作ではボブ・マーリーの“笑顔”が印象付けられている。その瞬間を見逃していなかった。それだけで涙できるのだから、充分だ。ドキュメンタリー含むボブ・マーリー関連の作品はすべて良い。そう、何があろうとも世界は"one love"だから。エンドロール、彼の鼓動に合わせたリズムに自然とからだが動いてしまった。ラスタファリ!
-
翻訳者、映画批評 篠儀直子
音楽伝記映画として飛びぬけた出来というわけではないし、演奏されるマーリーの曲がほぼすべて彼本人の音源から取られている(つまり口パク)のが、「ボヘミアン・ラプソディ」あたりと違って正直上手くいっていないように見えたりするのだが、ラスタファリズムをごまかさないでちゃんと描いているあたり誠実な作りだと思う。バックステージもの好きとしては、楽曲が生まれるプロセスを描いたシーンががぜん面白い。マーリー夫妻を演じるふたりに魅力があり、ボブ以上に妻のリタに興味がわく。
-
編集者/東北芸術工科大学教授 菅付雅信
レゲエの巨人ボブ・マーリーの絶頂期を描いた音楽映画。いわばレゲエ版「ボヘミアン・ラプソディ」を狙ったと言えるが、残念なことに肝心のライブの描写が、楽曲に当て振りしているだけなので全然盛り上がらない。また群衆CG技術を多用しており、これまたCG感が強くて醒めてくる。「ボブ・マーリー/ルーツ・オブ・レジェンド」という傑作ドキュメンタリーが既に存在しているだけに悲しい。それでもマーリーの楽曲には突き動かされるものがあるので、楽曲力に星ひとつ追加。
ミッシング(2024)
公開: 2024年5月17日-
ライター、編集 岡本敦史
今や希少な「信頼できる映画作家」吉田恵輔らしい問題意識が凝縮された秀作。前作「空白」で描かれなかった部分から着想したという脚本は、ぜひその形でも観てみたかったが、それでも芯は力強く残っている。深刻な状況に巧まざる笑いを生じさせるクセも、今回ほど私憤に満ちた骨太な内容なら、もはや必要ない感も。華がありすぎることは重々承知の上で、地方在住のイマドキの母親像を演じた石原さとみの意気込みも映画の確かな熱源だ。と思ったら、森優作が見事に全部かっさらった。
-
映画評論家 北川れい子
1に石原さとみ、2に石原さとみ、3、4がなくて5も石原さとみ。という、彼女の取り憑かれたような演技が先行するヒューマンミステリーで、女優魂というと大袈裟だが、この作品の石原さとみ、ちょっとただごとではない。幼いひとり娘が突然、行方不明になってしまった母親役。吉田監督はさまざまな事件をヒントにして自らオリジナル脚本を書いているが、あくまでも母親に焦点を当てつつ、事件に群がるマスコミやネットによる誹謗中傷にも触れ、見応えがある。
-
映画評論家 吉田伊知郎
終盤まで脇目もふらずに見た。傑作の声もあろう。被害者家族と報道、ワイドショー化するマスコミを冷徹に描いた点は評価したいが、東海テレビの『さよならテレビ』を劇映画化したような、というより置き換えた感が強い。後半はフィクションへ昇華できる場だったはずだが消化不良。石原は熱演だが、ケレン味のある演出でこそ映えるタイプなので本作のようなスタイルでは一人浮いてしまう。低温の中村倫也が印象深い。着想と演出力は抜きんでているが、はぐらかされるのは「空白」同様。
クイーン・オブ・ダイヤモンド
公開: 2024年5月10日-
映画監督 清原惟
淡々とした時間の流れに身を任せているうちに、他人の人生に乗り込んでいるような感覚になった。カジノのシーンでのお金を入れていく身振りや、部屋でだらだら話している女たち、ヤシの木が燃えているところをずっと見ている時間、印象的な場面がいくつも残る。一つひとつのカットがとても長いけれど、必然を感じられるし、現実の退屈な時間ってこんな感じかも。物語の網目が張り巡らされていなくても、引きのカットばかりでも、静かに破滅的な彼女の日々の実感がここにはあると思えた。
-
編集者、映画批評家 高崎俊夫
ニナ・メンケスの新作「ブレインウォッシュ」を見ると“映画における男性の眼差し”を俎上に載せる痛烈なるフェミニストという印象を抱く。だが、ラスベガスで孤高に生きる女性ディーラーの淀んだ日常をとらえた本作は、一見ぶっきらぼうでまったくとりとめがない。極端な長回しやズームによって浮かび上がるのはヒロインの内面ですらない。たとえて言えばゲイリー・ウィノグランドが傑作写真集『女は美しい』で抽出してみせた、荒涼たるアメリカの時代精神が鮮やかに透し彫りされているのだ。
-
映画批評・編集 渡部幻
アメリカの異端児ニナ・メンケス、91年の代表作。極私的なアヴァンギャルド・スタイルで知られる女性作家の白眉は、果てしなく続く台詞なしのカジノ場面に表れる。日光を遮断した屋内に響き渡るゲームマシーンの効果音による包囲……あの麻痺感覚と人間疎外をこれほど生々しく伝えた映画もなく、終末後のような砂漠を彷徨う女性ディーラーの無表情と孤立感が言外の説得力をもって迫ってくる。アケルマンと比較できるが、やはりアメリカ、それもユダヤ系のアウトサイダーから生まれた不条理性の映像美学。
ジョン・レノン 失われた週末
公開: 2024年5月10日-
俳優 小川あん
世界的スーパースターにはさまざまな事情がある。マスメディアはそれを暴くことを試みるが、切り取ることのできない一面が存在する。恋愛事情を追いかけようとするも、愛の具体的なかたちや中身は知ることはできないのだ。メイとジョンの間に確かな愛があったことを明らかにし、失われた時間はやはり存在したことを再確認するために、一つ一つの記憶から手繰り寄せて制作したように見えた。それにしては(あえてかもしれないが)、観客と共有できる具合にポップに再構築されている。
-
翻訳者、映画批評 篠儀直子
ジョンとヨーコが別居していた期間は「失われた週末」と呼ばれているそうだが、いったい誰にとって「失われ」ていたというのか。この時期を彼と過ごした女性がみずから口を開き、さまざまな誤解を解く。ジョンの先妻も現妻もからむ複雑怪奇な関係もさることながら、ビートルズの元メンバーからM・ジャガー、D・ボウイまで登場する活気ある日々はまぶしいばかり。ジョンの人物像と愛の物語が、豊富な映像資料でテンポよく語られる。でも、悪役にされてしまったヨーコにも言い分はあるよね。
-
編集者/東北芸術工科大学教授 菅付雅信
ジョン・レノンがオノ・ヨーコと別居していた18カ月間の時期にレノンと同居していた中国系アメリカ人メイ・パンの証言で描く新たなレノン像のドキュメンタリー。彼女の赤裸々な証言で語られるレノン、マッカートニーから多くのアーティストの私生活が新鮮で、ロック史が少し塗り替えられるインパクト。貴重な証言映像、プライベート写真に加え、アニメを効果的に使った映像編集も見事。ただし、あくまでパンの視点であり彼女に都合よくまとまりすぎではと。オノ・ヨーコがこれを見たら怒り狂う予感が。
鬼平犯科帳 血闘
公開: 2024年5月10日-
ライター、編集 岡本敦史
敵役を演じた北村有起哉の素晴らしさに尽きる。何しろ声がいい。口上ではカリスマ性を迸らせるが実戦ではへっぴり腰というキャラも、主人公より目立つべからずという作劇的配慮かもしれないが、なかなか秀逸な人物造形だ。それ以外は「様式まつり」というか、心機一転の再始動にしては新味のない、型通りの長寿番組の延長に見えた。セリフを喋る俳優の口許も表情も全部映さないと気が済まない平凡な画が続くので、昔の時代劇のほうがもっと面白い撮り方をしていた気がしてならない。
-
映画評論家 北川れい子
中断はあるものの、昭和、平成と長きにわたって継続されてきたテレビ時代劇の『鬼平』シリーズ。その令和版シリーズの劇場版で、鬼平役は十代目松本幸四郎。まあね、こういうシリーズものは「あぶ刑事」にしてもそうだが、演技、展開、見せ場などにいくつもの“お約束ごと”があり、その約束ごとがあるからファンも安心して楽しめるのだが、この「鬼平」令和版、ダイイング・メッセージなどを盛り込んでいるが、テレビ時代劇の様式を律儀に守りすぎてか演技、演出も型通りなのが残念。
-
映画評論家 吉田伊知郎
前回の劇場版以来29年ぶりに「鬼平」を観たので新鮮だったが、誰が演じるというより、〈声〉によって鬼平は決まるのではないか。声が印象深い中村吉右衛門や丹波哲郎と比較しても、流石、当代幸四郎。強弱自在に発せられる声が聴き応えあり。加えて北村有起哉、柄本明の声も個性を発揮する。手堅い演出で飽きさせず見せるが、先行して放送されたTV版と同様の出来栄えで、映画館で流す意義がどこにあったか。もっともそれを言い出せば、先代の劇場版でも同じことを感じたが。
不死身ラヴァーズ
公開: 2024年5月10日-
文筆家 和泉萌香
両思いになってはその彼が消え、同じ彼が現れ、「運命の相手」と信じ込んで向日葵のような笑顔で告白しまくる主人公……という、リアリティの全てを無視した超特急の前半部分に「運命」にはピンとこなくなった自分、動悸が止まらない。その異様っぷりの正体は無事に明かされていくが、本作がスゴいのは、10代の突飛な少女のものであろう(漫画から飛び出してきたような)着色料たっぷりのキャンディのように色付けされた世界が最後まで増強され続けることである。なんだこれ!
-
フランス文学者 谷昌親
松居大悟監督の10年越しの企画ということで、熱量が感じられる作品ではある。しかし、原作の漫画とは設定を変えているものの、ファンタジー的要素のある物語を実写映画にするのはやはり力技で、その力の入りようが軋みを生じさせる。軋みを表現に昇華させる作品もないではないが、この映画は愛情讃歌を正面から描こうとしているだけに軋みは軋みのままだ。新興住宅地らしき家が並ぶ斜面が立ちふさがったり、高台のむこうに町の景色がひろがったりするロケーションは印象的だ。
-
映画評論家 吉田広明
未読だが、原作漫画は強引な展開ながら、荒削りで勢いのある画でねじ伏せてゆくのが魅力ということらしかった。一方本作は、画が粗削りというわけでもなく、また逆に洗練されることで新たな魅力が引き出されるわけでもない。画自体に強い印象がなく、そのため話自体に関心は集中するのだが、そうすると不自然な設定と強引な展開だけが悪目立ちしてくる。本作の場合、漫画の画としての表現をいかにパラフレーズするかによほど留意しなければ。原作ありきはそう簡単ではないという教訓。
胸騒ぎ
公開: 2024年5月10日-
文筆業 奈々村久生
友達の家で出された手作りのおにぎりを食べられない。あるいは親戚一同で集まったとき、他の一家のルールに触れて驚いたり拒絶反応を示す。そんな経験は誰しも心当たりがあるのではないか。これは家族という最小単位のコミュニティ間で起こる摩擦であり、自分の家が正しくて相手の家が間違っているわけでもないが、それに近い感覚を覚えてしまう。この言語化しづらくどうしようもない違和感を可視化する本作の過激な試みに、その手があったかと思う。他人の家という異文化の空間はかくも恐しい。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
外国や田舎で地獄のような目にあうホラー映画はたくさんあるが、これは前半というか3分の2までずっと具体的な恐ろしいことはおきず、ただただ嫌な胸騒ぎと自己嫌悪(しかも主人公の自己嫌悪が観客に伝染する)が延々と続いて、すばらしい。本当に気分が悪く、ラスト近くでやっとホラーになってくれてむしろ安心した。終わりかたがまた絶望的なのだが、この絶望ってきっと聖書についての知識があると、もっと絶望的で、もっと呆然とできるんだろうな。いつか牧師さんの知り合いに訊いてみよう。
-
映画評論家 真魚八重子
こういった生理的な不快感を呼び起こすスリラーも、随分流行が続いている。本作は早くもリメイクが制作中で、かなりどす黒い好奇心を刺激するのだろう。“断り切れない気の弱さ”は、誰しも経験があるだろうし、脚本もその流れをうまく作っている。話が気になって、技術面の注視は忘れるほどだった。ただ、この悪意ある人々の労の取り方は、厭な映画を作ることが目的過ぎて、現実味が乏しく不自然だ。そして動体視力の良い人なら視認できる残酷な幼児虐待カットもあり、嫌悪感を覚える。
人間の境界
公開: 2024年5月3日-
映画監督 清原惟
モノクロで描かれる夜、メガネの輪郭だけが闇の中で光るさまが印象に残った。一見何が起きているのか掴みにくい映像が内容と強く呼応する。難民の中にもウクライナのように優遇される人々と、肌の色によって冷遇される人々がいるという現実を突きつけられ、今まさにパレスチナに対して起きていることを思い苦しくなった。正義だと思われていたヨーロッパに対しての問題提起がなされていること、それがさまざまな立場の人間による複数の視点によって支えられているところに心を動かされた。
-
編集者、映画批評家 高崎俊夫
内戦を生き延び、難民としてヨーロッパへ辿り着いた6人のシリア人家族を容赦なく見舞う地獄めぐりのような苛烈なドラマだ。原題は「緑の国境」だが、峻厳なモノクロ映像は数多の難民がポーランドとベラルーシの境界上に張り巡らされた鉄条網で深手を負い、命を失う光景を鮮烈に刻み込む。アンジェイ・ワイダの衣鉢を継ぐホランド監督は難民のみならず、国境警備隊の青年、中年の女性活動家と視点を分散させた語り口によって、単なる告発調に陥らない切迫したリアルさを獲得している。
-
映画批評・編集 渡部幻
時は2021年10月のヨーロッパ。22年2月のウクライナ戦争前夜。2014年からのベラルーシ難民はポーランド国境警備隊による非人道的な扱いでベラルーシに押し返され、国境の原生林で約3万人が死んだ。一方、ポーランドが受け入れたウクライナ難民は最初の2週間で約200万人。違いは、前者がベラルーシがヨーロッパ国境を混乱させるべく“人間兵器”として利用した難民であったことであり、中東やアフリカを出自とする彼らの肌の色だった。フィクション映画の力を見せつける名匠ホランドの重要作。
ミセス・クルナス vs. ジョージ・W・ブッシュ
公開: 2024年5月3日-
文筆業 奈々村久生
いつ帰ってくるのか、帰ってこられるのかどうかもわからない不在の長男を待つ拠り所のなさを、メルテム・カプタンの演じる肝っ玉母さんの強烈なキャラクターで強引に押し切る。その原動力が無条件の母性というものにフルベットしていて、劇中の訴訟でもそれを最大の武器として民意に訴えているのがしんどい。彼女にはラビエというファーストネームがあるのだが、邦題では「ミセス」と改訳されているのも、人間であることより母であることが存在意義のすべてとされているようでつらい。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
息子が突然いなくなった母。息子は自分の意志で帰ってこないのではなく、遠い外国で幽閉されてしまったのだ。しかもドイツの友好国であるはずのアメリカの兵隊から拷問をされている。ほんとうにひどいことが世界中でおきている(こういう外国映画を観て「日本はまだマシ」とは言いたくない)。だけどこっちに元気があるうちはジタバタはしてみるものです。がんばるおっ母さんとマジメな弁護士のユーモラスな凸凹コンビの姿を見ているだけで、笑うべきところじゃなくても笑みがこぼれてしまう。
-
映画評論家 真魚八重子
クルナス夫人のように陽気でふくよかで、華やかな女性はいる。政治にうとくても収監された息子の解放のため、奔走するイメージそのものの外貌だ。その明るさと経過する日数の乖離が恐ろしい。役所の書類はなぜか読みづらい文章で書かれていて、意味を解するのが難しいのはどこも同じか。それがさらに複数の言語にわたってしまうと、絶望的な気持ちになる。本作も人権派弁護士のおかげで理解できるが、被監禁者がどういう理由で、なぜたらい回しにされるのか、根本的なところが知りたい。
殺人鬼の存在証明
公開: 2024年5月3日-
俳優 小川あん
かなりウェルメイドに作られている。時代を交錯させ、章ごとの展開が事件を複雑化させる。徐々に加害者と被害者の周囲をめぐる人間関係が露呈し、一連を見届けた鑑賞者がきちんと納得できるように事件は帰結する。それゆえに、少しちゃんとしました感が強い。この人がこうなって、これとこれが繋がってといった、人物相関図を作りたくなるような映画。そうなると「なるほど。よくできたクライム・サスペンスとして、最後まで飽きずに見終えました!」と発展が難しくなってしまう。
-
翻訳者、映画批評 篠儀直子
2021年のロシアの映画製作がどういう状況だったかはわからないが、古今東西のさまざまな映画をきちんと学んだ人が撮った作品という印象(ちなみに監督はジョージアとウクライナにルーツがある人らしい)。手のこんだ構成とこだわりの映像で、いつの間にやらぐいぐい引きこまれる。これと同様に実際の事件に想を得たポン・ジュノの「殺人の追憶」もそうだったが、捜査と並行して警察組織の堕落が描かれる趣向で、ソ連時代が舞台とはいえ、権力こそが狂っているのだという痛烈なメッセージが。
-
編集者/東北芸術工科大学教授 菅付雅信
旧ソビエト連邦での52名を殺害した連続殺人鬼をモチーフにしたサイコスリラー。熱血捜査官が容疑者を逮捕したところですべてが解決したかと思いきや事態は思わぬ展開を見せる。監督したラド・クヴァタニアはCFやカニエ・ウェストのMVなども手掛けるだけに技巧派で、凝った編集もあり最後まで飽きさせないが、策士策に溺れるならぬ技巧派技に溺れる的なトゥーマッチ感。画作りと技巧性ではフィンチャーを想起させるが、フィンチャーのような洒落っ気はなく、ロシア的鈍重さが画面からのしかかる。
青春18×2 君へと続く道
公開: 2024年5月3日-
ライター、編集 岡本敦史
おお、チョン・モンホン作品のスターたちが長野県松本ロケで共演している、という感慨はあった。しかし、本格的な日台合作の青春映画という試みの面白さに、作品自体は届いていない。こういうベタな青春ドラマをただ新味なく撮っても、タイのGDHなどには全然敵わないし、今の観客に届けるための戦略を感じさせてほしい。特に回想パート。甘酸っぱさと気恥ずかしさは同義ではない。ただ、乗り鉄的には見どころが多く、クライマックスの舞台は大いに納得。そりゃ絵になるもの、只見線。
-
映画評論家 北川れい子
そういえば劇中、岩井俊二監督の映画が好きだ、という台詞があるが、台湾と日本を舞台にしたこのラブストーリーの人物や行動、エピソードも多分に岩井俊二的で、「新聞記者」「最後まで行く」の藤井道人監督・脚本にしては、これまでになく軽やか。ひょんなことから台湾のカラオケ店に住み込みで働きだした日本娘アミと、アミに恋した18歳の僕。18年後、人生の岐路にたった僕はアミに会うため日本へ。台湾と日本のどちらにも配慮した脚本は、みんないい人ばかりだが。
-
映画評論家 吉田伊知郎
清原果耶のベストアクトというべき魅力が引き出されており、その一点押しで評価したいが、ここは点を辛く。岩井俊二の「Love Letter」が劇中へ引用されており、物語もその影響下にあるが、それなら引用元を上回る要素がひとつでも必要なのではないか。日本各地で良い人と出会い、短時間で別れを繰り返すだけなので「幸福の黄色いハンカチ」の健さんみたいな行くに行けない焦燥がない。福島が大きな位置を占め、過去と向き合う物語なのに、震災や原発も透明化されている。
正義の行方(2024)
公開: 2024年4月27日-
文筆家 和泉萌香
サスペンスドラマが始まるぞ、というくらいにスタイリッシュなオープニングだが、これから語られ問われてゆくのは女の子ふたりが殺され、犯人とされた男性が、最高裁で確定してから二年あまりで死刑になった実際の事件のこと。監督が聞き出す事件の当事者たちの言葉の数々はすさまじく、日本の死刑制度と、現在進行形でおこっている暗澹とした現実にも思いを伸ばすとともに、生身の人間の顔を映し刻みつけることの重さと<パワー>を持っているのが映画であると改めて震えた。
-
フランス文学者 谷昌親
犯人とされた男にはすでに異例の早さで死刑が執行され、真相は永遠にわかりようがないが、粘り強く丹念な取材によって殺人事件の輪郭をみごとに浮き彫りにしていて、ルポルタージュとして観るなら、圧倒的なすばらしさだ。それぞれの立場からの証言や主張が交錯するさまはスリリングであると同時に、人間が抱える闇や社会のひずみをあぶりだしている。しかし、映画作品として観る場合、関係者たちのひとりひとりが過ごした事件からの30年あまりの時間の手ざわりがほしいように思う。
-
映画評論家 吉田広明
死刑が執行されるまでの経緯、再審請求する弁護士、捜査の問題点や自身の報道姿勢について検証する新聞の三段構え、重厚な作りで見ごたえがある。弁護士や新聞の検証で、警察の見込み捜査、状況証拠の弱さなどの疑義が明らかになってくる。問題なのはそれに乗っかった新聞の報道であり、間違いを認めようとしない司法なのだが、新聞は自己検証した、では司法は?というのが本作最大の問いだ。日本の正義の女神像は目かくしをせず、右顧左眄して判決を下すという言葉が核心を突く。
システム・クラッシャー
公開: 2024年4月27日-
映画監督 清原惟
児童養護施設を転々としている、問題を抱える子を丁寧に取材して制作したという経緯がひしひしと伝わってくる。なにより、主人公の女の子を演じた俳優の演技と演出が力強い。破滅的になりたいわけではないのに、そうなってしまうこと。とんでもなく破天荒で衝動的で暴力性の高い子の役を、こんなにもリアリティを持って演じられることもすごいし、彼女の弱さや、周りと同じようにできないが故の魅力も表現されていた。衣裳として主人公が着ている服の鮮やかさがいつまでも目に残る。
-
編集者、映画批評家 高崎俊夫
不敵な面構えの9歳の少女にとって世界とは“根源的な違和”の集積にすぎないのだろうか。幼少期に父親から受けたトラウマというとりあえずのアリバイをもかなぐり捨て、理不尽なる怒りに突き動かされ、彼女はあらゆる支援施設からの遁走を試みる。自然に抱かれた隔離療法のトレーナーとの束の間の牧歌的な時間さえ、自らぶち壊してしまう異様なまでの破壊への意志はどこから生じたのか。かつてトリュフォーや浦山桐郎が切実な想いを込めて描いた“不良少年”“非行少女”の残像すらここにはない。
-
映画批評・編集 渡部幻
金髪にピンクの服。愛嬌もあるが、瞳の奥に猛烈な怒りと無理解への憎悪が滲んでる。9歳の少女役のヘレナ・ツェンゲルの演技力が驚異的で、母親の愛を求める少女の暴発は凄まじい。受け入れ先の施設もなくなってきていて、暴れるたびに母親との生活から遠ざかる。だから少女は逃げる。疾走の映像が美しい。しかし一体どこへ? やはり9歳の少年を描いた「かいじゅうたちのいるところ」を思い出させたが、このドイツ人女性監督が少女に寄せた共感、パンキッシュなエネルギーと解放感は他に比すものがない。
エドガルド・モルターラ ある少年の数奇な運命
公開: 2024年4月26日-
文筆業 奈々村久生
持って生まれたものよりも育つ環境が人を作る。その可能性と残酷さ。社会や政治の時勢に利用される宗教の力と脆さ。ベロッキオには無駄がない。必要最低限のカット。無駄がなさすぎて、映画が終わった瞬間に潔くシャッターを降ろされるような問答無用感がある。ユダヤ教とキリスト教の関係やローマ教皇の影響下における信仰については、その背景のもとに育っていなければおそらく完全には理解し得ないが、これがたとえ新興宗教だとしても原理は同じであることが事の重さを突きつける。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
人間にとっていちばん大事なのは心の自由だと思うのだが、しかし心が自由であることなんて人間に可能なのかとも思う。なにかに洗脳されていなかったら人は人間になれないのではないか。暴力で連れ去られ、親が信じているのとは別の、こう生きたほうが幸せになれるという生きかたを教えこまれる。そういう宗教と宗教の戦い、倫理と別の倫理の争いに巻き込まれることを人間はずっとやってきたのか。この映画で語られているとても大きな歴史の問題は、僕にはどう捉えていいのかわからない。
-
映画評論家 真魚八重子
エドガルドは母との別れで泣くような感情も見せるが、基本的には言われるがまま動く人間だ。ユダヤ人でありつつ、派手な教皇に対しスターへの憧れの眼差しを向ける。二つの生きる道の岐路に立つ彼が、同時に引率者を亡くすと空っぽになり、この数奇な運命は彼には重すぎてむごい。壁がアップになるとき、それは必ず向こう側から打ち壊されるためだという、映画のお約束にスカッとする。またエドガルドが磔刑に処されたキリスト像のくさびを抜くシーンも、心が射られた思いがした。
悪は存在しない
公開: 2024年4月26日-
文筆家 和泉萌香
空の道から地の道へ、映画は道を途切れさせ、男は斧を振りかざし薪を割り、車は無邪気に遊ぶ子供たちへと接近し、音楽はぶち切られ、切断から切断へ……。不穏さを際立たせる音の数々と、真っ白な雪の厳かな美しさ、やや露骨に感じられるくらいのカメラワークが織りなす濃密さは、やっぱり外から遮断された映画館で見なくては。印象は真逆ながら、同じタイミングで鑑賞した「辰巳」で発せられるセリフ──男の性=セックスと暴力、殺しに関する──が思わず響いた。
-
フランス文学者 谷昌親
「ハッピーアワー」で組んだスタッフやキャストが複数参加しているだけに、「ドライブ・マイ・カー」以上に濱口竜介監督らしい作品と言えるかもしれない。主人公の巧を演じる大美賀均はもともとスタッフで、台詞まわしもぎこちなく感じられるが、終わってみれば、まさに巧という人物以外のなにものでもない。森のなかを人が歩き、水を汲み、薪を割る、ただそれだけで画面が活気づく。鳥のさえずり、風やせせらぎの音、それらにかぶさるように流れてくる石橋英子の音楽も印象的だ。
-
映画評論家 吉田広明
山間地にリゾート建設を図る企業、形だけの説明会でお茶を濁すはずが、担当者が地元住人に感化される。神宮再開発を連想させる問題提起にも、「偶然と想像」につながるコメディにも見える作品。車の中での長い会話が事態を転回させる点も監督らしい。冒頭の長い移動など、音楽家のライブ用映像の名残だろうが、映画としてあれは要るのかなど疑問は残る。みんな悪い人間ではないという意味で「悪は存在しない」が、地元民に「悪意」がないわけではないというズレが露わになる衝撃。
青春(2023)
公開: 2024年4月20日-
映画監督 清原惟
中国の個人経営の縫製工場に勤める人々のドキュメンタリー。住居と職場が同じ集合住宅内にあるということもあって、仕事と生活が渾然一体となっている。皆とても仲がよさそうで、まるで家族のように暮らし仕事をしている。部屋もほとんどが相部屋で、働いている時間以外も一緒に食事をしたり音楽を聴いたりして、仕事の賃上げの交渉も一丸となってやっている様子に、人々のコミュニティのあり方について考えされられたし、自分もその中に暮らしているかのように時間を過ごした。
-
編集者、映画批評家 高崎俊夫
ワン・ビンが描く長江のデルタ地域にある小さな町の衣料品工場で働く農村出身の若者たちの初々しい青春群像を見ていると、“変われば変わるほど同じだ”と呟きたくなる。日本の不動産を買い漁る富裕層の対極にある彼らこそが中国経済を深層で下支えしているのだ。さらに中国の都市部との途方もない格差構造がじわりと滲み出す。同じ20代の経営者との賃上げをめぐる攻防。いくつものカップルたちが織りなすたわいない戯れ言や親密な触れ合い、寄る辺なさまでが怜悧な視点で切り取られている。
-
映画批評・編集 渡部幻
ワン・ビンは中国経済の一翼を担う長江デルタ地域の出稼ぎ労働者たちの特異な環境を捉え、文字では到底伝わらないだろう生活臭を充満させる。灰色の衣料品工場にミシン。灰色の空、灰色の生活、室内も室外もゴミだらけだ。カメラは若者たちを追う。みんなタバコを吸い、カップ麺を食べる。会話の中心は恋、妊娠、結婚、そして賃上げの交渉。肉体的な距離が密接で、やたらにじゃれ合う。ぼくに身近な20世紀後半の日本を思い出したが、彼らの手にはスマホが握られている。これもまた“21世紀の青春”なのだ。
辰巳
公開: 2024年4月20日-
文筆家 和泉萌香
歯車の部品が転がった、車のはらわたもはみ出る整備工場で、文字通り彼彼女らの体液も飛び散り絡み合い、肌のきめもすべて太陽にあぶり出され、暴力から発せられる汚い言葉が飛び交う。感傷や愛情にからめとられることなく、?き出し(になりすぎるくらい)のエネルギーをみなぎらせたまま、そのエネルギーのままに動き続け、穏やかではないカメラもここは、と揺るぎなくとらえるふたりの顔。血みどろのはて、海や草むらと同様にさらされる、人間の肌が湛える確かな美しさを喚起する。力作。
-
フランス文学者 谷昌親
日本映画には珍しいハードなノワール物だ。水辺の街の無機質さが人物たちの非情な生き方に重なり、陰影のある独特の虚構世界が作り上げられている。物語としては、「レオン」の日本版といった感じだが、少女の年齢が高いこともあり、ただ守ってもらうだけの存在でないあたりもおもしろい。自主制作でジャンル物を手がけ、しかもこの完成度になるということに驚かされるが、すぐれたジャンル映画を参考にしつつ、自分の求める世界を妥協せずに追求できたということなのかもしれない。
-
映画評論家 吉田広明
やくざの上前をはねた金を巡り、巻き込まれて死んだ姉の仇を撃とうとする妹に、同じやくざの一員で死んだ姉の元彼であった男が協力するという構図。主人公の男は自分が主体的に動くというより、受動的に引きずられるわけだが、その理由はあくまで情動であるという点に本作をノワールとする根拠はあるだろう。姉の断末魔の長い場面の痛ましさ、殺しが快感になるという職業犯罪者に対し、殺す度に吐く妹の姿が、死の重さを感じさせるだけに、主人公の情動は説得的になっている。
マンティコア 怪物
公開: 2024年4月19日-
文筆業 奈々村久生
群青いろの新作「雨降って、ジ・エンド。」との相似が妙に腑に落ちる。カルロス・ベルムト監督ならではのトリッキーな作劇と抑制された語り口が効いていて、リアリズムではセンシティブになりすぎそうなところを絶妙なバランスで「表現」にスライドさせている。フィクションの矜持がうかがえるようなラストも見事。同じビターズ・エンド配給で昨年公開された「正欲」もテーマ的には同系譜に属しており、この題材は繰り返し描かれることによって、今後タブーから議論の対象になっていくと思う。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
オタク男の妄想のモンスターがAIの暴走で実体化して悪さするホラーかと思ったら、そんな昔よくあった差別的な話じゃなくて、もっと地味な、つらい恋愛譚だった。異常な(って言いかたを僕はしたくないのだが)欲望をもってしまった者はどうやって幸せになればいいのか。日本の「怪物」は結果的にポリコレの人も反ポリコレの人もそれぞれが考えねばならないことを考えざるをえない映画になったわけだが、こっちの怪物にはできれば一生考えたくなかったことまで深く考えさせられてしまった。
-
映画評論家 真魚八重子
本作は主人公のとある秘密を隠して物語が進む。その核心に触れないように、話はずっと本題を避けた無駄話が続く。意図はわかるが、そのギミックに付き合わされる観客はたまったものではない。ある種の性的嗜好を持つ人々は、一生その欲望を経験できずに、妄想のままで終わらせなければならない。欲望を行動に移せば犯罪となり、その対象者に大きなトラウマを与えてしまう。それは確かに哀れであるが、もう一人の重要人物もいびつな共依存の欲望の持ち主で、ラストまで気持ち悪い。
異人たち
公開: 2024年4月19日-
文筆業 奈々村久生
主人公の内面世界と現実世界が渾然とした世界観。限られた登場人物と視点がその描写を可能にする。他者との関わりの少なさは自己の肥大を許し、それを妄想と呼ぶのは簡単だが、敢えてネタバレ前提で言うと(以下閲覧注意)「シックス・センス」のシステムをあくまでもドラマとして描いたのが大林宣彦版ともシャマランとも異なるところで、原作のエッセンスに近いかもしれない。愛の儚さと不確かさ、それにともなう孤独はヘイ監督のテーマでもあり、この世ならざる存在とは相性がよかったといえる。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
最初ずいぶんスティーヴン・キングみがあるなと思ってたら劇中で言及されてた。〈甘える〉という魂に必要なことを人は大人になったらどこですればいいのさ。さみしさを癒そうとセックスすればするほどさみしくなるし、親と(その親が死んでても生きてても)コミュニケーションなんかしようものなら、ますますさみしくなる。自分は生きてると思ってる我々の営みはすべて、すでに死せる人たちが見ている夢なのだからさみしくてあたりまえだ。大林宣彦版に出た俳優さんたちはもうご覧になったかな。
-
映画評論家 真魚八重子
夕暮れのタワーマンションから見える、ロンドンの星々のような灯りの輝き。美しいと死にたくなる。大林の「異人たちとの夏」は、亡くなった両親が生きている息子の精気を吸い取るような奇妙な話だったが、本作は整頓されている。マンションに二人しか住人がおらず、クィアで美形なため惹かれあうのもわかるが、本作は薬物と強い酒が悲しく付きまとう。孤立したマンションで、訪ねるのも迎え入れるのも遅すぎた。クライマックスのトランス状態で時間が経過するのが上手い処理。
あまろっく
公開: 2024年4月19日-
文筆家 和泉萌香
還暦すぎの男性に自分からプロポーズ(!!)して結婚した美女(つっこみが追いつかないが)……。不器用な独身女と、いまどき「良妻でありたいわ」なんていう若い既婚の女ふたりのキャラクター像に最初うんざりしたが、彼女が「どうしても家族が欲しい」という意思を終始、曇りない笑みで突き通してしまう姿には、思わず頭が下がります。だがありえない設定に盛り込んだ幾つかのエピソードの生々しさが、家族三人白鳥ボートに乗るような、微笑ましいギャグを薄めてしまっている。
-
フランス文学者 谷昌親
尼崎という土地にこだわり、コメディの風味をたっぷり盛り込んだ人情ドラマ、とでも言えばいいだろうか。しかし、ロケーションを活かすというのは、その土地らしい場所で撮影するということではないはずだ。シチュエーションコメディ的な側面のある映画だけに、やや無理のある設定をどう観客に受け入れてもらうかもだいじになってくるわけで、だからこそヒロインの人生を少女時代から描くのだろうが、そのわりには現在と過去のつながりが有機的に感じられないままなのも残念だ。
-
映画評論家 吉田広明
いきなりリストラされたエリート女子と、家族団欒を知らずそれに憧れていた女子が、多幸的老年を鎹として「赤の他人」から本当の家族になるまで。詰まらないわけではないし、血ではなく心情でつながる「家族」という主題の重要性も分かる。しかし、事態の転換点となる場面でのスローの使用はいかにも格好悪いし、いくらやりやすくなったからと言って意味のないドローン撮影も、時間経過、あるいは人物が内向する場面の緩さを音楽でごまかすのも勘弁してほしい(この点、本作に限らず)。
陰陽師0
公開: 2024年4月19日-
ライター、編集 岡本敦史
佐藤嗣麻子監督といえば夢枕獏と谷口ジローのコミック版『神々の山嶺』誕生のきっかけを作った功労者として有名だが、ついに念願かなって「陰陽師」を監督! まずはめでたい。若手キャストを起用し、原作にないエピソード0にするという企画も、狙いとしてはアリである。ただ、作品の根幹たる安倍晴明&源博雅コンビ=山﨑賢人&染谷将太のカップリングに意外とケミストリーが感じられないのは残念。脇を固めるベテラン俳優陣の充実にばかり目が奪われるのは、ちょっともったいない。
-
映画評論家 北川れい子
能楽師の野村萬斎が安倍晴明を演じた「陰陽師」シリーズとは一線を画す、青春映画仕立てにしているのが親しみやすい。若き晴明は、平安朝の慣習や陰陽師なる役職から距離をおき、染まらず流されず合理的に行動、人の心の闇がもたらす不可解な現象や事件に冷静に対処する。という晴明のキャラクターを明確にした上で、佐藤監督は幻視や夢の映像を鮮烈に演出、目が覚めるような華麗な場面も。人物それぞれの立場の野心や思惑も痛快だ。美術や衣裳も見応えがある。
-
映画評論家 吉田伊知郎
以前のシリーズには全く乗れなかったが、さすがに原作への愛着とミステリとVFXに通じる佐藤監督だけあって魅せる。「ヤング・シャーロック ピラミッドの謎」よろしく、若き日の安倍晴明が陰陽師になるための学校に通い、ワトソン役の源博雅と出会って事件に挑むという設定からして愉しい。山﨑、染谷の好演は予想通りだが、帝役の板垣李光人が浮世離れした存在感で目を引く。終盤はVFX頼りになってしまい、そのスケールに予算が追いついていない感が溢れるのが惜しまれる。
プリシラ(2023)
公開: 2024年4月12日-
俳優 小川あん
エルヴィス・プレスリーと初妻プリシラの出会い・結婚・離別までを描く。時系列どおりのノーマルな物語構成。特筆すべきシーンはないのだが、S・コッポラの得意なガールズ・ムービーとしての画作りは深まっている。プリシラの少女性と同時にエルヴィスの少年性が見えたのは新たな発見だった。二人の恋路を眺めていると、エルヴィスに恋をしたような気持ちにさせてくれる。ただ、個人的にバズ・ラーマン監督作「エルヴィス」が前に出てしまったので、本作の印象が少し薄くなってしまった。
-
翻訳者、映画批評 篠儀直子
少女プリシラが飛びこむ状況の異様さは傍から見れば一目瞭然。最初は夢見心地でも、王子様だったエルヴィスはやがて精神的な不安定さゆえに支配欲をむき出しに。女性の自立や尊厳がまだほとんど問題にすらされていなかった時代、彼女はファーストショットで示されたように、自分の足でしっかりと歩けるようになるのだろうか?という話に着地するはずだと思うのだが、最終的にふわっとしてしまうのは、まあソフィアのよさでもあるのだろう。プレスリーの曲がほぼ流れないのも興味深い。
-
編集者/東北芸術工科大学教授 菅付雅信
エルヴィス・プレスリーの元妻プリシラのエルヴィスとの日々を彼女の回顧録をもとにソフィア・コッポラが映画化。保守的な家庭で育った少女プリシラが偶然エルヴィスと出会い、求愛を受けて結婚しスーパースターの華美な館で「籠の中の鳥」のような日々を送る。映画はプリシラの視点で作られ、彼女の「物質的に満たされた空虚さ」を執拗なディテール描写で描く。ソフィア十八番の「お姫様の憂鬱」話だが、もうソフィアの憂鬱ゴッコにうんざり。この空虚さから脱しないと映画作家としてヤバいのでは。
No.10
公開: 2024年4月12日-
映画監督 清原惟
始めと終わりで全く別の映画のように、悪夢のようにさまざまなジャンルを横断していく。とある舞台の座組みの中で起きているドロドロした人間関係の話だと思って観ていると、途中からサスペンスのような雰囲気になり、と思えば最後は異星人SFものになっていた。しかし、すべてに冗談めいた空気があるからか、ジャンルの移り変わりをすんなり受け入れて観られたのが奇妙だった。スケールの大きな話なのにも拘らず、登場人物が最初からあまり変わらず、どこかスモールワールド的な雰囲気も。
-
編集者、映画批評家 高崎俊夫
主人公の舞台俳優と共演者の女優の不倫が発覚し、嫉妬に駆られた演出家である夫が権力を笠に理不尽な報復に出る。前半は至極ありふれた三角関係の行方をサスペンスたっぷりに魅せるが、にもかかわらず、〈監視者〉を介在させつつ意味ありげ、かつ思わせぶりな不条理劇風の演出を施している狙いは奈辺にありや。などと訝しんでいるうちに不意打ちのように訪れる奇想に満ちた展開に?然となる。その壮大なる野心をあっぱれと称賛するか虚仮威しと断ずるかで評価が割れようが、私は後者。
-
映画批評・編集 渡部幻
オランダの変わり種ヴァーメルダムに日本公開された作品は少ないが、71歳のベテラン。「ボーグマン」もかなり風変わりな映画だったが、この新作もそう。幼少期の記憶を持たない役者の物語。田舎劇団に所属し、監督の妻と不倫しているが、悪い人間ではない。アート映画風に淡々と進行、オフビートな喜劇のようだが、面白くなりそうな気配はない。しかし時折、彼を監視するビデオカメラの視点が挿入され……プレスにネタバレ禁止が記されていたが、実際知らない方がよい。監督は観客を信用しているのだ。
氷室蓮司
公開: 2024年4月12日-
ライター、編集 岡本敦史
破格の長期シリーズOV「日本統一」のスピンオフ。台湾ロケを敢行し、誘拐と爆弾テロと復讐劇をミックスした欲張りなドラマが展開するが、節約第一のOVテイストは健在。チープでけっこう、でも悪ふざけはしないという独特の美学は、作り手と常連客の信頼関係ありきのものなので、一見客には敷居の高い世界ではある。大陸におもねる経済ヤクザが登場したり、ひまわり学生運動がキーポイントになったり、独立系ならではの踏み込み方が面白い。80年代末の韓国にもこんな映画あった気が。
-
映画評論家 北川れい子
かつて一般向けの日本映画に背を向けるようにして、任?に生きる男たちやヤクザ世界の抗争などを描き、一部ファンに熱く支持されたVシネマ。当時とは世間も状況も激変したが、本作がその路線で踏ん張っていることに少なからず感心する。しかも今回はドラマ化もされている「日本統一」シリーズ10周年記念作品で舞台は台湾、チラッと台湾の歴史に触れたりも。日本統一を目指す侠和会のナンバー2、氷室の捨て身の父性愛で、話はいささか乱暴だが、それもVシネらしい。
-
映画評論家 吉田伊知郎
ひたすら本宮泰風を愛でてしまう。低温ながら俊敏な動きが際立ち、スター映画の残り香を漂わせる。「日本統一」シリーズが未見でも問題ない作りになっており、台湾を舞台に父子の物語へと拡張させても大味になることなく、ウエットにもならない。爆弾魔の話でありながら合成丸出しの爆発ばかりなのは不満だが、小気味良いアクションを積み重ねて終盤へなだれ込む手堅い演出は好調。東映系のシネコンチェーンで公開されるので、往年のプログラムピクチャーの味わいを愉しむのも一興。
ミルクの中のイワナ
公開: 2024年4月5日-
ライター、編集 岡本敦史
イワナについてのドキュメンタリーと聞いて、ネイチャー番組的なものを想像すると、意外なギャップに驚く。研究者、漁協参事、料理店の主人といった人々のインタビューを通して、イワナを取り巻く現状を多角的に描いていく内容が興味深い。環境問題全体にも関わる多くの示唆も与えてくれるが、だとしても、肝心のイワナの映像が少なすぎる。人間ばかり映しすぎ。鳴りっぱなしの音楽も、スローモーションの美しい映像(それもやっぱり人間主体)も、作品に必要だったかというと疑問。
-
映画評論家 北川れい子
タイトルに使われている言葉の意味を、このドキュメンタリーで初めて知ったのだが、独特な進化を遂げたという渓流魚・イワナのルーツやその現状を記録した本作、実に面白く観た。タイトルにピッタリの知的な詩情とロマンがあり、渓流の流れや水中映像がまた美しい。そしてイワナほかの渓流魚について、さまざまに語る研究者や専門家の方々の、穏やかで分かりやすい言葉。切り口を変えた章仕立ての進行も効果的。ダムには“魚道”があることも今回初めて知った。
-
映画評論家 吉田伊知郎
釣りにもイワナにも興味がない身としては、釣りキチの綺麗事ではないかと斜めに構えて観始めたが、食と生命を真摯に考える人たちの語りに引き込まれていく。大量に釣ってから川へ戻して生態系を維持しましょうなどと言うのは勝手な屁理屈にしか思えなかったが、そうした疑問にも答えてくれる。獲り過ぎて翌日になると魚がいなくなっていた経験を語る宮沢和史が、それを大量殺戮、沖縄地上戦のようと形容することに驚くが、決して大げさではないことがわかるようになっている。
スケジュールSCHEDULE
 映画公開スケジュール
映画公開スケジュール
- 2024年5月24日 公開予定
-
帰ってきた あぶない刑事
1986年にスタートしたTVドラマ『あぶない刑事』の劇場版が8年ぶりに復活。刑事を引退しニュージーランドで探偵事務所を立ち上げたタカ&ユージ。再び横浜に戻り探偵を始めた彼らの前に、依頼人第一号として現れたのは2人にとって旧知の女性・夏子の娘だった。舘ひろし、柴田恭兵、浅野温子、仲村トオル、ベンガル、長谷部香苗といったお馴染みのメンバーに加え、「マッチング」の土屋太鳳、「孤狼の血 LEVEL2」の西野七瀬が参加。監督はWOWWOWドラマ『ウツボラ』の原廣利。 -
劇場版 ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉
競走馬を擬人化したウマ娘を育成するゲームを中心に多ジャンル展開する『ウマ娘 プリティーダービー』シリーズのアニメ劇場版。走りで最強を目指すジャングルポケットは、トゥインクル・シリーズでのフジキセキの走りに衝撃を受け、レースの世界に飛び込む。監督は、『雪ほどきし二藍』の山本健。ジャングルポケット役の藤本侑里、アグネスタキオン役の上坂すみれ、マンハッタンカフェ役の小倉唯が続投。新キャラクター、ダンツフレームの声を『舞台「ウマ娘 プリティーダービー」~Sprinters’Story~』に出演した福嶋晴菜が担当する。 -
冗談じゃないよ
30歳目前の若手俳優が現実と理想の狭間で七転八倒を繰り返し、それでも何とか自身を鼓舞して今を生きようとする姿を描いた青春映画。俳優の海老沢七海が30歳になる節目に人生初の主演に挑み、代表作を残すという目標を掲げて自主制作した。監督・脚本を担当したのは監督作品「最悪は友達さ」がゆうばり国際ファンタスティック映画祭など4つの映画祭に入選した日下玉巳。撮影は「JOINT」(小島央大監督)、「脳天パラダイス」(山本政志監督)の寺本慎太朗。音楽は北海道生まれ、高円寺在住のフォークシンガー、グッナイ小形。
 TV放映スケジュール(映画)
TV放映スケジュール(映画)
- 2024年5月20日放送
-
13:00〜15:31 NHK BSプレミアム
白い巨塔(1966)
-
13:40〜15:40 テレビ東京
張り込み(1987)
-
19:00〜20:54 BSジャパン
荒野の用心棒
- 2024年5月21日放送
-
13:40〜15:40 テレビ東京
インサイド・マン(2006)
-
20:00〜22:01 BS松竹東急
あぶない刑事