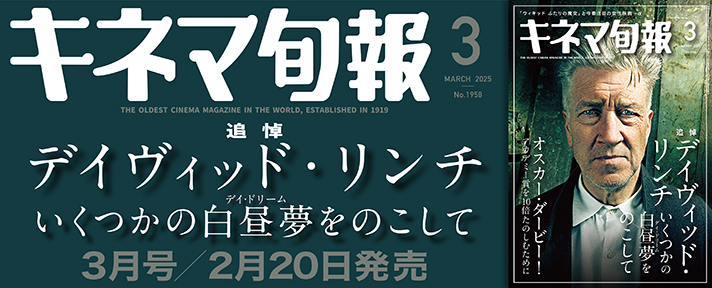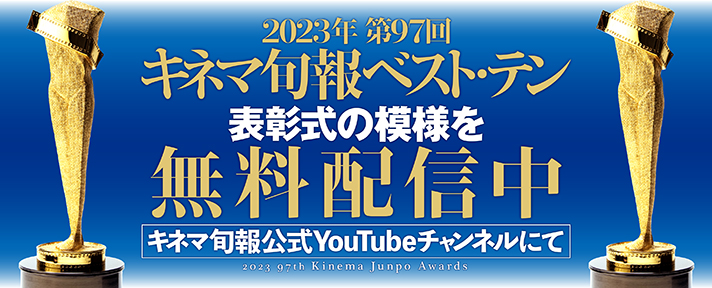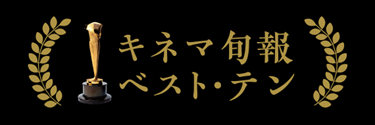ニュースNEWS
特集・評論ARTICLE
新作情報NEW RELEASE INFORMATION
週末映画ランキングMOVIE RANKING
キングダム 大将軍の帰還
公開: 2024年7月12日 公開 4週目怪盗グルーのミニオン超変身
公開: 2024年7月19日 公開 3週目劇場版すとぷり はじまりの物語~Strawberry School Festival!!!~
公開: 2024年7月19日 公開 3週目あのコはだぁれ?
公開: 2024年7月19日 公開 3週目逃走中 THE MOVIE
公開: 2024年7月19日 公開 3週目ルックバック
公開: 2024年6月28日 公開 6週目フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン
公開: 2024年7月19日 公開 3週目ヤマトよ永遠に REBEL3199 第一章 黒の侵略
公開: 2024年7月19日 公開 3週目それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン
公開: 2024年6月28日 公開 6週目ディア・ファミリー
公開: 2024年6月14日 公開 8週目専門家レビューREVIEW
もしも徳川家康が総理大臣になったら
公開: 2024年7月26日-
ライター、編集 岡本敦史
原作は「ビジネス小説」に分類されるそうだが、特に新味のある内容ではない。永田町が火の海になる愉快な展開とか、「シン・ゴジラ」ばりの国家改造シミュレーションとかいった見どころもなく、あるのはCM的なギャグの羅列のみ。また、劇中でフィーチャーされるのは一緒に蘇った秀吉や信長の政策で、家康はそれっぽい長広舌を披露するだけなので、タイトルの答えも見当たらない。国民の投票率アップを促すエクスキューズ的展開も、むしろ逆効果の感もあり、はなはだ迷惑である。
-
映画評論家 北川れい子
監督の武内英樹と脚本の徳永友一は「翔んで埼玉」シリーズのコンビ、しかもGACKTまで出演するということで、「翔んで埼玉」級の人騒がせな笑いと展開を期待したのだが、賑々しいわりには芝居のド派手な絵看板でも観ているようで、かなりがっかり。それでも話の導入部には身を乗り出し、現実の不甲斐ない政治家たちも、いっそAIで信頼できる人物に、と思ったりしたが、偉人内閣の面々は、通り一遍のイメージに収まったままで格別な活躍はなし。にしても家康のラストの大演説はお節介にもほどがある!
-
映画評論家 吉田伊知郎
偉人たちはAIで復活したホログラムで、時代変化も学習済、歴史上の禍根も抱かないようになっている懇切丁寧な設定が面白さを削ぐ。上杉謙信が瞬く間に自衛隊の装備を扱えるようになっていた「戦国自衛隊」よろしく、タイムスリップで偉人たちを強制連行してきても現代に順応したはず。ホログラムだから斬っても撃っても効果なしであることも生かされていないし、最後に現代人へ向けて偉人たちが説教臭い話を長々とするのも閉口。何より浜辺美波を輝かせていないのは許しがたい。
HOW TO HAVE SEX
公開: 2024年7月19日-
映画監督 清原惟
友人と旅行に出かけた少女が、旅先で初体験をしようと意気込むが思わぬ方向へ行ってしまうという、デートレイプの問題を扱った作品。突然訪れる残酷な出来事に、自分でも自覚しないままに傷ついてしまうさまは、主人公を演じた俳優によって生々しく表現されていた。少女らしい見栄の張り方、妬みや苦しみが、簡単に割り切れない複雑なもののまま存在していた。ただ、最後に突然訪れるシスターフッド感と、無理やりにでも元気を出そうとする結び方は、少し乱暴な感じがしてしまった。
-
編集者、映画批評家 高崎俊夫
見終えたあとで、ジェーン・カンピオンの絶賛や性加害のモチーフを潜在的に忍ばせさせた果敢な問題提起作という高評価に触れてやや意外だった。リゾート地に卒業旅行でやってきてお酒とダンスに興じる3人のティーンエイジャーの空騒ぎが延々と無造作に点描される。そのうちの一人がヴァージンであることに引け目を感じてひと夏の冒険を試みるという過去に無数に変奏されてきた〈初体験ヴァカンスもの〉のバリエーションであり、それ以上でも以下でもない。それとも私は全く別な映画を見ていたのだろうか。
-
映画批評・編集 渡部幻
宣伝の通り“直感的で感覚的な体験”であると同時に“感情的な経験の追体験”を探求した青春映画。物語としては何度も見てきたありきたりな青春の通過儀礼だが、描き方が違う。10代の少女のセックスへの憧れとプレッシャー、同意なき経験の痛みに皮膚感覚で寄り添いながら、前向きで、非感傷的である。全ての映画は人間の経験を扱っている。人の経験には個人差があるが、どこかで似通ってもいる。だからこそ私たちは経験の物語を共有できる。そんな映画の可能性を拡げる試みであり、この新鋭監督の才能だろう。
墓泥棒と失われた女神
公開: 2024年7月19日-
文筆業 奈々村久生
現時点の自分は、多くのロルヴァケル支持者に比べて、その美しい映像叙情詩を愛していない。ダウジングの能力を持つ主人公は「エル・スール」(83)を思い出させるが、あの父親もやはり喪失に囚われた男であった。失われた過去を幻想化して神聖視することは目の前の現実を容易に下に見ておろそかにする。ジョシュ・オコナー演じる男性のナイーブさは村上春樹的でもあり、幻想を取り戻すことがゴールではあまりに救いがない。その中で圧倒的な現在と現実を担う女性・イタリアの存在が希望だ。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
導入部で「幸せの黄色いハンカチ」みたいな人情話かと思ったら全然ちがった。超能力というものがあるとしたら(あるのだと思うが)それは正義のためや戦いのためには使われず、日々こういうことに使われているのだろう。もう死んでいる人から盗む泥棒は何を盗んでいるのか。泥棒にならざるをえない人々は誰から何を盗まれているのか。死んでいる人に恋し続けることは美しいことなのか。美術館や写真や一瞬の夢の中で見る過去の遺跡や過去の恋人は、どこから掘りだされてきたものなのか。
-
映画評論家 真魚八重子
撮影は35ミリ、16ミリ、スーパー16を使っていて、時折左右にぼやけた黒味が出る。特に使い分けに法則は感じず、適当な割り振り方に好感が持てた。そもそも主人公のアーサーがダウジングで古代の墓を探り当てる時点で、マジックリアリズムのような映画だ。昔の墓に入っていくシーンの供えられた動物の人形の魅力。アーサーはこの世とあの世の狭間にいる人間だが、失ってしまった恋人、魅了される古代の遺物と、過去に引っ張られているようだ。それゆえのラストシーンがまばゆかった。
フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン
公開: 2024年7月19日-
俳優 小川あん
人類の歴史的偉業「アポロ11号」の題材にひねりをくわえ、その裏側に存在したメディアの嘘を描いた壮大なブラックユーモア。それに留まらず、たくさんの夢と希望が詰まっている。95年に製作された「アポロ13」から、語りのアプローチがここまで飛躍するとは。NASAの当時の貴重映像とともにさまざまなギミックを駆使したオープニングから一気に心を掴まれる。後はもう映画のリズムに乗るだけ。やっと、バーランティ監督の実力が明らかになった。これからどんどん映画を撮ってほしい!
-
翻訳者、映画批評 篠儀直子
捏造映像を保険として撮影しておくことにしたのがやがてサスペンスを生み出すという、根強い都市伝説を逆手に取った着想がなかなか面白く、NASAを支えていた女性たちを讃える側面を備えているのもイマの映画らしくてよい。ところで作品の評価とは全然関係ないが、テイタムがチームメンバーを奮起させる演説シーンを見つつ、こういうのつい最近も見た気がするけど何だっけと考えてみたら「オッペンハイマー」だった。両プロジェクトの本質的類似性やら、表象行為の危うさやらを再度思い知らされた気分。
-
編集者/東北芸術工科大学教授 菅付雅信
1969年の人類初の月面着陸に関わる陰謀をめぐるコメディ。切れ者のPRウーマンをジョハンソン、NASAの発射責任者をテイタムが演じ、二人の掛け合いの楽しさは50〜60年代のハリウッド映画的。全体に往年ハリウッド映画的かつ、古き良きアメリカ的なテイストが濃厚で、最終的に誰も悪役ではなく、見事にハッピーエンドとなる。しかし、その後の世界を生きる我々としては「古き良きハッピーエンド」で映画を終わらせていいのかと。たとえコメディにするとしても月面着陸に対する批評的視点が必要はなずでは。
逃走中 THE MOVIE
公開: 2024年7月19日-
ライター、編集 岡本敦史
人気ゲームバラエティ番組の劇映画化という趣向自体にはなんの異論もない。面白ければ全然OKだが、結局なんの驚きも興奮もないまま終わった。反撃も対決もせず逃げ続けるだけのアクション映画がいかに成立し難いか思い知らされる内容だが、それ以前に、親友同士という設定にまるで実感が伴わない主人公たちのドラマが空虚すぎて震えた。現実世界を異世界のルールが侵食するという設定が映画版「クレヨンしんちゃん」そっくりで、敵キャラのドラァグクイーン3人組もすごい既視感。
-
映画評論家 北川れい子
テレビのバラエティ番組をドラマ化した映画だそうだが、ごめん、始まって5分ほどでスクリーンの前から“逃走”したくなった。友情と絆をベースにしたゲーム仕立ての青春アクション? 最後まで逃げきれれば賞金がドサッ!? が、設定もキャラも実に雑で、口裂け男まで登場、逃げて逃げての逃走シーンもただそういう場面があるだけ。彼らを追うハンターたちのナリフリが、サングラスに黒服、ネクタイで、以前の“NO MORE 映画泥棒”のキャラそっくり。まぁ勝手にやってれば。映画を観るのも忍耐なのだった。
-
映画評論家 吉田伊知郎
ひたすら追われて逃げるだけの映画の根源的な面白さに満ちた設定なのに、サスペンスの欠片もない。若者たちの古臭い青春回顧物語も邪魔。中途半端にテレビと連動させ、タレントの顔出しが多いのも興を削ぐ。それなら、「ミンナのウタ」のGENERATIONSのように、本作のJO1もFANTASTICSも本人役にした方が良かったのでは? 「もし徳」に暴れん坊将軍役で出なくて正解だった松平健という俳優のスケールを生かせていないのも無念。長井短のヒールぶりが見どころ。
化け猫あんずちゃん
公開: 2024年7月19日-
ライター、編集 岡本敦史
実写をトレスするロトスコープという作画技法は、現実を解剖するような生々しさと異化をアニメーションにもたらす。本作のもっさりした妖怪キャラたちはその効果を台無しにしそうに見えて、見たことのないリアリティと愛らしさをしっかり兼ね備え、そこに才人・久野遥子監督のセンスと巧さが光る。実写担当・山下敦弘監督のアニメ的定型から離れた構図も新鮮な化学反応を生み、のどかなのに終始ゾクゾクした。原作には登場しない、ちょいワルな主役の女の子も抜群にかわいい。
-
映画評論家 北川れい子
猫漫画、猫アニメに外れなし! いえ、ネコ好きの独りごとです。それにしてもアニメ化された大島弓子の傑作漫画『綿の国星』の猫同様、等身大に擬人化された茶猫・あんずちゃんのキャラと言動の愉快なこと。お寺の住職に拾われて37年、バイクで出張マッサージもする町の人気者。ただかなり皮肉屋。そんな猫人間が、住職の孫娘の世話をする羽目になって化け猫ぶりを発揮、リアルとファンタジーを巧みに融合させた展開は、絵も色も軽やか。ロトスコープなるアニメ手法が効果的で、そして森山未來の声!
-
映画評論家 吉田伊知郎
船頭が多くとも順路が一致すれば、こんな快適な旅が待っている。原作への愛着が迸る久野・山下両監督に、これまで河童に蛙、さらに神も地獄も平然と自作に登場させてきた、いまおかしんじの濃厚な脚本を理想的な形でアニメーションへ昇華。「お引越し」「つぐみ」から触発されたという映画オリジナルのヒロインの異分子ぶりも良く、終始不機嫌な少女と、あんずちゃんのドライでシニカルな描写の数々が素晴らしい。死を描きつつ安易な感動に利用しない作劇に、じんわりと涙が滲む。
お母さんが一緒
公開: 2024年7月12日-
文筆家 和泉萌香
男がどうの、あんたがどうのと互いを責めたてる姉妹たち、もうやかましいどころではないのだが、彼女たちはそうして「結婚」という同じひとつの言葉をぶつけ合い、「結婚」以上の複雑な呪縛、負の連鎖を引き剥がそうと頑張り叫びつくす。一晩明けてのさっぱり感は微笑ましく、その奇跡(!?)に救われたのは、彼女たちよりも母親か。「ゴド待ち」ならぬ「母待ち」でもなく、肝心の母も同じ旅館内にいる設定と施設での喧嘩っぷりは、映画の中でも現実性が欠ける気がするが……。
-
フランス文学者 谷昌親
脚本も手掛けているペヤンヌマキの戯曲が原作で、いかにも舞台劇らしく、終始温泉宿で展開する三人姉妹のほぼ一日の物語であり、俳優たちの演技も映画的というよりはむしろ演劇的と言えなくもないのだが、それがむしろコメディとしてのこの作品のあり方をうまく際立たせている。緻密に構成されつつパワフルに展開する原作と芸達者な俳優たちに身を委ねるかのように、これまでとは違い、余分な力を抜いた演出を披露した橋口亮輔監督によって、良質のコメディ映画が生み出された。
-
映画評論家 吉田広明
キューカー「女性たち」を思わせる密室女性劇。とは言えあれほど姦しくはない。母親を出さず(別室にいる)、主要舞台を姉妹らの一室に限る設定が、原作が演劇であることを思い起こさせるが、映画だと少し窮屈な印象。末妹が婚約者に対して吐く決定的な一言が、聞いてなかったでスルーされる、最後の母親の肯定的な言葉で結局事態が全て丸く収まるなど、いささか緩いのが引っかかるが、よく出来たドラマ。ただ、今これは映画として必要なのか、橋口監督がすべき題材なのかは疑問が残った。
クレオの夏休み
公開: 2024年7月12日-
俳優 小川あん
一つ一つのシーンが幼きクレオの記憶として、大切に扱われている。秀逸なのは、映されるいくつかの手元のショット。洗濯物を畳む母親代わりのグロリアの手。しかし、そこにはいないはずの我が子たちの存在を強く感じさせる。クレオがグロリアの素肌を指で触れる。同様に、亡き母親の存在がある。それらのショットは言葉より強い仕草で愛情を示し、その深さの海図は印象的なアニメーションで表現される。グロリアとクレオの永遠の絆はカメラのフィルターを越えるほどの温もりを与えた。
-
翻訳者、映画批評 篠儀直子
いわゆる「マジカル・ニグロ」(白人に都合よく奉仕する黒人キャラクター)のパターンになるのではと冒頭懸念したが、全然違う趣向の物語に。クレオはグロリアを実母のように慕うが、グロリアもその家族も、新しい子守が来れば他人になってしまう人々だ。クレオやグロリアから離れまいとするかのようなカメラ(ウニー・ルコントの「冬の小鳥」を思わせる)の親密さ。母親と過ごすはずの年月をクレオに奪われていた少年セザールの苛立ち。挿入されるアニメーションにも催涙効果あり。これはたまらん。
-
編集者/東北芸術工科大学教授 菅付雅信
パリの6歳の少女クレオが、アフリカ系の乳母グロリアが故郷に戻ることになり、彼女を訪ねてアフリカへの旅に出る。好奇心に満ち未知なるものとの出会いに一々興奮するクレオ役の少女が素晴らしく、劇映画とドキュメンタリーのいいとこどりをした高揚感とリアリティがある。願わくは、もう少しドラマ性があったほうが楽しめるのだろうが、そうなると映画が嘘っぽくなるのだろう。大まかな物語の筋はあるが、ほとんどドキュメンタルな現場感で作られている(ように見える)、フィクションとドキュメントの見事な交差点。ちょっとした映画の発明。
メイ・ディセンバー ゆれる真実
公開: 2024年7月12日-
映画監督 清原惟
子どもと大人の恋愛が客観的には犯罪と位置付けられたとしても、本人たちにとっては真実の愛として存在できるのか。そのようなテーマを内包する本作は、今の時代にかなりアクチュアルな内容。当時少年だった彼の眼差しは不安げで見ていて苦しくなるが、それでも簡単に被害者とは割り切れないように描かれていることの奥行きもある。知らず知らずのうちに近づいてくる暴力について考えさせられた。ナタリー・ポートマン、ジュリアン・ムーアをはじめとする俳優たちの演技がすごい。
-
編集者、映画批評家 高崎俊夫
ミシェル・ルグランの傑作「恋」のスコアが耳にこびりつく。トッド・ヘインズは「あるスキャンダルの覚え書き」と同工のテーマを全く異なるアプローチで自家薬籠中のものとする。事件の当事者に取材する女優がいつしか対象と同一化し、危うい共犯関係へと踏み入ってゆくのだ。「仮面/ペルソナ」「三人の女」といった人格交換劇の記憶を喚起させながらも、ヒロインの無意識の悪意が感染症のごとく他者に浸透してゆく恐怖をこれほど澄明なトーンで描ききった映画は稀ではないだろうか。
-
映画批評・編集 渡部幻
36歳の女性が13歳の少年と不倫し、逮捕されたのちに刑務所で出産。23年後、彼らの人生を映画化すべく主演女優が取材に来て……。異才トッド・ヘインズの腕が冴え渡る“解釈の迷宮”である。分裂し多層化したアイデンティティの混乱に、“演じること”と“同化”の問題が絡んでくる。ピンターとロージーの「恋」のテーマ曲(ルグラン)を編曲した音楽が強力で、精妙な細部を敷き詰めた一流の映画と同様、二度見るとさらに興趣を増す。蜘蛛の巣に捕らわれた元少年(チャールズ・メルトン)の哀れが胸に残る。
密輸 1970
公開: 2024年7月12日-
文筆業 奈々村久生
「ベテラン」(15)続篇の公開も控えたリュ・スンワン監督によるエンタメの極み。コテコテの方言でまくし立てる痛快なセリフ回しでクセの強い海女を演じたキム・ヘスの幅には目を見張るばかり。流行りのシスターフッドは監督の初期作「血も涙もなく」(02)を彷彿とさせる。時系列トリック、ゲストのチョ・インソン、潜水アクションなどてんこ盛りで語り口はややごたつくが泥くさいパワーと人情味が勝った感じ。当時のレトロカルチャーや70年代風味あふれるチャン・ギハの音楽も楽しい。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
実際の60〜70年代の韓国歌謡曲なのか新譜なのかわからないけど音楽がすばらしくて泣ける。水中撮影も美しい。泥臭い話だが編集で飽きさせない。人間がみんな暴力的で、かわいい。女と女の(恋愛ではない)友情と憎しみと事情を軸に、登場人物たちが変貌していくのが人生を感じさせて悲しいし楽しいし、物語の筋はそらさないまま映画そのものまでどんどん変貌していく。人の命の値段に関係ないサメ映画にまでなっちゃうサービス精神が炸裂。最後のオチ、あれも俳優のファンへのサービス?
-
映画評論家 真魚八重子
リュ・スンワンは「ベテラン」に引き続き、音楽に60年代コリアンサイケロックをチョイス。この絶妙な劇伴だけで楽しいのに、物語も海女たちvsギャングvs税関、という設定が素晴らしい。友情、裏切り、アクションとてんこ盛りで、スンワンの作品の中でももっとも抑揚があり、秀逸な出来。現代のフェミニズム運動とも連動した内容だ。女性たちの仲間で海女ではない人は、美人局的な役割を自然と担う仕事の分配も良い。キム・ヘスの全然老けない美貌とスタイルも目の保養になる。
キングダム 大将軍の帰還
公開: 2024年7月12日-
ライター、編集 岡本敦史
吉川晃司無双と大沢たかお歌舞伎が火花を散らす場面はずっと面白い。両者が戦場のド真ん中で繰り広げる一対一のバトルと、馬陽の戦いに決着がつくまでの一大スペクタクルは、確かに入場料の元は取れる見応えだ。とはいえ、そこに至るまでが長い。冒頭はツイ・ハーク作品も思わせる吉川アクションで魅了するも、中盤はファンフレンドリーに徹するがゆえ省略できない部分が多く、かなりの忍耐を強いられる。主役の影の薄さもシリーズ随一だが、見せ場は最高という評者泣かせの一篇だ。
-
映画評論家 北川れい子
今回もスペクタクルな戦闘シーンに因縁のある人物やそのエピソードを絡ませて進行するが、際立って魅力的なのは、大沢たかおが演じる大将軍・王騎の冷静かつ圧倒的なリーダーシップ。「キングダム2 遥かなる大地へ」の終盤に登場したときも、不敵な笑みを浮かべて大合戦を俯瞰していたが、その王騎が中華統一を目指す秦国軍を率いて戦う本作は、です、ます調の台詞といい、小事に拘らない大局的な戦術といい、実に鮮烈で、さしずめ大沢たかおのワンマンショー! あっ、吉川晃司の怪演にも拍手。
-
映画評論家 吉田伊知郎
もはや王騎を眺めることが最大の目的となっていた本シリーズ。作を重ねるごとに王騎役の大沢たかおが、とんでもない肉体と演技にバージョンアップしていく。これまで後方に控えてきた王騎による肉弾戦と饒舌な語りが中心となる本作には大いに満足するが、女優陣の扱いは薄い。清野は相変わらずアクションで際立つとしても、橋本、長澤、佐久間は突っ立っているだけで顔見世以上のものではなく、摎役の新木優子の細い身体と腕は、原作もそうだからとは言え、実写では説得力に欠ける。
大いなる不在
公開: 2024年7月12日-
文筆家 和泉萌香
まだ何も見ていない、もうすでに見た、何も見ていない、と反芻し続けたくなる魅力の作品だ。あっけにとられる逮捕シーンから始まり、自分の人生に長らく不在だった父が語る話、優しい義母の失踪……と少しずつ玉突きのように広がっていく謎のほか、登場人物たちのさまざまな感情をかかえながら、ある地点での状態の理由を明かすべく、まさに無限階段の時間をみせてゆくエレガントな手腕。藤竜也が発する声、呼びかけによって、どこかSFの手ざわりも感じられる傑作。
-
フランス文学者 谷昌親
疎遠だった父親との再会、その父親の認知症、結婚前の父と義母のあいだの秘められた情熱的な愛、そしてその義母の失踪、そうした重たいテーマのそれぞれに、近浦啓監督は真摯に向き合っている。だが、その真摯な姿勢が映画的な柔軟さを奪い、ひとつひとつのピースがばらばらのままになってしまった。職業は俳優という設定の主人公の卓(森山未來)が劇中で演じようとしているイヨネスコの『瀕死の王』のほうが、映画そのものよりもむしろ魅力的に見えてしまうのは、なんとも皮肉だ。
-
映画評論家 吉田広明
二十五年ぶりに父親と再会する主人公が視点人物で、父親の現在から過去を辿ることになるが、父親はいわば信用できない語り手であり、彼の語ることが本当なのか嘘なのか次第に分からなくなってゆく。とはいえその原因は認知症であって、そう言われれば何の驚きもないのだが、それをあえて羅生門形式のミステリ仕立てにするのは目くらましに見える。特に冒頭の逮捕場面はミスリーディングであざとく、そのせいで虚実のはざまに見えてくる真情も、共感度を著しく損なうことになる。
フェラーリ
公開: 2024年7月5日-
文筆業 奈々村久生
P・クルスの妻が息子の死という夫婦最大の試練から目をそらせないのに対して、愛人との二重生活に苦悩の証しを求めるエンツォは、A・ドライヴァーがまとう煮え切らない空気と相まって絶妙に愛され難い人物像となっている。特筆すべきは終盤の事故シーン。スピード、カット割り、犠牲者をとらえる描写の切れ味は戦争映画の爆撃シーンにも匹敵し、皮肉なことに、カーレースの熱狂とスリルと迫力を最も実感したのはここだった。その容赦ない凄惨ぶりにマイケル・マンの本気を見た気がする。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
アダムくん老け役でも顔つきも物腰もやっぱり変でいい。家父長制を煮詰めたような哀れな成功者。速度が経済になり、競うことに愛や死を賭けるなんて地獄だよ。自動車の映画だと思って観に来た人が期待するのだろう男のロマンという糞みたいなものがほぼ描かれない(クライマックスで少し描かれたと思ったら、すぐ最悪の悲劇が起きる)のがいい。ペネロペさんのサレ妻もいい。お金持ちの妻や愛人やってる女性、それと「がんばれ。命がけでやれ」と人に指図するのが仕事の人はみんな観てね。
-
映画評論家 真魚八重子
アダム・ドライヴァーは魅力的な俳優だし、役に入ると雰囲気も変わる傑出した存在だけれども、「ハウス・オブ・グッチ」から「フェラーリ」と、名門の実在の人物を立て続けに演じるのはどうなのか。他の才能ある俳優たちの、世に出る機会を奪っているのではないか? 車へのフェティシズムよりビジネスを優先しており、世知辛い話題が続くのも面白いとは言いづらい。事故のシーンは丁寧で非常にリアリティを持っていたが、基本的には車のフェラーリではなく会社としてのフェラーリの話だ。
先生の白い嘘
公開: 2024年7月5日-
文筆家 和泉萌香
強姦のシーンの悪趣味なスローモーション。しょっちゅう流れる音楽もひどいし、夫婦でのセックスシーンも撮り方や演出といい、性加害を扱う話であるのに、プレスの言葉を借りれば「センセーショナルさ」に注力してないか。配給宣伝側からもレビューの際のNGワードやらここはネタバレ注意やらの指定をされていて、もう、配給側もこういったテーマをまっすぐ扱う覚悟がないならやらない方がいい。原作者、鳥飼氏の「性被害を無くしたくてこの漫画を書いた」というコメントに★一つ。
-
フランス文学者 谷昌親
問題作と言われる漫画の映画化であり、むずかしいテーマに逃げずに取り組むその姿勢には敬意を表したいのだが、作品としてどうも咀嚼しきれない。性にかかわる問題を扱っているにもかかわらず、妙に観念的に感じられてしまうのだ。性が人間にとって重要であるのは言うまでもないが、同時に、それだけが人間を形づくっているわけではないだろう。どんな人間にも日常生活があるはずなのに、この映画の作中人物の場合、ひとりひとりの背景が一切見えず、薄っぺらな存在になっている。
-
映画評論家 吉田広明
自分が現在置かれた弱い立場は女であるせいと思い込んできた主人公が、同様の性被害に遭っていた男子生徒によって、男女問わない権力性こそ悪と気づき、同志として連帯する。衝撃的な題材を扱っているからこそ注目度も高くなるのではあろうが、性差別、権力性への眼差しは、より日常的で繊細なものに精度を上げる時期ではないか(「はちどり」がその方向性を示している)。女性性の肯定にしても、娼婦と聖女の同居という紋切り型イメージに帰着することで果たされるのは疑問だ。
Shirley シャーリイ
公開: 2024年7月5日-
映画監督 清原惟
凡庸の中に閉じ込められている若い女性と、天才的小説家の年上の女性が惹かれ合う物語。惹かれ合う二人の関係性もキャラクターも独特で、ステレオタイプではない。現代よりも女は男に支配されており自由ではなかったという視点も、単なる主張に留まらず、とても巧妙に物語に組み込まれていた。それでいうと夫が結局暗躍者で、創作さえうまく行けばいいとも捉えられるラストは少し腑に落ちないかもしれない。不穏なときに軽快な音楽が鳴る演出も、事態の混乱を表しているようで冴えていた。
-
編集者、映画批評家 高崎俊夫
〈イヤミス〉のベストテン上位に必ず選ばれる傑作短篇『くじ』の作家シャーリイ・ジャクスンの知られざる私生活に迫った異色作。最大の理解者たる大学教授の夫との捻れた共依存関係、そこに教職に就こうと目論む若い野心家夫婦が絡む。かくして肥大したエゴとモラルを欠落させた4人の間でアブノーマルな心理劇が展開される。シャーリイは多重人格がテーマの『鳥の巣』という傑作ミステリも書いているが、エリザベス・モスは深い狂気の淵にたたずむヒロインを絶妙に演じている。
-
映画批評・編集 渡部幻
伝説の小説家シャーリイ・ジャクスン夫妻と架空の若い夫妻をめぐる結婚と創作の物語。通常の伝記映画とは異なる。事情と空想を溶かした映像美が蠱惑的で、指先で触れれば絵の具が付きそうだ。劇中のシャーリイは、代表作『くじ』の後で、実際の少女失踪事件に刺激された『絞首人』を執筆しようとしている。それらは実在の小説だが、ジョセフィン・デッカー監督は、かつてワイズが映画化した「たたり」同様、女性心理に力点を置き、仮にシャーリイ(エリザベス・モスはそっくり)に詳しくなくとも引き込む力があると思う。
THE MOON
公開: 2024年7月5日-
俳優 小川あん
ウリ号? 韓国人宇宙飛行士で月面を歩いた人いたかな?と思ったら、近未来のSF映画だった! 韓国が宇宙開発競争に限らず、世界の映画産業に対しても切り札を差し出したような結構な力作。ドラマ展開に実直すぎる部分はあるけれど、主演ソル・ギョングの勢いで物語を引っ張っていく。ツッコミどころがたくさんあったが、楽しく鑑賞した。CGでイノシシの集団が突然現れるところとか、偉い上層部の人物に限ってオーバーアクティングしがちなこととか。エンタメ要素はやや韓国ドラマ寄り。
-
翻訳者、映画批評 篠儀直子
映画内の人々が国の威信をかけて技術力の高さを証明しようとするのと同様、この作品自体もまた、韓国映画の技術力がいよいよ世界トップレベルにあることを証明する。複数の先行米国映画の影が序盤こそちらちらするが、手に汗握る展開を観るうち気にならなくなるはず。一方、もはやこれまでという局面を打開するのが、過去の因縁とディープな情念というのは韓国映画らしいところ。いつものように愛すべき小物感を爆発させるチョ・ハンチョルからいつも素晴らしいソル・ギョングまで、キャストも充実。
-
編集者/東北芸術工科大学教授 菅付雅信
韓国初の月面有人探査というミッションを担い3人の宇宙飛行士が月へ旅立つが、太陽風の影響で2名の命が失われる。果たして残された1名は月面探査を行い、地球に帰還できるのか。韓国映画として最大級の超大作SFだが、構成は「ゼロ・グラビティ」×「オデッセイ」のまんま。そこに過剰なまでの愛国主義的な情感を盛り込み、かなりウエットな仕上がり。この制作費と技術力には素直に負けを認めるが、いかなる国の愛国主義映画も好まない私としては残念なプロパガンダ映画に思える。
WALK UP
公開: 2024年6月28日-
俳優 小川あん
今までありそうでなかった、ワンシチュエーション縦4層構成。娘を含めた女性4人に対してのそれぞれの時間軸を経て、主人公の男性を多方面から覗き見る。会話劇として肝心なはずの会話は、中身があるようでないよう。傍観するしかない観客は、どこに当の本人の姿があるのか見失う。そうしてるうちに、ひとり煙草を吸うビョンスの無の時間で幕は降りる。結果、悩める男を悲哀の者にしてしまうのだ。こういったある意味の悪事を見事なセンスでホン・サンス先生はこっそりカバーする。
-
翻訳者、映画批評 篠儀直子
作中に出てくる台詞を聞いて、なるほどホン・サンスの映画は酒を飲みながらだらだら観るのにちょうどいいのだ(そして酔いが回ってわからなくなったらその地点からまた繰り返し観ればいいのだ)と膝を打ち、今回は変なズームとかないんだな、ある意味正攻法の撮り方だなと思っていたら、最後の最後にこんな仕掛けがあるのだから油断がならない。原題は「塔」という意味だが、階を上がるたび変わるビョンスの姿は、まさに「どれもビョンス」なのだろう。クォン・ヘヒョが美声の持ち主だと今回気づく。
-
編集者/東北芸術工科大学教授 菅付雅信
韓国のインディー映画作家を代表するホン・サンス監督の最新作は、まるで彼のアバターのような映画監督が主人公となり4階建てアパートメントを舞台に、各章ごとに一階ずつ上の階に上がっていく4章構成の繊細なコメディ。悩み多き中年映画監督だが女にはモテるところはウディ・アレン的。モノクロの画像が美しく、ウィットに富んだ会話が楽しく、時間経過が曖昧なままエピソードがつながり、最後が円環構造になる構成の斬新さに感服。「映画作家」への批評的視点も持った、見事な映画作家映画。
ふたごのユーとミー 忘れられない夏
公開: 2024年6月28日-
映画監督 清原惟
まず、ひとりの俳優によって双子の少女が演じられていることにとても驚いた。そしてそのことに常に意識を奪われながら見てしまったようにも感じる。双子の恋とお互いへの想いの間での葛藤を描く物語なのだが、全体的にかなりクリーンな映像で、少年少女も絵空事のように美しいので、あまり内容に親身になれない感じがあった。それでも、同じ俳優が双子を演じていても、映画が進むうちに全く別の人に見えてくるのは、演技というものの不思議さに改めて思いめぐらせるきっかけになった。
-
編集者、映画批評家 高崎俊夫
双子というテーマは「らせん階段」から「シャイニング」まで恐怖映画と相性が良いが、思春期の恋愛ものはどうか。近年、タイ映画は前衛的なアートフィルムから時代の先端を行くエンタテインメントまで懐の深さを垣間見せているが、監督が一卵性双生児姉妹である本作のような等身大の視点を感じさせる作品に出会うと妙にホッとする。親密なスロームービーの趣向とは裏腹に貧困で離散を強いられる過酷な家族の肖像は苦い現実のリアルさを突きつける。
-
映画批評・編集 渡部幻
田舎で夏休みを過ごした女の子2人と男の子1人の恋模様。飽き飽きの設定だが、少し変わっているのは舞台が1999年のタイで、主人公が双子の少女の点。長篇デビューとなる監督も双子の女性であり、新人女優が一人二役で双子を演じている。何をするにもシェアしてきた双子も中学生となり、ある出来事をきっかけに心優しい少年をシェアすることになってしまう。恋は大人への一歩で、やがてはそれぞれの恋をして、人生を歩まねばならない。わざとらしいほど天真爛漫として純情な3人のセンチメンタルな成長物語。
スリープ
公開: 2024年6月28日-
文筆業 奈々村久生
睡眠中の夫の奇行が心身機能の異変か超常現象かの境を行き交うストーリーテリング。「ローズマリーの赤ちゃん」(68)に連なる系譜で、本作の核心は、最も身近で信頼すべき相手を信じられなくなる恐怖だ。愛する人が得体の知れない存在になっていく。その葛藤と戦う妻をチョン・ユミが好演。夫役のイ・ソンギュンも昨年韓国での公開時に観たときはまだ存命だった。惜しむらくは映像が暗いこと。光量を落とせば暗さが写るわけではなく、闇は光との対比であり、影の濃さで体感したかった。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
不眠で生活に支障をきたしたり悪夢に殺人鬼が現れるのではなく、よく寝てるのに動きだして昼間はしない異常行動をしちゃう。夢遊病者は内面の無意識で抑圧(幸せな夫婦が抑圧が強いのは現実によくある)から解放されてるのか、外部の超自然の悪意に呪われているのか、ホラー映画の文脈では峻別困難だという脱構築ホラー。章立てで視点が変わるのは「来る」と同じだが、あそこまで無惨ではない。睡眠中に自分で顔を掻きむしるのが事件の発端で、アトピー持ちの僕としては複雑な気持ちに。
-
映画評論家 真魚八重子
イ・ソンギュンは韓国の俳優の中でも三本指に入るほど好きだったので、亡くなった今その姿を観るのは悲しい。映画の構成は章立ての通り、妻の出産を境に狂気に憑かれているのが夫から妻に移行して見える。無防備な赤ん坊を前にして、母性が女性の正気を奪うのは正しいかもしれない。後半のチョン・ユミの演技は恐ろしく、何をしでかすかわからない演出と芝居は秀でている。ラストは芝居なのか、本当に霊が抜けたのか、観客に判断を委ねるタイプで、珍しく面白い宙吊り感があった。
言えない秘密(2024)
公開: 2024年6月28日-
文筆家 和泉萌香
映画は時を超えるボーイ・ミーツ・ガール。「歩く二宮金次郎像」をはじめ昔から学校には不思議話が多々あるが、この現代にあって学校はそんな不思議や秘密ごとを忍ばすことができる最後の砦であり、ただ恋の舞台となりえる最後の場所のようにも思えてくる。彼らの<旅>が直線の時間軸からきっちりと足を踏み外しはしないのと、涙、涙のクライマックスは残念だが、ラストカットはロマンティックで、潔い。ピアノの猛練習を重ねたという主演の京本と古川もきらめくように魅力満点だ。
-
フランス文学者 谷昌親
ファンタジー色の強い台湾の恋愛映画のリメイクだが、いくらファンタジーと言っても、この物語の設定を受け入れさせるにはそれ相応の表現力が必要なはずで、たしかに、謎の少女が初めて画面に登場する際に鏡に映った身体の一部のイメージを示すなど、それなりの工夫は見られるものの、作品全体としては残念ながら説得力を持つまでに至っていない。劇中で重要な役割を演じるピアノ曲も、映画音楽風のものでなく、オリジナル版のようなクラシカルな曲のほうがよかったのではないか。
-
映画評論家 吉田広明
ピアノが嫌いになっていた音大生が、妖精的な存在により音楽への愛を取り戻す。定型的な物語であるが、定型は内容の理解が早い利点もある一方、個々の作品を呑み込んでしまう怖いものでもある。個性は伝統のもとに発揮され、伝統は個性によって賦活する。何も新しい作品が新奇でなければならないこともないが、定型への意識(それが批評意識であり、個性)は必要に違いない。それが無ければ単なる「使用価値」(この場合「泣ける」等)しか残らないが、そんなものは早晩摩耗するだろう。
わたしの物語
公開: 2024年6月22日-
文筆業 奈々村久生
差別や偏見が生まれる一因として「見慣れていない」ことは強く作用する。監督かつ被写体であるエラの下半身が短い容姿は多くの人にとって「きわめて稀」だと思われるが、約1時間半の上映中にエラの姿に触れ続けるだけでも認識は劇的に変わる。要は「慣れる」。四肢延長と再建手術の権威である医師との対面はハイライトで、誰かを否定したとて自分を肯定できるわけではない複雑さをエラの表情が物語る。エラの夫の視点がないことは、彼女たちの関係にとって障がいが絶対的ではない証だろうか。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
エラ監督は美人だ(とジャッジしてるんだからこの短評はルッキズムという差別である)が映画ではそこは言及されない。若い美女でありつつ障がい者でもあることはそれはそれで大変だろう。ところでメガネをかけなければ外出できない我々は障がい者だが、メガネやコンタクトという補助具が普及しまくったから生きることができてる。治療したほうが幸せだという医療モデルと、矯正するのではなく当人の自己受容の尊厳を大切にするべきとの考えの、人生を賭けた対立が凄い。いい映画でした。
-
映画評論家 真魚八重子
生まれつき、両足に障がいがあるエラ・グレンディニング監督。特徴的な障がいの中でも、片足だけの症状が多く、両足という例は他に会ったことがないという。障がいが世界でも自分だけというのはなんと不安なことか。その合間に映るエラの私生活は、恋人と生活をエンジョイする積極性が印象深い。手術による治療も進んでいるが、幼児期から何度も手術をし、部分的な切断なども余儀なくされる。自身で判断がつかぬ年齢からの治療や、健常者と同じが良いことなのかを問いかける映画だ。
アンゼルム “傷ついた世界”の芸術家
公開: 2024年6月21日-
映画監督 清原惟
アンゼルム・キーファーの作品を紹介するためにヴェンダースがとった手法は、言葉を削ぎ落として、高精細で抽象的なイメージを使うということ。少年時代のシーンなどはノスタルジーを感じてしまわなくもないが、同世代の作家として世界観に共鳴して撮っているのも窺える。制作風景の場面では、80歳近い作家自身が熱々の液体を絵にぶちまけていてスリリングで良かった。ヨーロッパの負の歴史に向き合う作家が、現代社会とどのように向き合っているのか、もっと知りたい気持ちが芽生えた。
-
編集者、映画批評家 高崎俊夫
ヴェンダースは敗戦の前後に生まれ、同時代としての戦後を生きたアンゼルム・キーファーの膨大な作品を俯瞰する際、注釈としてハイデガーとパウル・ツェランを引用する。ナチズムの〈凡庸な悪〉を告発したハンナ・アーレントの愛人・師でありナチスに加担した大哲学者と虐殺から生き残ったユダヤ詩人の対比が印象に残る。とりわけツェランの肉声による詩の朗読が延々と流れる件が忘れがたい。ホロコーストの呪縛を抱えた母国へのアンビヴァレントな想念が本作の純粋心棒といえよう。
-
映画批評・編集 渡部幻
ドイツの芸術家アンゼルム・キーファーのドキュメンタリー。冒頭にドレスの彫刻群が現れる。頭がなく、代わりに本や石が乗せられ、ガラスの破片が刺さったものもある。女性の声——「私たちは名もなく忘れられし者。でも私たちは忘れない」——空間を時間が浮遊している。ドイツ降伏の1945年に生まれたアンゼルムは、自国の過去と対峙し、その忘却に抗う壮大な絵画と彫刻を連作。同年生まれのヴェンダースは「ベルリン」を撮った。3Dを2Dで観た。が、それでもここには紛れもない“映画の感動”があった。
ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ
公開: 2024年6月21日-
映画監督 清原惟
人間は自分以外の誰かのために自分の人生をつかうことができる。そのことを信じさせてくれる素晴らしい作品だった。初めは気軽な学園コメディだと思い観ていたが、少年が一人取り残されるあたりから、クリスマスの神聖な空気も相まって映画全体が神秘的な空気で包まれた。出てくる人たちは、別にみんな善人というわけでもない。それでも、たとえ人生の中の一瞬の出来事であっても、人間と人間の儚く強い結びつきが存在できたことに心震える。クリスマス映画の定番になってほしい!
-
編集者、映画批評家 高崎俊夫
1970年という映画の時代背景はアメリカン・ニューシネマの全盛期にあたるが、既成のヒットポップスを一見、無造作に垂れ流すような手法はまるで「卒業」のようである(映画館でD・ホフマンの「小さな巨人」を見るシーンあり)。無論下敷きになっているのはハル・アシュビーの「さらば冬のかもめ」だろう。互いに反撥しあう師弟関係が繊細な感情教育によって変容を遂げてゆく。こんな深い味わいをもったロードムービーは本当に久しぶりだ。ポール・ジアマッティの新たな代表作である。
-
映画批評・編集 渡部幻
アレクサンダー・ペインは今もロードムービー作家であり続けていて、世がどうであろうとも人間主義を手放さない。名優ポール・ジアマッティも同様だ。例えば同じペインとの「サイドウェイ」、あるいはクローネンバーグの「コズモポリス」終盤で映画全体をさらったあの人間臭さ。1970年のクリスマスが舞台の教師と生徒の物語。冬の映画であり、70年代のハル・アシュビー好きは気に入るのではないか。我が道をゆくアメリカ監督による小さな宝石。ぼくならオスカーはジアマッティに投票しただろう。
HOW TO BLOW UP
公開: 2024年6月14日-
文筆業 奈々村久生
過激な環境テロで加害企業に一矢を報いようとする者たち。緊迫感を煽るように延々と流れ続ける音楽がかえって集中力を疲弊させる。メンバーの動機は全員の個人的な怒りや悲しみに基づき、社会活動と言うには甘く、組織的な犯行としての周到さにも欠け、未熟な寄せ集め集団の幼稚な犯罪劇になっているのが悲哀を誘う。犯人が何らかの被害者である場合、首謀者が英雄になってしまうと本質がロマンチシズムにすり替わってしまうため、リーダーのドヤ顔が散らつくラストは極めて後味がよくない。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
スーパー戦隊み、と言って不謹慎なら「七人の侍」みがあった。脚本に凝りすぎずバババッと書いちゃって撮った感じも、低予算だから撮りかたをいろいろ工夫してるのも、終わりかたも、めちゃめちゃ良い。こんな話をこんな面白い映画にされては国家権力や大企業は困っちゃうねえ。こっちとしてはアジア人を一人入れといてくれると(金持ち坊ちゃんを中国か韓国か台湾か日本からの留学生にするとか?)さらにもっと楽しめたかもと思ったけど、そこまでやらんでもいいか。とにかく面白かった!
-
映画評論家 真魚八重子
破片のような個々の人々が、ある時点で集合し力が結実して何かが起こる。それがテロリズムであることが、この計画に携わる者たちと、石油会社による環境汚染の関係性で明らかになっていく。計画はスマートで、若者たちは危険だが練りに練った計画が展開する。不毛に終わらず、過激すぎない目的を掲げた正義感に基づくテロリズム。こういったテロを描いた映画が少ないと気づかされ、個々の若者たちの役割分担が鮮やかな脚本に唸る。率先した自己犠牲など身を切る思いに揺さぶられた。
蛇の道(2024)
公開: 2024年6月14日-
映画監督 清原惟
1998年の原作映画は男性同士の二人組だったが、今回は男と女に設定が変わっていたのが、印象を大きく変えていた。前作を観たのがかなり前なのでぼんやりとした記憶だが、残酷でありながらもその過剰さに少し笑いを覚えた気がする。しかし、今作は笑いが微塵もないシリアスな映画になっていた。人を拷問するシーンがフィクションに見えず、世界で今も起きている現実として見えてしまう自分の受け取り方の変化かもしれないが……。柴咲コウの本心が分からない魅惑的な声に惹きこまれた。
-
編集者、映画批評家 高崎俊夫
「勝手にしやがれ」シリーズを連打していた頃に見た「蛇の道」はその酷たらしいまでの暗さに驚いたが、いっぽうで、スラップスティックすれすれのガンアクションには黒沢清の真骨頂が窺えた。リメイク版もパリの市街を柴咲コウが律儀に自転車で移動する場面や廃屋のような寂れた工場での拷問シーンまでもが前作同様の低予算感覚に貫かれ妙に感心してしまった。ただし住宅街を車で周回するだけで〈不気味なもの〉を醸成させた不可知論的な恐怖をめぐっては前作に軍配が上がるのではないか。
-
映画批評・編集 渡部幻
セルフリメイクといえば、ヒッチコックや市川崑らを例に出すまでもないが、黒沢清も挑戦した。しかも最も過激だった頃の異色作を、それもフランスで。哀川翔が演じた役を柴咲コウが演じたことによって“復讐の冷酷さ”に新しいニュアンスが加わっている。が、それ以前に驚いたのは、画面構成がオリジナルからあまり変わらないことで、しかも緊張感と恐怖感が減退していたこと。そして何よりも残念なのは、マチュー・アマルリックを含むフランスの俳優が揃って精彩を欠いており、退屈な存在に思えたことだ。
オールド・フォックス 11 歳の選択
公開: 2024年6月14日-
俳優 小川あん
数多くの傑作が生まれている台湾。独特の風習と生活が撮影に大きな影響をもたらすはずが……本作にはその魅力が感じられない。生と死、男と女、経済格差などの要素を扱っているが、表面から掘り下げられていない。その上、俳優の芝居もポーズになってしまっていて伝わらない。長い時間をかけてゆっくりと抉っていく人間の性を見たかった。少年の将来像がチープな演出になっていたのもがっかり。チェン・クンホウ「少年」を想う。侯孝賢は脚本に言及しなかったのかしら?
-
翻訳者、映画批評 篠儀直子
ファーストショットのあまりの見事さにいきなり度肝を抜かれ、美しい画面のテキパキした連鎖にドキドキし、帰宅したリウ・グァンティンがサックスで〈恋に落ちた時〉をしっとりと演奏しはじめるに至ってはもう身もだえしそうにたまらない。この導入部分で興奮しすぎたせいか、いまいち加速していかないかのように感じてしまったけれど、その後も充実した画面が頻出、ノスタルジックなスコアも素晴らしい。ある種のふてぶてしさをたたえた子役俳優の演技を含め、全方面において立派な仕事の映画。
-
編集者/東北芸術工科大学教授 菅付雅信
バブル期の台北の少年の成長を描くドラマ。レストランで働きながらお金を貯めて理髪店を開こうとする父を尊敬する純朴な少年が、バブル崩壊の中で「腹黒いキツネ(オールド・フォックス)」と呼ばれる地主のタフな人生哲学に惹かれていく。清貧潔白な父を支えるか、強烈な拝金主義に身を委ねるか。少年の成長譚として普遍のテーマを台湾ならではのウォームな質感で包み、丁寧なリアリズムで描く。共感する物語だが映像的面白みに欠けるのが惜しい。
ディア・ファミリー
公開: 2024年6月14日-
ライター、編集 岡本敦史
「実話ベースのお涙頂戴もの」というイメージで甘く見てはいけない良作。日本人好みの『下町ロケット』的な熱血技術開発秘話と、常に哀歓を湛えた家族の年代記が並行して描かれる物語は、現実の悲劇に対して不謹慎な物言いだが、秀逸な構造である。それに対してオーソドックスに徹する演出の賢明さも好ましい。ただ、IABPバルーンカテーテルという名称を劇中であれだけ連呼するなら、もっと専門的ディテールを見せてもよかった。観客の知識欲も満たすことが作品の厚みになるのだから。
-
映画評論家 北川れい子
かつてのNHKの看板ドキュメンタリー『プロジェクトX 挑戦者たち』が、『新プロジェクトX〜』としてこの4月から復活したが、本作はさしずめ“プロジェクトX“の個人版。町工場の経営者が、心臓に疾患のある娘のために、自ら時間と資金を注ぎこんで医療器具の開発に挑み、やがて多くの命を救う器具を完成するまで。むろんその過程で大学の研究者や専門家なども関わり、具体的な器具がいくつも作られる。主人公の飽くなき探究心と家族愛には頭が下がるが、大泉洋の見え見えの熱演が煩くも。ごめん。
-
映画評論家 吉田伊知郎
冒頭でカテーテル開発をめぐる映画であることが明かされるので、人工心臓の開発に四苦八苦する前半に、いつカテーテル開発に切り替わるのかとやきもき。しかし、大泉の軽やかさが猪突猛進型のキャラを暑苦しくさせない。川栄、福本ら姉妹の関係性もさり気なく描かれ、押しつけがましい感動映画にならないよう慎重に計算されている。菅野美穂の吐息芝居が妙に引っかかった点を除けば流石は月川翔。70年代から現代へと時代性を程よく表出させた見せ方も大味にならず好感。
風の奏の君へ
公開: 2024年6月7日-
文筆家 和泉萌香
異性の浴場に向かって声かけし騒ぐノリなど、高校生にも失礼では? 100歩ゆずって男同士「素直になれよ」系の大喧嘩も、「お姉さんがいうこと聞いてあげる」的台詞も、コミカルな学園ものなら微笑ましいが、こちらは“余命もの”だし、大の大人たちばかりでくすぐったいどころではない。原作は部活を引退したばかりの「空っぽ」な受験生が主人公とのことで、年上の女性への憧ればかりでなく、その喪失感や焦燥にもう少し重点を傾ければ、青春映画の味わいがあったかもしれないが……。
-
フランス文学者 谷昌親
冒頭の橋の上の出会いとそこで吹く風が魅力的に感じられないのがまずは致命的だが、その後の展開においても画面には力が感じられず、物語も陳腐なエピソードの羅列にとどまっている。主人公と高校時代の友人たちとの関係をもっと描けば、少しは違ったかもしれないが、それ以前にキャスティングに違和感があり、演出にも冴えがない。同じように女性ピアニストが主人公だった昨年のテレビドラマは、大谷監督らしいセンスを感じさせる出来になっていただけに、残念としか言いようがない。
-
映画評論家 吉田広明
地元を振興したいという善意があればどんな映画であっても良いわけではなかろう。映画としてユルユルであれば、むしろその善意は見る者の反感さえ招く。地場産業に関わる兄弟、元カレであるその兄の方を訪ねて訪れたピアニストが死病を得ていたというメロドラマ。物語の通俗性は措き、その通俗性をただの一瞬すらも超え出ることのない演技、ピアニストが書く楽譜に一枚一枚彼女の「想い」が記される説明臭さ、彼女の演奏にフラッシュバックされる過去演出の凡庸にほとほと閉口する。
チャレンジャーズ
公開: 2024年6月7日-
俳優 小川あん
前作「ボーンズ アンド オール」に続き、主演俳優がプロデューサーも兼任する製作スタイル。なにかと注目・期待されているルカ・グァダニーノ、主演はゼンデイヤ。いろんな意味で絶対的に面白くないわけではないんだけど、問題は捻くれた視点で作品を見てしまうこと。汗が滴るスローモーション。両脇に男を抱え、もみくちゃになるタシ。会場が吹っ飛ぶほど激しすぎる台風。決闘を睨むタシ。そう、少しスクリーンから距離をとりたくなるほど圧が強い。ゼンデイヤが歩くと、嵐すらも避けそうだ。
-
翻訳者、映画批評 篠儀直子
同じ女を二人の男が同時に愛する映画といえば、男たちこそが愛し合っているように見えることが多いのだが、その最もあからさまな例かも。対戦する二人はやがて完璧な相互理解へと至る。では女の立場はと言いたくなるけれど、この映画のゼンデイヤはこれぞ本領発揮で最高で、コートの中のゲームも外のゲームも彼女が支配しているのだった。テニスボールの主観ショットまで登場する、技巧満載のクライマックスの愉快さ。映画が進むにつれどんどんなじむ、レズナー&ロスのテクノ風電子音楽もよき。
-
編集者/東北芸術工科大学教授 菅付雅信
ルカ・グァダニーノ監督作で今や時代のファッション・アイコンであるゼンデイヤ主演。3人の男女のテニス選手の十数年にわたる複雑な三角関係を描く。物語はノンリニアな時間の流れをモザイク状に組み合わせ、最後の男二人のテニス対決という山場を迎える。ハイスピードカメラを含むカメラワークが秀逸で凝った編集も加わり映像力としては傑出した出来。グァダニーノ映画としては面白すぎる仕上がりだが、グァダニーノ映画にエンタメ以上のものを求める者には物足りない。
罪深き少年たち
公開: 2024年6月7日-
映画監督 清原惟
街の小さな商店で起きた強盗事件を発端に、警察の不正に立ち向かおうとした警察官と、裁かれることのなかった真犯人たちの話。権力に刃向かい干されてしまった警察官と共に、冤罪を着せられた可哀想な少年たちが立ち上がるというストーリーは、定番の流れや演出でありながら応援したくなる。映画としては少しご都合主義に感じられる部分もあったが、この映画を観た日にちょうど袴田事件の再審のニュースが流れたというタイミングもあって、主題としても考えさせられるものがあった。
-
編集者、映画批評家 高崎俊夫
ソル・ギョングの風貌は質朴で愚直なまでのヒューマニズムゆえに孤立し苦悩する人物像がすぐさま想起される。実話ベースの冤罪事件の真相を探る本作でも〈狂犬〉という異名をもつ敏腕刑事という触れ込みとは裏腹に、滲むように表出される優しさを隠蔽することはむずかしい。15年という歳月を行きつ戻りつしながら、刑期を終えた少年たちの現在と事件当時を交錯させる語り口もあまりに古色蒼然というべきだろう。とはいえ往年の〈警視庁物語〉シリーズを彷彿させる妙な安定感は捨てがたい。
-
映画批評・編集 渡部幻
冒頭に「実話に基づいたフィクション」と字幕が出る。時代背景は1999年から2016年。冤罪に青春を台無しにされた少年たちの物語で、熱血刑事が杜撰な捜査の真相に迫る。しかしこれは臆面もなくお涙頂戴的な脚色を施した作品であった。絵に描いたような正義漢、卑劣漢、臆病者が彩る感情のドラマは古めかしく、過去と現在を行き来する構成も効果的とは言えない。要点から要点に飛躍できる便利さがあったにしても、余程の趣向を凝らさなければ、肝心要の人の心に太く繊細な筋を通すことはできないのだ。
ドライブアウェイ・ドールズ
公開: 2024年6月7日-
俳優 小川あん
B級映画のオマージュをベテランの映画監督が全力で作ったらどうなるか? それはもう、楽しいが炸裂。謎の男が狙われる最初のシークエンスで、カメラアングルとポジション、カット割り、編集の諸々で、イーサン最高だね! 突然現れるサイケな世界観もイケイケGOGO! そんな無茶苦茶なロード・ムービーはきちんと二人が結ばれる道のりであった。愛を育んだキスシーンは色っぽくドキドキした。ラブシーンは小ネタで笑わせられる。クィアのパートナーを偏向しない描き方が気持ちいい。
-
翻訳者、映画批評 篠儀直子
追いかけてくるギャングたちの描き方や、彼らと主人公ふたりが出くわしてからの展開にもうひと工夫ほしいけど、どこまでもくだらないたわいなさが最高なロードムービー。でも芯にあるのはロマンティック・コメディのエバーグリーンなフォーマット。「メリーに首ったけ」をみんなでニコニコしながら観ていた記憶が思い出される。マーガレット・クアリーとジェラルディン・ヴィスワナサンがふたりともすごく魅力的で、今後の活躍にますます期待大。クアリーがお母さんそっくりなのにもしみじみ。
-
編集者/東北芸術工科大学教授 菅付雅信
コーエン兄弟のイーサンの初単独監督作。レズビアンの女性二人がアメリカ縦断ドライブする中で犯罪に巻き込まれるコメディ。ちょい役のマット・デイモン以外はスターキャストはなく、徹底的にB級路線でコーエン兄弟映画から芸術性を引いてくだらなさを倍増した仕上がり。「それを意図してるんだよ!」という監督の声が聞こえそうだが、どこかしらインテリのB級ごっこ感がプンプン漂ってくるので、本気のB級映画のほうがずっと楽しめる。兄弟監督は単独では成功しないというジンクスがここにも。
かくしごと
公開: 2024年6月7日-
文筆家 和泉萌香
「母性観」をめぐっては女性同士も異なるさまざまな意見があるし、個人的にも母性なるものには懐疑的。「母親でありたい」という願いも、大人のある種のエゴには違いない。本作は嘘を重ねてしまった「母親」に同情するでも突き放すでもなく、キャメラは出来事を静かに追い続けるが、「虐待被害者の児童を安全な場所で護りたい」という(社会で広く共有されるべき)彼女の揺るがない心を、なかば強引だが感動的なかたちで尊び通すのには、涙が出る。杏の素晴らしさはここで書き尽くせない。
-
フランス文学者 谷昌親
認知症の父親、虐待を受け、記憶をなくした少年、この2人が主人公の千紗子を軸にして絡み合い、さらには、山里の風景や古い日本家屋での生活、造形作品の制作といったエピソードが散りばめられた映画は、すべてが丁寧に準備され、撮影され、編集されたという印象をあたえる。だが、その丁寧さがそれぞれの要素をかえって引き離してしまった。しかも、最後に少年が重大な発言をした瞬間、物語のすべてがその言葉に収斂していき、作品にむしろ亀裂が入ってしまったように感じられる。
-
映画評論家 吉田広明
道端で拾った虐待を疑われる少年が記憶喪失という設定、また性格が妙に素直なのも胡散臭いと思っていると案の定。また奥田が彼に渡すナイフも唐突で、何か伏線なのだろうと思うと案の定。ミステリと謳うならばこれら伏線の分かりやすさは難点だろう。また最大の難は、奥田に対する杏の態度の変化が、認知症がどういう病なのかの医者による説明を聞いて起こったり、また少年が自身の口で真相を語るために、さほど必要と思えない裁判劇が最後に設定されたり、総じて言葉に依存している点だ。
違国日記
公開: 2024年6月7日-
文筆家 和泉萌香
両親を失った少女の、世界に一人ぼっちになってしまったような感覚、足湯の暖かさや食事の美味しそうなこと、朝日の美しさなど、視覚と聴覚をくすぐる魅力は実写映像化ならでは。ただ、エピソードや、登場人物たちが紡ぐたくさんの言葉、心の移り変わりとがじっくりと積み重ねられていく原作漫画を思うと、作中での台詞も切り貼り、すべてを短く縮めたことにより(仕方がないことだが)テーマが不明瞭なのも否めない。槙生の複雑さと、愛に対する葛藤にもう少し注力してほしかった。
-
フランス文学者 谷昌親
他人またはそれに近い関係の2人が同居することになるという物語は珍しくはないが、この映画の場合、徐々に変化する2人の関係性が丹念に描かれていて心地よい。新垣結衣が槙生役かと当初はやや疑問を感じたが、引きこもり気味でぶっきらぼうでありながらも誠実な小説家をうまく演じているし、朝役の早瀬憩は、その初々しさが槙生といいバランスを生み、高校でのミニライブのシーンにも活かされている。スタッフやキャストの充実した仕事ぶりがそのまま画面に反映しているかのようだ。
-
映画評論家 吉田広明
新垣と早瀬の二人が一緒に暮らすことで共に変化するドラマ。ただ、死んだ母=姉がどういう人物かが不明瞭なため、二人が迎える変化の違いが明確な像を結ばない。新垣から見れば、姉は彼女を抑圧した「世間一般」=仮想敵ゆえ、姉との和解とは世間を知り大人になることを意味する。そんな変化は必要だったかの疑問は措き、理解は可能。一方早瀬の視点からすれば母への屈託はない以上、母を嫌った新垣=叔母の視点を通じて母を見ることがもたらした変化がどんなものなのか今一つ判然とせず。
あんのこと
公開: 2024年6月7日-
ライター、編集 岡本敦史
こういう悲惨な現実があること、負の構造から抜け出せない人間の痛みを伝えたいという意欲はこれでもかと伝わる入魂の力作である。ただ、もはや時代的に、問題提起だけでは足りない気もする。ソーシャルワーカー的な視点が作り手自身にもっとほしい。社会を変えたいという思いより、悲惨な現実を見せつけたいという熱量が上回っている感もある。また、不祥事を起こした人間の悔悛を描くより、週刊誌報道のケア不足に物申すのが先立ってしまうのは、まさに業界の問題点そのものでは。
-
映画評論家 北川れい子
コロナ禍での実話をべースにしたそうだが、主人公・杏の生活環境が、昨年の秀作「市子」とかなり類似しているのはあくまでも偶然だろう。団地住まい。無職で男出入りの激しい母親。寝たきりの家族。市子は巧みにそんな環境から逃げ出して自分の人生を生きようとしていたが、杏はそこまで強くない。家族の生活費は杏が売春で稼ぎ、しかも杏はシャブ中。そんな杏がある警官に出会い自立の道を歩み出すのだが。入江監督のリアルに徹した演出と、河合優実の心身を投げ出したような演技は痛ましくも力強い。
-
映画評論家 吉田伊知郎
コロナ禍に埋もれた実際の事件を掘り起こすのは良いとしても、現実の事件に対して虚構が追随するだけになっている。今や竹中直人と同枠の佐藤二朗のシリアスかつふざけた演技は虚構ならではの存在を持つはずだが、作者がどう捉えているのかわからず。河合優実が隣人の早見あかりから幼児を押し付けられる後半のフィクション部分は、早見の身勝手さと作者のご都合主義に呆れるのみ。好調の河合にしても、彼女ならこれくらいは演じられるだろうと思えてしまい、驚きがない。
スケジュールSCHEDULE
 映画公開スケジュール
映画公開スケジュール
- 2024年7月27日 公開予定
-
新橋探偵物語2 ダブルリボルバーラヴ
東京・新橋を舞台に四十八手の奥義を駆使して謎に挑むセックス探偵の活躍を描いた「新橋探偵物語」シリーズの3作目。セックス探偵兼役者のハテナシは撮影現場で働く美緒奈に一目惚れするが、そこには恐るべき罠が仕掛けられていた。長野こうへいが前作に続き主人公の果梨玉男をフレッシュに演じる。新ヒロイン・美緒奈には『全裸監督』『TOKYO VICE』の川上なな実。2022年、ピンク映画の老舗・大蔵映画が、従来のR18+作品とは別にR15+バージョンを製作・配給するプロジェクト「OP PICTURES+フェス2022」にて上映。2024年7月に単独劇場公開。 -
今、僕は嘘をついている
数々の作品の助監督などでキャリアを積んだ浦川公仁の初監督作品。かつての所属劇団が行う“バケモノ伝承”検証の撮影に参加した江藤秀春は、現場でバケモノに遭遇。仲間が次々と襲われ、逃げ出した秀春は警察に助けを求めるが、警察は彼の話を信じてくれず……。出演は数々の舞台で活躍する関口滉人、荒井まい。 -
ブーディカ 美しき英雄
「オブリビオン」のオルガ・キュリレンコ主演による歴史アクション。紀元1世紀。イケニ族の王・プラスタグスが殺害され、土地と財産はローマ帝国に奪われる。王の妻ブーディカは、悲しみに暮れながら復讐の炎をたぎらせ、ローマ人の手から祖国を取り戻すことを誓う。監督は「ガンズ&バレッツ CODE:White」のジェシー・V・ジョンソン。新宿シネマカリテで開催される「カリテ・ファンタスティック!シネマコレクション(R)2024 THE FINAL」(2024年7月12日~8月8日)にて上映。
 TV放映スケジュール(映画)
TV放映スケジュール(映画)
- 2024年7月27日放送
-
18:30〜20:54 BSジャパン
釣りバカ日誌12 史上最大の有給休暇
-
19:00〜21:10 BS12 トゥエルビ
アンブレイカブル
-
21:00〜23:12 BS松竹東急
マイケル・ジャクソン THIS IS IT
-
21:00〜22:54 BS-TBS
マッドマックス
- 2024年7月28日放送
-
12:24〜14:30 BS松竹東急
プロゴルファー織部金次郎3 飛べバーディー
-
18:30〜21:00 TOKYO MX
犬神家の一族(1976)
-
19:00〜20:54 BS日テレ
ランボー3 怒りのアフガン